最近の投稿
魔力の象徴としての「ヒョウ柄」:映画『媚薬』(1958年)の魔女ギルの衣装とインテリアから見る50年・・・映画『媚薬』(1958年)の中のビートニクな魔女とジャズが流れる占星術クラブ
「醜い老婆」から「若い女性」の姿へと変わっていく魔女(witch): 映画『オズの魔法使い』(193・・・
男性支配の物質主義的な世界の中で女性たちが求めること:映画『紳士は金髪がお好き』で「ヒョウ柄」の衣装・・・
記号としての「アニマル柄」:1934年の映画『特急20世紀』と1945年の『失われた週末』の中で「ヒ・・・
カテゴリ
フード&ドリンクビデオ・ゲーム
映画ポスター
ブック・カバー
ファッション
映画
インテリア
建築
音楽
ミュージック・ビデオ
コマーシャル映像
車・バイク
テレビ・シリーズ
アニメーション
アーカイブ
2024年1月2023年12月
2023年11月
2023年7月
2023年6月
2023年5月
2023年4月
2023年3月
2023年2月
2023年1月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
ブログについて
映画やTVドラマなどを観ていて、その中で流れてくる音楽、撮影に使われた建築やセットのデザイン、舞台の背景となるインテリア、登場人物が手にしているガジェットやプロダクトなどが気になったことはありませんか?
このブログでは、映画やTVドラマの中に登場するさまざまなものを調べて紹介していきます。そうしたものにも目を向けてみると、映画やTVドラマが今まで以上に楽しくなるはずです。映画、TVドラマ、音楽、建築、インテリアのどれかに興味がある方に、また自分と同じようにそのどれもが寝ても覚めても好きでたまらないという方に、面白いと思ってくれるような記事を発見してもらえたらという思いで書いています。
執筆者:伊泉龍一(いずみりゅういち)
ブログ以外には、以下のような書籍の翻訳をしたり、本を書いたりもしています。

ショーン・レヴィ著 伊泉龍一訳
『レディ・ステディ・ゴー! 60sスウィンギン・ロンドン』
伊泉龍一 (著)
『スピリチュアリズムの時代 1847-1903』
ポール・ガンビーノ (著), 伊泉 龍一 (監修, 翻訳)
『死を祀るコレクション:モダン・ゴシックという生き方、その住まい』
ドン・ラティン著 伊泉 龍一訳
『至福を追い求めて ―60年代のスピリチュアルな理想が 現代の私たちの生き方をいかに形作っているか』

ロバート・C・コトレル 著 伊泉 龍一 訳
『60sカウンターカルチャー ~セックス・ドラッグ・ロックンロール』

ドン・ラティン 著
『ハーバード・サイケデリック・クラブ ―ティモシー・リアリー、ラム・ダス、ヒューストン・スミス、アンドルー・ワイルは、いかにして50年代に終止符を打ち、新たな時代を先導したのか?』

デヴィッド・ヘップワース 著
『アンコモン・ピープル ―「ロック・スター」の誕生から終焉まで』

サラ・バートレット 著
『アイコニック・タロット イタリア・ルネサンスの寓意画から現代のタロット・アートの世界まで』
映画『トロン』の起源となったスティーヴン・リズバーガー監督のアニメーション広告とアーケード・ビデオ・ゲーム「ポン」――アーケード・ビデオ・ゲーム黄金時代と『スペースインベーダー』。
ビデオ・ゲーム 映画ポスター 映画 音楽 ミュージック・ビデオ テレビ・シリーズ / 2023.02.13
このブログの以前の記事で、1982年の映画『トロン(Tron)』製作以前のスティーヴン・リズバーガー(Steven Lisberger)監督が、1973年に製作した短編アニメーション映画『コズミック・カートゥーン(Cosmic Cartoon)』を掲載しました。その際、ついついイギリスのプログレッシヴ・ロック・バンド、ピンク・フロイド(Pink Floyd)の曲の映像を製作したイアン・イームズ(Ian Eames)監督の話に移ってしまったせいで、リズバーガー監督の話が書き足りないまま終わってしまいました。なので、今回はその記事の終わりでも予告した通り、映画『トロン』製作前のリズバーガー監督についての話に戻りたいと思います。
ここで映画『トロン』をご覧になっていない方のために言うと、古い映画ではありますが、いくつかの点で、今もなお改めて見直す価値があります(と個人的には思っています)。
あ、でも言っておきますが、ストーリー自体の面白さを期待すると、もしかすると「つまらかった」と思われる可能性も大いにあります。ですが、ジェフ・ブリッジス(Jeff Bridges)演じる主人公ケヴィン・フリン(Kevin Flynn)が実験用レーザーによってデジタル化され、コンピューターの中へアップロードされるという製作当時からすると非常に斬新な設定に加えて、そのデジタル領域の世界を黒色の背景とネオンの光で視覚化した革新的な映像に、ぜひとも注目してほしいのです。
まず、1982年の公開当時の『トロン』のトレイラーを掲載しておきます。ご覧になっていない方は以下をご覧ください。子供の頃観たという方も、懐かしい気分に浸りながらどうぞ。
ご覧のような形でデジタル空間を視覚化した『トロン』が劇場公開されたのは、先ほども述べたように1982年です。
とはいえ、「1982年」という時代がピンとこない方もいらっしゃると思いますので、あえて書きます。
マイクロソフトのOS「Windows」も生まれてなければ、ましてや今日のような形でのインターネットも存在しなければ、CGIの技術もいまだ本格化する前のことです。
ついでに言えば、今では誰もが口にするようになっている「サイバースペース(Cyber-space)」という語を、SF作家のウィリアム・ギブソン(William Gibson)が短編小説集『クローム襲撃(Burning Chrome)』の中で使用したのと同じ年のことです。
そんな時期に作られた映画『トロン』は、人工知能、デジタル ID、巨大テック企業の支配等々の今日的な問題を、すでに扱っているのです。そういう意味においても映画『トロン』は先駆的な映画だったわけです。
それにしてもリズバーガーは、いかにして映画『トロン』のアイデアを思い付いたのでしょうか? では、まず以下をご覧ください。
プレイ中の球の動きをじっくりと追っていると案外ハラハラしますよね。とはいえ、現代(今これを書いているのは2023年2月)の最新のビデオ・ゲームを見ている私たちからすると、黒い背景で白いパドルを移動させて、白い球を打ち返すという、このきわめてシンプルな動きのみの画面は原始的としか言いようがありません。
ですが、今や現実以上に美しいとも言えるグラフィックを備えるまでに進化した現代のビデオ・ゲームの祖先、あるいはその最初期の胎動だと思ってみると、何とも言えぬ感動を覚えるのは私だけでしょうか?
これはコンピューター・エンジニアのアラン・アルコーン(Allan Alcorn)によって作成され、アメリカのビデオ・ゲーム開発会社アタリ(Atari)からリリースされた『ポン(Pong)』という卓球をシミュレートしたアーケード・ビデオ・ゲームです。最初にリリースされたのは1972 年で、商業的に成功した最初のビデオ・ゲームとなりました。
で、なぜここで『ポン』を紹介したのかと言うと、後に映画『トロン』で描かれることになるコンピューター内部の仮想空間で繰り広げられる戦闘シーンの着想の源が、実はここにあるからなのです。
映画『トロン』をご覧になったことがない方は、以下の実際の戦闘シーンをどうぞ(2分40秒のあたりから開始されます)。『ポン』の動きから発展したことが、お分かりいただけるはずです。
正直なところ、戦闘シーンとしての迫力はまったくもって欠けています。ですが、暗闇を背景にした光のラインとごく単純な電子音の効果で独特の不思議な世界が作り出されています。
では、もう一つ別の映像をご覧ください。こちらはスティーヴン・リズバーガーが1977年に設立したリズバーガー・スタジオズ(Lisberger Studios)製作のFMラジオ局WGCLの宣伝用アニメーション映像です。
いかがでしょうか? こちらのアニメーションが製作されたのは1979年なので、映画『トロン』公開の3年前です。
衛星の電源が入りエネルギーのビームが発射され、前景の地面に当たって爆発します。そして、その粉塵が光の戦士へと変化します。さらに光の戦士は 2 枚のディスクを投げ、戻ってきたそれらをキャッチします。
このディスクを投げ、暗い背景の中で黄色く光るキャラクターこそが、映画『トロン』の戦士の原型なのです。また、このアニメーション映像は、セルを通して光を露出させ、レンズに直接光を当てるバックリット(Backlit)という撮影方法で製作されていますが、同じ手法は映画『トロン』でも使われています。
DEN OF GEEKの中のRyan Lambie氏によるインタヴュー記事‘Interview: Justin Springer and Steven Lisberger, co-producers of Tron: Legacy’の中で、監督スティーヴン・リズバーグが、このアニメーション映像の中のキャラクターについて次のように語っています。
「70 年代には誰もがバックリット・アニメーションを行っていた。それはその頃のディスコの見た目だったんだよ。 で、このネオン・ラインのキャラクターを使ったら、それがトロンの戦士――エレクトロニックにふさわしいトロンーーだったら、どうかって私たちは考えたんだ。そして、何が起こったのかというと、私はポンを見て、そうだよ、それが彼の舞台だと言ったんだ」。
後に出来上がった『トロン』は、本格的にコンピューター・グラフィックスを大々的に使った最初の映画としても知られています。ただし実際のところ、CGIが映像に取り入れられているのは15分ほど(当時としては15分は前例のない長時間でした)でしかなく、このバックリットによるアニメーションと実写の組み合わせで製作されています。
ところで、『トロン』をご覧になった方はご存じのように、ジェフ・ブリッジス演じする主役のケヴィン・フリンは、ビデオ・アーケード(日本で言うところのゲームセンター)を経営していました。
以下で、フリンのアーケードが映る実際の映画のシーンをご覧ください。ちなみに、最初の方の場面の背景に流れる、いかにも「エイティーズ」という感じのサウンドは、アメリカのロック・バンド、ジャーニー(Journey)がこの映画のために提供した「オンリー・ソリューションズ(Only Solutions)」という曲です。
ここで映画『トロン』の中のケヴィン・フリンのアーケードが舞台となる場面に言及したのは、映画の公開当時、まさしくアーケード・ビデオ・ゲームが黄金時代だったということにも触れておきたかったからです。
ビデオ・ゲーム・ジャーナリストのスティーヴン・L・ケント(Steven L. Kent)氏の著書 The Ultimate History of Video Games: From Pong to Pokemon–The Story Behind the Craze That Touched Our Lives and Changed the World (Crown, 2001)によると、アメリカでのアーケード・ビデオ・ゲームの黄金時代は、1979 年から 1983 年だそうです。
で、この1979年という年は、日本のゲーム製作者、西角友宏氏が考案したアーケード・ゲーム『スペースインベーダー(Space Invaders)』の人気が、アメリカで一気に爆発した年です(日本では、前年にタイトー株式会社からリリースされています)。
また翌年には、日本のナムコから澤野和則氏によって考案された『ギャラクシアン(Galaxian)』が、またアメリカのアタリからはライル・レインズ(Lyle Rains)とエド・ログ(Ed Logg)によって考案された『アステロイズ(Asteroids)』がリリースされ、シューティング・ビデオ・ゲームが、アーケードを席巻することになります。
ビデオ・ゲームの歴史の不滅の業績とも言うべき『インベーダーゲーム』をプレイしたことがない方もいらっしゃると思いますので、以下をご覧ください。
当時のシューティング・ビデオ・ゲームのターゲットと言えば、戦車、戦闘機、戦艦などでしたが、『スペースインベーダー』では、イカやカニを模してデザインされたエイリアンの形になっています。
『スペースインベーダー』の考案者、西角友宏氏ご本人が、フランス・カストロー(France Costrel)監督のネットフリックス・オリジナルのドキュメンタリー『ハイスコア: ゲーム黄金時代(High Score)』(2020年)の中のインタヴューで語っていましたが、そのエイリアンのデザインは、イギリスの小説家H・G・ウェルズ(Herbert Wells)のSF小説の古典的名作『宇宙戦争(The War of the Worlds )』(1898年)の地球を侵略してくる火星人のイメージに着想を得たそうです。
ビデオ・ゲーム好きの方は、とっくにご覧になっているかもしれませんが、『ハイスコア: ゲーム黄金時代』は、全6話でビデオ・ゲームの発展していく様が簡潔に描かれていますので、その歴史の大まかな流れを知りたい方にはお勧めです。ひとまず以下でトレイラーをどうぞ。
『スペースインベーダー』に話を戻すと、そのエイリアンのデザインもさることながら、非常に印象的なのは、しばらく聞いていると完全に頭から離れなくなるシンプルなサウンド・エフェクトです。
「ドゥ・ドゥ・ドゥ・ドゥ、ドゥ・ドゥ・ドゥ・ドゥ」と繰り返される下降音。そして、エイリアンの数が少なくなってくるにしたがって、「ドゥ・ドゥ・ドゥ・ドゥ、ドゥ・ドゥ・ドゥ・ドゥ」のテンポが速まっていきます。実際にプレイしたことがある方なら同意してくださると思いますが、この加速していく下降音で心臓をばくつかせられ、完全な興奮状態に持っていかれてしまいます。また、発射音とインベーダーにヒットしたときの音の連続が作り出す「ピーヒョン、ピーヒョン」という音とリズム感によって、おそらくプレイヤーの脳に生理的な快感が生み出され、最後の一匹に命中させた瞬間にはエクスタシーへと至り、ついには病みつきになってしまうのだと思います。
こうした『スペースインベーダー』の画期的なサウンドがどのようにして生まれてきたのかが気になったので調べてみると、4Gameer.netの中の「タイトーサウンドかく発祥せり。「「スペースインベーダー インヴィンシブルコレクション」発売を記念し亀井道行氏&今村善雄氏にインタビュー」と題したhally氏によるインタヴュー記事の中で、サウンド・エフェクトを作り出した亀井道行氏が当時のことを語ってくださっていました。
それによると、あのインベーダーたちが迫りくる下降音は、考案者の西角氏からの「もっと重厚で心臓に響くようなものが欲しい」という要望に応えるべく、映画『ジョーズ(Jaws)』の主題曲をイメージして作られたそうです。
スティーブン・スピルバーグ(Steven Spielberg)監督の1975年の映画『ジョーズ』の中の主題曲は、映画史上、最も有名な曲の一つなのではないでしょうか? チューバーで演奏された繰り返される2音のフレーズは、おそらく誰もがどこかで聞いたことがあるのではないかと思います。作曲家のジョン・ウィリアムズ(John Williams)は、このサウンド・トラックでアカデミー賞の「最優秀オリジナル・ドラマティック・スコア」を獲得しています。よろしければ、その迫りくるサウンドを、以下で改めてお聴きください。
音だけを聴いても、心臓がばくついてきそうです。 映画ファンの方ならご存じかと思われますが、ジョン・ウィリアムズと言えば、スティーブン・スピルバーグ監督の諸作品はもちろんのこと、当時で言えばジョージ・ルーカス(George Lucas)監督の『スターウォーズ(Star Wars)』(1977年)などのスコアも手掛けています。ということからすると、70年代後半から80年代にかけて映画を観ながら子供時代を過ごして大人になった人の思い出の中には、ジョン・ウィリアムズのサウンド・トラックがとてつもなく深く染み込んでいるはずです。
それはそうと、映画『ジョーズ』の宣伝ポスターも一目見て強い印象が残りますよね。この絵自体も映画史の中の最もアイコニックな作品の一つなのではないでしょうか? 画像は、ITMの中のChristina Sanza氏の記事‘Roger Kastel’s original “Jaws” artwork recreated for two limited edition screen prints by Mondo, on sale July 3’から引用しました。

絵を描いたのは、アメリカのイラストレーターのロジャー・カステル(Roger Kastel)です。元々は映画の原作となったピーター・ベンチリー(Peter Benchley)の小説『ジョーズ』 (1974年)のペーパーバック版の表紙を飾った絵でした。それが映画用の宣伝にも使われることになったのです。以下の画像をご覧ください。CWの中のBen Marks氏の記事‘Real Hollywood Thriller: Who Stole Jaws?’から引用しました。

向かって左側はダブルデイ(Doubleday)社から出版された『ジョーズ』のハードカーバー版の表紙です。こちらのヴァージョンは、本やレコードのカヴァーのデザイナーであるポール・ベーコン(Paul Bacon)によってデザインされました。続いてバンタム(Bantam)社から出版されたペーパーバック版は真ん中で、先ほど述べたようにロジャー・カステルの作品です。で、向かって左側がユニバーサル・スタジオの映画用のポスターです。
ハードカバー版とペーパバック版を見比べると、構図自体は一緒なのが分かります。ですが、モノクロの前者の絵では泳いでいる女性の下から巨大なサメが静かに迫ってくる不気味な感じが伝わってきます。黒の背景が不安感を助長し、これはこれで訴えてくるものがあります。一方、カラーの後者では泳いでいる女性の下から巨大なサメが獰猛に口を開いて、まさに襲いかかろうとしている危機感が強められています。確かに映画の派手な宣伝には、後者のデザインの方がぴったりですね。
ちなみに、ペーパーバック版の絵を描いたロジャー・カステルは、ジョージ・ルーカス監督の1980年の映画『スターウォーズ/帝国の逆襲(The Empire Strikes Back)』の宣伝用ポスターの絵なども描いています。この辺りの話は、また別の機会に。
ついつい映画『ジョーズ』の話に逸れ過ぎてしまいました。話を『スペースインベーダー』のサウンド・エフェクトの話に戻します。
前述のインタヴュー記事によると、弾がインベーダーにヒットしたときの音は、同時期にタイトーからリリースされた『ブルーシャーク(Blue Shark)』というゲームの「タコの出現音を遅くした」ものだそうです。気になる方は、どうぞ以下でご確認ください。
「ダイバーも撃つなんて!」と一瞬思ったら、ダイバーを売ってしまうと-500点になっていましたね。それにしても同時にリリースされたこの『ブルーシャーク』と比べると、『スペースインベーダー』の方がかなりゲームとして進化していて、人気が出た理由も分かりますね。
またしても話がどんどん逸れていきますが、こうした『スペースインベーダー』の印象的なサウンド・エフェクトを使ったディスコ・サウンドも、当時の日本では作らていました。そのままズバリの曲名の「ディスコ・スペース・インベーダー」です。この時代にビデオ・ゲーム好きだった人の中には、ラジオで聴いて覚えている、あるいはレコードを買ったという人もいらっしゃるのではないかと思います。試しにどうぞお聴きください。
『スペースインベーダー』のサウンド・エフェクトが鳴りまくる中、ファンキーなベースの印象的な音の動きに誘われて、つい踊りたくなってしまいますね。
プロデューサーには、前述の『スペースインベーダー』のサウンドの生みの親、亀井道行氏の名前がクレジットされています。
演奏はファニー・スタッフというグループですが、その中のメンバーでベース・ギターを担当し、作詞・作曲にクレジットされている遠藤敬三氏は、1978年から80年代にかけての日本のプログレッシヴ・ロック・バンドのクロスウインド(CROSSWIND)でベース・プレイヤーだった方です。
その後、遠藤氏は1992年から「わっぱがっぱ(WAPPA GAPPA)」というバンドを結成し、1996年にファースト・アルバム『邪馬台国』、1998年にセカンド・アルバム『神話』、2004年にサード・アルバム『我破』をリリースしています。私自身もファースト・アルバムの『邪馬台国』のCDを随分と久しぶりに、しかも偶然にも聴いていた矢先に、今回の記事を書いていて、遠藤氏が前述の「ディスコ・スペース・インベーダー」にかかわっていたのだということを知って実は驚きました。
今回ついでにプログレッシヴ・ロックのファン向けのリソース・サイト、PROGARCHIVESを調べてみたところ、わっぱがっぱのレヴューが掲載されていましたが、「女性ヴォーカリスト、山本圭美の声が素晴らしい」とも評されていました。
ちなみに、お聴きになったことがない方のために言うと、ジャズやフュージョン的な要素もあるシンフォニックなサウンドですが、欧米のプログレッシヴ・ロック・バンドには間違いなく出すことができないオリジナリティを強く感じられます。しかも聴き手の想像力をかきたてる歌詞を、ありがたいことにも日本語でしっかりと歌われています。わっぱがっぱのことについて詳しくは、オフィシャル・サイトをぜひご覧ください。
話が大きく脱線したままですが、そのまま気にせず突き進んで話をすると、アーケード・ビデオ・ゲームの『スペースインベーダー』のサウンドを取り入れた曲は、日本以外でも作られています。
オーストラリアのプレイヤー・ワン( Player [1])というグループが「スペース・インベーダーズ(Space Invaders)」という曲を1980年にリリースし、本国で大ヒットさせました。以下で、そのミュージック・ビデオをご覧ください。
こちらも『スペース・インベーダー』のサウンド・エフェクトが使用されていますが、ご覧の通り、映像的には映画『スターウォーズ』を始めとする70年代の宇宙を舞台にしたSF映画をあからさまに彷彿させます。
その点からすると、この曲は、1977年から始まった「サイファイ・ディスコ(Sci-fi Disco)」(SFの影響を受けたディスコ)の流行の余波に、最新のビデオ・ゲームの要素が加えられた作品だと言えるでしょう。
サイファイ・ディスコ・ブームの始まりとなったのは、1977年にリリースされ、アメリカで大ヒットしたミーコ(Meco)のアルバム『スターウォーズ・アンド・アザー・ギャラクティック・ファンク(Star Wars and Other Galactic Funk)』です。その中のシングル曲「スターウォーズ・テーマ/カンティーナ・バンド(Star Wars Theme/ Cantina Band)」は、同年10月のビルボード・チャートで一位となりました。どうぞ以下でお聴きください。
映画『スターウォーズ』のファンならば、始まった瞬間から、あの反乱軍の活躍を目に浮かばせる、勇気を鼓舞するメロディーに心躍らされますよね。もちろん、映画の方のオリジナルのスコアは、先ほどの映画『ジョーズ』と同じくジョン・ウィリアムズ作曲です。
ジョージ・ルーカス監督の映画『スターウォーズ』が公開されたのは1977年です。ミーコは映画を観て感動し、すぐさま『スターウォーズ・アンド・アザー・ギャラクティック・ファンク』を製作したわけです。この辺りの事情は、自分自身が訳した本をを宣伝するようで気が引けますが、ジェイソン・ヘラー(Jason Heller)氏の著書『ストレンジ・スターズーーデヴィッド・ボウイ、ポップ・ミュージック、そしてSFが激発した十年(Strange Stars: David Bowie, Pop Music, and the Decade Sci-Fi Exploded )』に詳しく書かれています。同書の中でヘラー氏は、このミーコの曲を非常に高く評価し、次のように述べています。
「モナード【ミーコの本名はドメニコ・モナード】はウィリアムズ【映画『スターウォーズ』のスコアを作曲したジョン・ウィリアムズのこと】の元々の音楽をきめ細かに再考し、ぞくぞくさせるものでありながら、主題的には複雑に改変したものを巧妙に作り上げた。……その当時一般的にみなされていたような商業的に安っぽい利用ではなく、むしろ『ギャラクティック・ファンク』は非常に贅沢なトリビュートだった」(【】内は筆者)。
ミーコが大ヒットした後、その成功を追うように、すぐさま他のアーティストたちも続々とSF的な要素を取り入れたディスコの曲を作り始め、サイファイ・ディスコの波が生まれてくることになりました。
ところで、アーケード・ビデオ・ゲームの『スペースインベーダー』のサウンド・エフェクトをポピュラー・ミュージックで引用したのは、ディスコ・サウンドだけではありませんでした。
例えば、イギリスのロック・バンドのプリテンダーズ(Thee Pretenders)の1979年のアルバム『プリテンダーズ(Pritenders)』の中の「スペース・インベーダー(Space Invader)」にも、『スペースインベーダー』のサウンド・エフェクトがサンプリングされています。お聴きになったことがない方は、以下でどうぞ。先に言っておってきますが、『スペースインベーダー』のサウンド・エフェクトが聞こえてくるのは、曲の終わりの部分になってからです。
完全に余談となりますが、このプリテンダーズの「スペース・インベーダーズ」は、1999年から2007年まで放映されていたHBO製作のTVドラマ『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア(The Sopranos)』のシーズン2の第11話「軟禁(House Arrest)」でも使われていました。以下で、その場面をご覧ください。
ドラムとベースのみで始まるイントロとともにトラックがゆっくりと画面の方に近づいてきて、その後に何かをやらかしてくれることへの期待を盛り上げてくれますね。そして、家の前に到着すると、トラックの後部からゴミがばらまれます。そこに至るまでのドラマの過程をご覧になった方ならうなずいていただけると思いますが、このシーン、最高にすかっとしますよね。
ちなみにですが、『ザ・ソプラノズ』をご覧になっていない方に言うと、このドラマはどのエピソードでも抜群のタイミングで、幅広いジャンルの音楽から選ばれた多様な曲が流れてきます。ジャンル関係なく無節操にいろいろな音楽を聴いてしまう方(私もそうですが)でしたら、その都度のシークエンスを見ながら「あ、この曲がきたか!」という感じで、背景に流れる曲だけでも十分に楽しめますよ。
実際、全シリーズのクリエイターを務めたデイヴィッド・チェイス(David Chase)氏は、音楽へのこだわりが相当ある方です。
VANITY FAIRの中のPETER BISKIND氏のインタヴュー記事‘THE FAMILY THAT PREYS TOGETHER’で、チェイス本人が言うには、「事前に選択した音楽に合わせてシークエンスを撮影した」こともあったそうです。しかも、最終的にドラマの中で使われる全ての曲をチェイス自身が選んでいます。『ザ・ソプラノズ』の音楽についての話題はまた別の機会にでも。
ちなみに、日本では今(2023年2月)のところ未公開ですが、60年代舞台にしたロック・バンドを組む若者たちを描いた『ノット・フェイド・アウェイ( Not Fade Away)』(2012年)という映画の監督もデヴィッド・チェイスが務めています。
さて、『スペースインベーダー』関連の曲をもう一つだけ。勝手なイメージかもしれませんが、ビデオ・ゲームのようなギーク・カルチャーからは程遠そうに見えるイギリスのパンク・バンド、ザ・クラッシュ(The Clash)の1980 年のアルバム『サンディニスタ! (Sandinista!)』の中の「アイヴァン・ミーツ・G・I・ジョー」という曲です。こちらでは、『スペースインベーダー』のサウンド・エフェクトが、演奏の背景でふんだんに使われています。お聴きになったことがない方は、以下でどうぞ。
話の流れが、スティーヴン・リズバーガー監督の『トロン』以前のアニメーションの話から、当時のアーケード・ビデオ・ゲームと『スペースインベーダー』、そしてそのサウンド・エフェクトが使われたポピュラー・ミュージックの話へと移り、本題とはまったくかけ離れたところにきてしまいました。
ですが、今回のアーケード・ビデオ・ゲームの話ついでにさらに言うと、映画『トロン』が公開される2年前の1980年には、岩谷徹氏によって考案された『パックマン』が日本のナムコからリリースされ、これまたアメリカでも驚異的な人気となります。
今回の記事を書きながらちょっと気になったので、当時の子供たちの『パックマン』に対する熱狂とアメリカのポピュラー・カルチャーへのその影響について改めて少し調べてみると、それが思っていた以上に大きかったことに驚かされました。本題との関連で言えば、そもそも映画『トロン』自体の中にも、『パックマン』がちらっと登場しています。
ということから、次回は『パックマン』を軸にしながら、映画やドラマや音楽とアーケード・ビデオ・ゲームのかかわりについて、もう少し書いてみたいと思います。
この記事が気に入ったら下のボタンでシェア!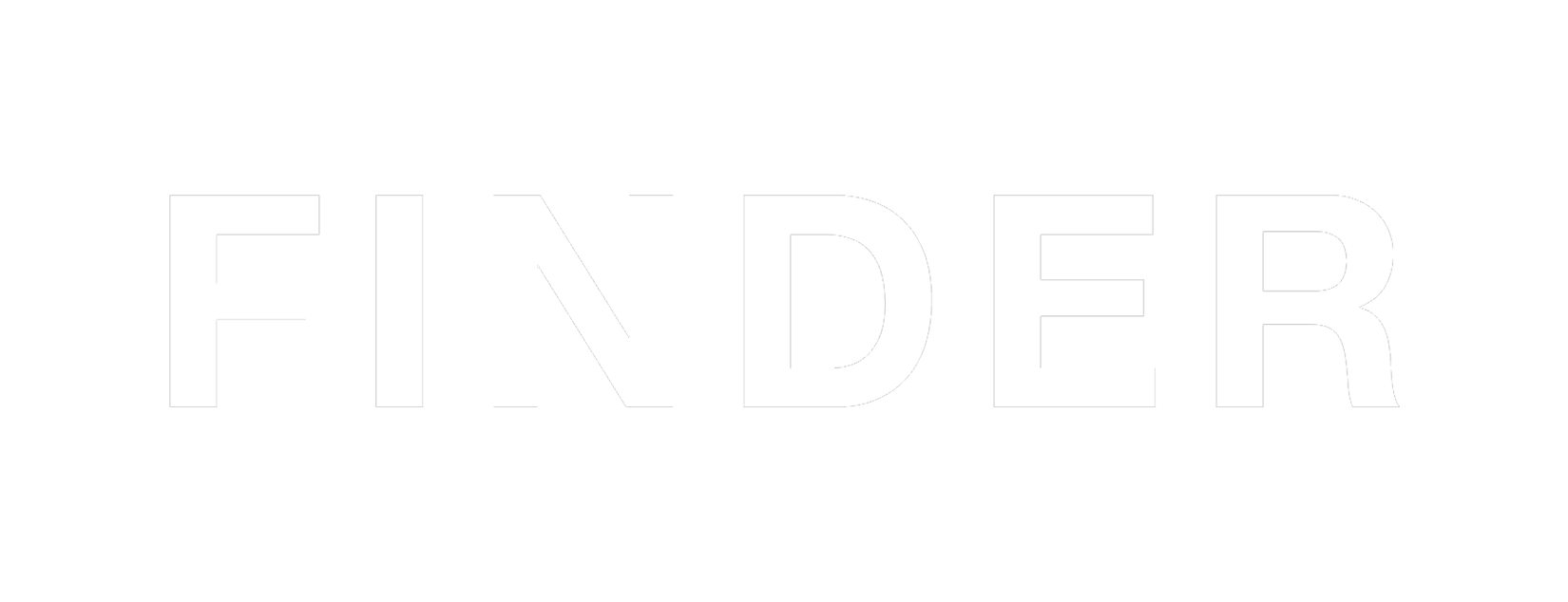 映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど
映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど





