最近の投稿
魔力の象徴としての「ヒョウ柄」:映画『媚薬』(1958年)の魔女ギルの衣装とインテリアから見る50年・・・映画『媚薬』(1958年)の中のビートニクな魔女とジャズが流れる占星術クラブ
「醜い老婆」から「若い女性」の姿へと変わっていく魔女(witch): 映画『オズの魔法使い』(193・・・
男性支配の物質主義的な世界の中で女性たちが求めること:映画『紳士は金髪がお好き』で「ヒョウ柄」の衣装・・・
記号としての「アニマル柄」:1934年の映画『特急20世紀』と1945年の『失われた週末』の中で「ヒ・・・
カテゴリ
フード&ドリンクビデオ・ゲーム
映画ポスター
ブック・カバー
ファッション
映画
インテリア
建築
音楽
ミュージック・ビデオ
コマーシャル映像
車・バイク
テレビ・シリーズ
アニメーション
アーカイブ
2024年1月2023年12月
2023年11月
2023年7月
2023年6月
2023年5月
2023年4月
2023年3月
2023年2月
2023年1月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
ブログについて
映画やTVドラマなどを観ていて、その中で流れてくる音楽、撮影に使われた建築やセットのデザイン、舞台の背景となるインテリア、登場人物が手にしているガジェットやプロダクトなどが気になったことはありませんか?
このブログでは、映画やTVドラマの中に登場するさまざまなものを調べて紹介していきます。そうしたものにも目を向けてみると、映画やTVドラマが今まで以上に楽しくなるはずです。映画、TVドラマ、音楽、建築、インテリアのどれかに興味がある方に、また自分と同じようにそのどれもが寝ても覚めても好きでたまらないという方に、面白いと思ってくれるような記事を発見してもらえたらという思いで書いています。
執筆者:伊泉龍一(いずみりゅういち)
ブログ以外には、以下のような書籍の翻訳をしたり、本を書いたりもしています。

ロバート・C・コトレル 著 伊泉 龍一 訳
『60sカウンターカルチャー ~セックス・ドラッグ・ロックンロール』

ドン・ラティン 著
『ハーバード・サイケデリック・クラブ ―ティモシー・リアリー、ラム・ダス、ヒューストン・スミス、アンドルー・ワイルは、いかにして50年代に終止符を打ち、新たな時代を先導したのか?』

デヴィッド・ヘップワース 著
『アンコモン・ピープル ―「ロック・スター」の誕生から終焉まで』

サラ・バートレット 著
『アイコニック・タロット イタリア・ルネサンスの寓意画から現代のタロット・アートの世界まで』
魔力の象徴としての「ヒョウ柄」:映画『媚薬』(1958年)の魔女ギルの衣装とインテリアから見る50年代の社会が求める「女性らしさ」の規範
ファッション 映画 インテリア テレビ・シリーズ / 2024.01.17

前回は1958年の映画『媚薬(Bell, Book and Candle)』の中でキム・ノヴァク(Kim Novak)演じるビートニクな魔女とジャズの流れる占星術クラブの話を書きました。また前々回は映画『オズの魔法使い(The Wizard of Oz)』(1939年)から『奥様は魔女(I Married a Witch)』(1942年)へと至る魔女の姿の変遷について書きました。
さらにその前の記事では映画『特急20世紀(20th Century)』(1934年)の中のキャロル・ロンバード(Carole Lombard)の衣装、映画『失われた週末(The Lost Weekend)』(1945年)の中のジェーン・ワイマン(Jane Wyman)の衣装、映画『紳士は金髪がお好き(Gentlemen Prefer Blondes)』(1953年)の中のマリリン・モンロー(Marilyn Monroe)の衣装を取り上げて、1930年代から1950年代その時代のファッション・デザインとしての「ヒョウ柄」が意味することを考えてみました。今回はそこに戻って再び「ヒョウ柄」の話です。
では、前回言及した映画『媚薬』の中のキム・ノヴァク演じる魔女ジルが身に着けている衣装をまずはご覧ください。

赤い手袋とスカーフにヒョウ柄のケープを身に着けていますね。前回述べたように、魔女のギルは飼い猫のパイワケットの力を借りて魔法をかけます。そんな彼女にとって、ネコ科の動物のヒョウ柄の衣装はまさしくふさわしい衣装に思われます。
この場面の後、以下のように目を引き付ける鮮明な赤いドレスを着たギルはパイワケットとともに、この映画の中での最大の魔法を使います。

さらに次の衣装をご覧ください。これは恋人のシェプのオフィスを訪ね、今まで隠していた自身が魔女であることを告白する場面です。

このフード付きの黒いドレスは、確かに古典的な魔女のイメージにだいぶん近づいた衣装のように思えます。ここで注目すべきは、その上にはおっているケープの裏地がヒョウだという点です。
しかも興味深いのは、自分が魔女であり、愛の魔法を使ったことをいよいよ告白する段階で、以下のように椅子(向かって左下)にかけたケープのヒョウの面が表に見えることです。あたかもそれはジルが隠していた魔力の暴露を象徴しているかのようにも思えます。

そして、自分が魔女であることを説明した後に、部屋を去っていく場面では黒地の方ではなく、部屋に入ってきたときは裏側だったヒョウ柄の面を堂々と見せながら出口の扉の方に近づいていきます。

この一連の場面では自分が魔女であり、魔力を使うことができることを告白することとヒョウの裏地を完全に外側に見せることが同期しています。すなわち、ここでのヒョウ柄は、まさに彼女の魔力を暗に象徴しているようにも見えるわけです。
この場面が映画の結末へと向かっていく重要な転換点となります。その後、ジルは魔法の力を失ってしまいます。それとともにパイワケットも彼女の元から逃げ出していきます。
そもそもこの映画では、魔女であることの特徴は人を愛することができず、涙を流すこともできないとされています。ですが、ギルはパイワケットを見失ったとき、自分が涙を流していることに気が付きます。つまり、ギルはもはや魔女ではなくなっているのです。そうなったのは本人が述べるように「シップとの愛に落ちてしまった」からです。

最終的に『媚薬』の物語は、ハッピー・エンディングへと向かいます。ギルとシェプはめでたく愛で結ばれます。その最後の場面でのギルの衣装に注目してみましょう。もはや前回見たようなビートニクな黒い衣装でもなければ、大胆な赤いドレスもヒョウ柄のケープも身に着けていません。以下をご覧ください。

ご覧の通り、ここでのギルは、薄い緑色のとても柔らかそうなブラウスに、ウェストが絞られ、ふわっとしたスカートを履いています。つまり、当時の(すなわち1950年代末)の典型的な女性らしい(しかも古風で従順そうな)服装に変わってしまっているのです。もはやギルは危険なファム・ファタールではなくなっっているどころか、郊外の家で夫の帰りを待つ新婚の主婦の姿のようにも見えてしまいます。
さらにギルの経営するショップも様変わりしてしまっています。元々のショップではアフリカのプリミティヴでエキゾチックで少々不気味な仮面や彫刻を元々販売していました。以下で元々のショップをご覧ください。

ですが、今やそれがフラワー・アレンジメントや貝殻などが置かれたフェミニンさが充満するごっちゃりとしたショップに変わってしまっています。以下をご覧ください。

『媚薬』のハッピーなエンディングは、前回取り上げた1942年の映画『奥様は魔女』と同じ教訓、すなわち理想の男性との愛を手に入れて本当の女性の幸せへと至るには、男性中心主義的な規範に合わせた理想の女性になる必要がある(=魔力を手放さなければならない)ことを訴えているようにも思えます。実際にジェップがギルを受け入れ、二人が最後に愛で結ばれたのは、彼女が魔力(彼女を独特の存在にしていたものすべて)を失ったことを知った後です。
GEEK GIRL AUTHORITYの中の記事‘Classic Film Through a Feminist Lens: BELL BOOK AND CANDLE’でKimberly Pierce氏は、この映画を次のように評しています。
「キム・ノヴァクは楽しくて興味深いギリアンを演じて輝いている。そして、彼女のキャラクターは、ハリウッド映画で始まったばかりの進化を示している。 突然、女性のキャラクターはわずか 10 年前よりも深みと主体性を持つことになった。だが、ハリウッドの不可欠な要素として、ハッピーなエンディングがすべてに勝る。そのため、その興味深いキャラクターの働きの一切が無視され、ギリアンはハッピーなエンディングを迎えることができる前にメタフォリカルに力を去勢されてしまうのである」。
最終的に「本物」の愛を手に入れ、シェプと抱きあって涙を流すギル、つまり男性社会が求める女性らしさの規範に従うことで主体性や自由や力を失ったギルには、もはや前回見たビートニクのブラックの服も、また飼いならされることのないワイルドな性質をイメージさせると同時に魔法の力を象徴するヒョウ柄のケープも、またアフリカのプリミティヴなアートも、もはやまったくふさわしいものではなくなったわけです。
前々回見た映画『奥様は魔女』も今回の『媚薬』も愛と結婚、すなわち「女性としての真の幸福」を手に入れる代償として、魔法の力を失うことになりました。この点に留意すると、前々回に言及したテレビ・シリーズの『奥さまは魔女』(1964年から1972年)が非常に興味深く思えてきます。
というのも、このコメディ・ドラマ『奥さまは魔女』のエリザベス・モンゴメリー(Elizabeth Montgomery)演じる魔女サマンサ・スティーブンスは、映画『奥様は魔女』のジェニファーや『媚薬』のギルとは異なり、結婚しても魔法の力を失うことはありません。そして、人間の世界と魔女の世界の狭間で生活をします。この点と関連して映画史家のヘザー・グリーン(Heather Greene)氏は『奥さまは魔女』を次のように評しています。
「『奥さまは魔女』には、1960 年代後半を特徴づける隠れされた文化的意味が込められている。 核家族とジェンダー政治に課せられた課題のため、これは概して最初のフェミニスト番組とみなされている。魔法(Witchcraft)は観客を引き付けるための単なる遊び心のある仮面である。この番組は、拡大するフェミニスト運動と公民権運動のための寓話である」(Heather Greene, ‘Representations of the Hollywood Witch: 1950-1968’ in THE WILD HUNTより)。
前回言及した1950年代のビートニクの時代に続き、1960年代後半のアメリカでは既存のあらゆる社会規範や政治・経済体制に異議を唱える若者たちによる「カウンターカルチャー」の大きなムーヴメントがやってきます(ちなみに、以前にこのブログの中で書いた映画『フォレスト・ガンプ/一期一会(Forrest Gump)』(1994年)に関する記事の中で、フォレストが大人になった頃の時代背景として1960年代のカウンターカルチャーに少し触れたことがあります。詳しくは「映画『フォレスト・ガンプ/一期一会』の中のジミ・ヘンドリックスの「ヘイ・ジョー」と1960年代後半のアメリカのカウンターカルチャー」をご覧ください)。
次回は時代を1950年代から1960年代に進め、その時代のポピュラー・カルチャーの中でヒョウ柄が持っていたイメージの変遷を追ってみたいと思います。
最後に、今回の映画『媚薬』のついでとして、猫好きの方のための話を書いておきます。前回の記事に書きましたが『媚薬』の中には、魔法の場面で重要な役割を果たすパイワケットという猫が登場します。で、以下のシーンをご覧ください。ギルの部屋で電話をしているジェームズ・ステュアート(James Stewart)演じるシェプの姿の隣に見える隣にパイワケットを描いた絵がかけてありました。

この絵は誰の作品なのかと気になったので調べてみました。ですが、残念ながら分かりませんでした。ただし、Film AND Furnitureの中のPAULA BENSON氏の記事‘#FFFind: Pyewacket cat painting in Bell Book and Candle’を読むと、この絵をカナダの画家ジョン・ライス(John Lyes)が忠実に再現した商品がFine Art Americaで販売されていることが書かれていました。以下をご覧ください。画像はFine Art Americaの商品ページから引用しました。

このパイワケットを描いたジョン・ライスの作品は、マグカップはフォンケースやTシャツ等々にも印刷されて販売されていました。このブルーとレッドの配色を見ていると、80年代的なインテリアが好きな人の部屋にも合いそうな気がします。「魔女と猫が好き」という女性の方だったら、この絵を部屋に飾ってみたくはなりませんか?
ところで、インテリア好きの方の中で、先ほどのシップが電話をしている場面に映っていたちょっとアジアな趣を感じるウォール・ランプが気になった方はいませんか?
おそらくアメリカのライティング・デザイナーのジェラルド・サーストン(Gerald Thurston)がアメリカのライトリア(Lightolier)社のためにデザインされた50年代後半のウォール・ランプだと思われます。以下をご覧ください。画像は1st DIBSの商品ページから引用しました。

細かい話をすると、映画『媚薬』のウォール・ランプとこの写真のウォール・ランプを見比べると、シェードを吊るしている縦のラインの長さが違うと思われた方もいるかもしれませんが、そこの部分の長さは調整可能になっています。
ジェラルド・サーストンは、1950年代から60年代にかけてライトリアのために多数の魅力的なランプをデザインしていますが、例えば以下の50年代のテーブル・ランプは個人的にかなり好みです。画像は1st DIBSの商品ページから引用しました。

自然素材のシェードとウォールナットの支柱に対して、脚部までが木材だと素朴すぎる感じになりそうなところですが、そこに真鍮が使われているのが、このランプの魅力を増していることは間違いありません。
このテーブル・ランプは、映画『媚薬』の中で実際には使われていませんが、仮にギルのボヘミアンな部屋に置いたとしても間違いなくぴったりきそうです(そのうちこのブログで、自由で解放的な生き方を表現するボヘミアンないしはボーホー・スタイルのインテリアについて、いくつかの映画を取り上げてあれこれ書いてみたいと思っています)。
最後にもう一つだけ。ここ数回にわたって扱ってきた1940年代から1960年代の映画やテレビ・シリーズについて詳しく知りたい方は、koukinobaaba氏のブログ、Audio-Visual Triviaをお勧めします。各映画について、他ではなかなか読めないとても詳細な情報がまとめられているばかりか、思わず「へえー」と言いたくならトリビアな内容が盛りだくさんですので、熱心な映画ファンの方なら絶対に楽しめるはずです。
この記事が気に入ったら下のボタンでシェア!
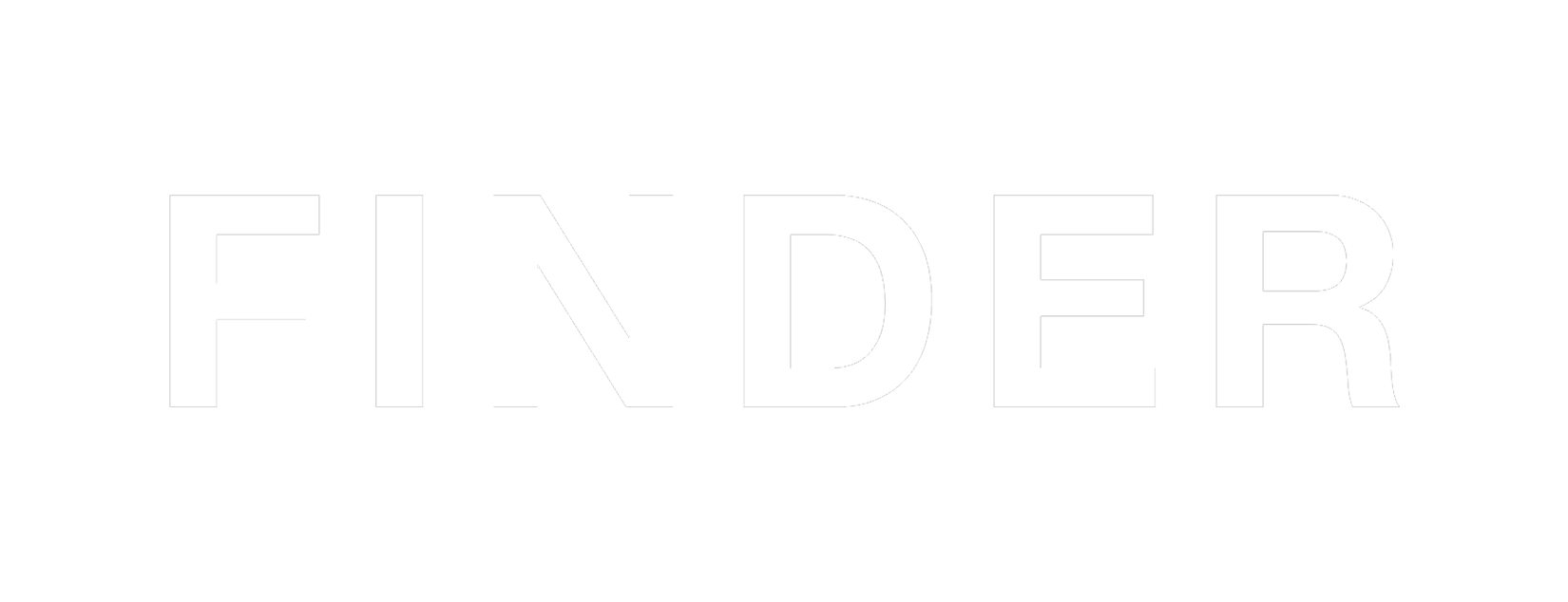 映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど
映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど


