最近の投稿
魔力の象徴としての「ヒョウ柄」:映画『媚薬』(1958年)の魔女ギルの衣装とインテリアから見る50年・・・映画『媚薬』(1958年)の中のビートニクな魔女とジャズが流れる占星術クラブ
「醜い老婆」から「若い女性」の姿へと変わっていく魔女(witch): 映画『オズの魔法使い』(193・・・
男性支配の物質主義的な世界の中で女性たちが求めること:映画『紳士は金髪がお好き』で「ヒョウ柄」の衣装・・・
記号としての「アニマル柄」:1934年の映画『特急20世紀』と1945年の『失われた週末』の中で「ヒ・・・
カテゴリ
フード&ドリンクビデオ・ゲーム
映画ポスター
ブック・カバー
ファッション
映画
インテリア
建築
音楽
ミュージック・ビデオ
コマーシャル映像
車・バイク
テレビ・シリーズ
アニメーション
アーカイブ
2024年1月2023年12月
2023年11月
2023年7月
2023年6月
2023年5月
2023年4月
2023年3月
2023年2月
2023年1月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
ブログについて
映画やTVドラマなどを観ていて、その中で流れてくる音楽、撮影に使われた建築やセットのデザイン、舞台の背景となるインテリア、登場人物が手にしているガジェットやプロダクトなどが気になったことはありませんか?
このブログでは、映画やTVドラマの中に登場するさまざまなものを調べて紹介していきます。そうしたものにも目を向けてみると、映画やTVドラマが今まで以上に楽しくなるはずです。映画、TVドラマ、音楽、建築、インテリアのどれかに興味がある方に、また自分と同じようにそのどれもが寝ても覚めても好きでたまらないという方に、面白いと思ってくれるような記事を発見してもらえたらという思いで書いています。
執筆者:伊泉龍一(いずみりゅういち)
ブログ以外には、以下のような書籍の翻訳をしたり、本を書いたりもしています。

ロバート・C・コトレル 著 伊泉 龍一 訳
『60sカウンターカルチャー ~セックス・ドラッグ・ロックンロール』

ドン・ラティン 著
『ハーバード・サイケデリック・クラブ ―ティモシー・リアリー、ラム・ダス、ヒューストン・スミス、アンドルー・ワイルは、いかにして50年代に終止符を打ち、新たな時代を先導したのか?』

デヴィッド・ヘップワース 著
『アンコモン・ピープル ―「ロック・スター」の誕生から終焉まで』

サラ・バートレット 著
『アイコニック・タロット イタリア・ルネサンスの寓意画から現代のタロット・アートの世界まで』
「醜い老婆」から「若い女性」の姿へと変わっていく魔女(witch): 映画『オズの魔法使い』(1939年)から映画『奥様は魔女』(1942年)へ
ファッション 映画 コマーシャル映像 テレビ・シリーズ / 2024.01.15

前々回は映画『特急20世紀(Twentieth Century)』(1934年)と映画『失われた週末(The Lost Weekend)』(1945年)の中でヒョウ柄の衣装が登場するシーンに目を向けながら、1930年代から1940年代のその意味を見てみました。また前回も同様に、映画『紳士は金髪がお好き(Gentlemen Prefer Blondes)』(1953年)の中でヒョウ柄の衣装が登場するシーンに目を向けながら1950年代のその意味を見てみました。
その続きとして今回も映画の中の衣装として使われている「ヒョウ柄」について書いていきます。まずは以下をご覧ください。

これは1958年のリチャード・クワイン(Richard Quine)監督の映画『媚薬(Bell, Book and Candle)』の中でキム・ノヴァク(Kim Novak)が演じている魔女ギリアンの姿です。
今回は、この『媚薬』の中での「ヒョウ柄」の持つ意味を考える前に、同映画の前後の時代に当たる1930年代から1940年代の映画、及び1960年代から1970年代のテレビの中に登場する「魔女(witch)」たちの姿へ少々目を向けておきたいと思います。
ということから聞きますが、アメリカで1964年から1972年までABCで放映されていた非常に有名なテレビ・シリーズのシットコム『奥さまは魔女(Bewitched)』をご覧になったことはありますでしょうか? 日本でも吹き替え版が何度も再放映されるほどの人気だったようです。しかも調べてみると、2004年には米倉涼子さんが魔女役を演じる日本版のリメイクもTBSで放映されていたんですね。
日本版ではなく、元のアメリカの『奥さまは魔女』を観たことがないという方は、ソニー・ピクチャーズ 公式チャンネルの中の「【特別総集編】海外ドラマ『奥さまは魔女』〈海外ドラマの大傑作!世代を超えて愛される大ヒットコメディドラマ!〉」と題した動画を以下でご覧ください。
ここで留意しておきたいのは、このドラマを通して60年代半ばから70年代初頭にかけて最も有名になったテレビの中の魔女サマンサを演じるエリザベス・モンゴメリー(Elizabeth Montgomery)の姿には外見上として魔女らしさを連想させる要素がまったく見られないという点です。ここでの魔女にはダークなイメージなどまるでなく、ごく普通のアメリカの主婦の服装をしています。彼女が魔法をかけるときにも、もはや謎めいた儀式や複雑な呪文などは必要ありません。「ピコピコピン」という可愛らしい効果音が聞こえるのみで、その魔法のシーンからおどろおどろしさや邪悪さは完全に失われています。
この記事を書いている2020年代前半の今も映画やテレビ・シリーズの中で魔女が登場することは珍しくはありませんし、その風貌や衣装も多様です。ですが、多くの人がいまだに連想する古典的な魔女の姿と言えば、円錐形のとんがり帽子を被り、箒に乗った女性という姿なのではないでしょうか?
そういった古典的な魔女の姿を多くの人々のイメージの中に植え付けた最も有名な作品と言えば、あの1939年のヴィクター・フレミング(Victor Fleming)監督のミュージカル映画の名作『オズの魔法使い(The Wizard of Oz)』でしょう。以下の同映画の4Kウルトラ・ブルーレイ版のトレイラーでは、48秒のあたりから数秒間、マーガレット・ハミルトン(Margaret Hamilton)演じる邪悪な「西の魔女」が登場します。では、ハリウッド映画史上最も有名な魔女の姿をご覧ください。
ご覧の通り、ここでの魔女は、大きなつばのある円錐形のとんがり帽子を被り、黒いマントを身に着け、爪が長く、角張った顎と鼻をした醜い老婆の姿になっています。また、2分あたりの箇所では箒に乗って空を飛んでいる姿も見られます。
この映画の中には善良な「北の魔女」も登場します(40秒あたりに映っています)。ライマン・フランク・ボーム(Lyman Frank Baum)が著し、W・W・デンスロウ(W. W. Denslow)が挿絵を描いた映画の原作となった児童文学作品の方での「北の魔女」は奇妙な白い服を着た老婦人の姿として描かれていますが、映画の中ではふんわりとしたピンクの服を着て、髪をカールさせた若い女性の姿に変わっています。以下の動画の冒頭で登場するビリー・バーク(Billie Burke)演じる「北の魔女」の姿をご覧ください。
空中から降りてくる光り輝く球体から姿を現わした「北の魔女」は、ご覧の通り、まるで妖精のようにも見える恰好をしています。
この『オズの魔法使い』以降、ポピュラー・カルチャーの中に登場する魔女のイメージは、この「北の魔女」姿ではなく、前者の「西の魔女」の方に近い姿が定着したようです。そして、その姿は若干の変化を経ながらも再生産され続けていきます。例えば、以下の動画をご覧ください。
こちらは60年代のアメリカの「ヒドゥン・マジック・ヘア・スプレー(Hidden Magic Hair Spray)」という商品のコマーシャル映像です。ここに登場する魔女のワンダは「醜い老婆」ではなくなり、邪悪さも消えていますが、とんがり帽子とマントという古典的な魔女の姿を踏襲しています。
先ほどのテレビ・シリーズ『奥さまは魔女』のサマンサの平凡な姿は、こうしたハリウッドの古典的な魔女たちとは懸け離れています。もちろん、『奥さまは魔女』の舞台となるのがファンタジーの異世界ではなく普通の人間の世界であり、かつそこに溶け込んで生活しているという設定からすると、魔女の姿も普通の女性の姿にするしかありません。後に詳しく見ていきますが、本題の映画『媚薬』でも主役の魔女ギルは、ニューヨークという都会の中で、ごく普通に生活しているというところから話が始まります。
そもそものことを言えば、『奥さまは魔女』の創作者でパイロット版の脚本を書いたソル・サックス(Sol Saks)は、映画『媚薬』を着想の基にしたそうです。さらに言えば、ソル・サックスの念頭には『媚薬』だけでなく、1942年のルネ・クレール(René Clair)監督の映画『奥様は魔女(I Married a Witch)』もあったようです(Bewitched@Harpiesbizarreの中の記事
‘A Prelude to Bewitched’を参照)
混乱のないように言っておきますが、テレビ・シリーズ『奥さまは魔女』と映画『奥様は魔女』は邦題がたまたま似ているだけで、まったく別の話です(前者の原題はBewitchedで後者の原題はI Married a Witchです)。
これら三つ(映画『奥様は魔女』、映画『媚薬』、テレビ・シリーズ『奥さまは魔女』)は、いずれも魔女を主役に置いた物語という点で共通しています。
ここで、映画『奥様は魔女』の中の魔女が、どんな姿だったのかも見ておきましょう。 まずは以下で『奥様は魔女』のトレイラーをご覧ください。
ご覧の通り、ヴェロニカ・レイク(Veronica Lake)演じる魔女ジェニファーは、普通の人間と同じ服装をしていますし、老婆どころか若いセクシーな女性です。外見上、先ほどの『オズの魔法使い』に代表されるような古典的なハリウッドの魔女らしい特徴はまったくありません(実際のところ、この映画の本編の中に登場する魔女の典型的なアイコンと言えば、空飛ぶ箒と大釜ぐらいです)。それどころか、むしろ先ほどのトレイラーでも階段の手すりを伝って滑り降りたり、上がったりする彼女の振る舞いをしている姿は、ほとんど無邪気な子供のようです。
以下の映画の一場面でジェニファーの姿を改めてご覧ください。魔女ジェニファーの美しい姿から忌み嫌われる邪悪な存在という感じはまったくしません。

フレドリック・マーチ(Fredric March)演じる恋人役のウォレス・ウーリーにもたれかかっている魔女ジェニファーの姿は、まるで父親に甘えてもたれかかる娘のような印象さえ受けます。まあ、実際のところ、フレドリック・マーチは1897年生まれで、ヴェロニカ・レイクは1922年生まれですから、25歳の年の差があります。
ところで上の画像は、Buzz Feed Newsの中のLouis Peitzman氏の記事’32 Witch Movies You Have To See’(見るべき32の魔女映画)から引用しましたが、同記事の順位付けでは、『奥様は魔女』は3位に選ばれていました。また、先ほどの『オズの魔法使い』は2位で、『媚薬』は4位といずれも高評価でした。
ちなみに、1位は 1922年のベンジャミン・クリステンセン(Benjamin Christensen)監督のスウェーデンの映画『魔女(Häxan)』でした。批評家からも非常に評価の高いクリステンセンの『魔女』については、あまりにも多くの語るべき点があるため、今回は触れないでおきます。
ところで、映画『奥さまは魔女』はコメディ映画ではありながらも、魔女は邪悪で有害であり、一般の人々の世界には入ることの許されない存在であるということが冒頭の場面で明示されます。以下でその場面をご覧ください。
タイトルに続いて「遠い遠い昔、人々がいまだ魔女を信じていた頃」と表示された後、魔女が火刑に処せられ、人々が集まっている光景が映し出されていました。映画『奥様は魔女』は全編に渡って明るく楽しいコメディでありながらも、その物語の発端にあるのは過去の魔女裁判での火刑に処せられたことへの復讐なのです。こうしたアメリカの過去の歴史的出来事としての魔女裁判へと言及することで、魔女が忌み嫌われ、排除されてきた存在であることを示唆するような場面は、テレビ・シリーズの『奥さまは魔女』の方では描かれていません。
先ほどの冒頭の場面で描かれていたように、魔女ジェニファーとその父親の魔法使い(warlock)のダニエルは、ピューリタンのジョナサン・ウーリーによって火で焼かれて灰にされ、木の下に埋められます。ただし、この映画の中では、史実としての魔女裁判がどれほど残酷だったかという点にはまったく無頓着です。むしろ火刑の後に、ちょっとふざけた感じでポップコーン売りを登場させることにより、その場面の残酷さから目をそらさせ、あくまでコメディ映画であるということを確認させています(そもそもポップコーンは17世紀のニューイングランドで本当に売られていたのでしょうか?)。
その後、舞台が1942年に変わり、稲妻が木を引き裂き、その下に長年にわたって閉じ込められていたジェニファーとダニエルの魂が解放されます。そこから復讐の物語が始まるわけです。
この『奥様は魔女』の物語の結末は、興味深いことにも本題の『媚薬』の結末と並置して考えてみたくなります。そのため、ここで『奥様は魔女』の話の筋をもう少しだけ紹介しておきます。
この世に戻ってきた魔女ジェニファーと父親のダニエルは、自分たちを火刑にしたジョナサン・ウーリーの子孫のウォレス・ウーリーを発見します。自分の祖先が行ったことに何の認識もないウォレス・ウーリーは、ただ善良な人として描かれています。
物語の舞台となる1942年、ウーリーは有力な知事候補者であり、スーザン・ヘイワード(Susan Hayward)演じるエステルとの結婚前夜を迎えていました。魔女ジェニファーは、過去の仕返しのためにウーリーを誘惑することに決めます。そこでジェニファーはウーリーに惚れ薬を飲ませようとします。ですが、それを自分が飲んでしまい、彼に夢中になってしまうのです。そこからドタバタ劇が始まることになります。
いわゆる「ネタばれ」になりますが、観ている側の誰もが予想するであろう(そうなることを期待するであろう)通りの結論を言います。最後にジェニファーとウーリーは愛で結ばれ、幸せな家庭を築きます。しかもジェニファーは「愛は魔法よりも強い」という道徳的教訓めいた台詞さえ口にします。
では、そもそもの復讐はどうなったのでしょうか? それは忘れてしまったかのように消えてしまっています。一方、過去の恨みを忘れることのない父親のダニエルは、娘とウーリーの結婚を阻止しようとしますが、結局のところリキュールの瓶の中に閉じ込められてしまいます。
そして最後のシーンでは、あたかも1940年代の社会的に求められる「良き妻」としての役割をまっとうしているかのように、長い髪をきちんとまとめて、静かに編み物をしているジェニファーの姿が映し出されます。そのジェニファーの姿には、無邪気で活発で奔放な魔女だった頃の魅力は見られません。
The Wild Huntの中の記事‘Representations of the Hollywood Witch: 1939-1950’でヘザー・グリーン(Heather Greene)氏は、この最後のシーンに注目しながら、この映画のストーリーを「第二次世界大戦中に流行したテーマのバリエーション」だと述べています。グリーン氏いわく、それらの映画では社会の期待から一時的に抜け出し、「別の道」を模索する機会を女性に与えます。ですが、最終的には「そうであるべき道」、すなわち結婚へと必ずや辿り着き、伝統的な女性の役割を受け入れることになります。この映画では、その「別の道」を象徴しているのが「魔法(witchcraft)」なのです。グリーン氏はさらに次のようにも述べています。
「最終的に、ジェニファーは「愛は魔法よりも強い」と宣言し、結果として罪深い不死の存在から家族や結婚という伝統的な生活へと導かれる。 ……「良き父親」としての適切な役割を決して受け入れない父親は、永遠にリキュールの瓶の中に閉じ込められるのである」。
同様のジェンダー的な観点から同映画を評しているzachariasの中の記事’Love is Stronger than Witchcraft: A Feminist Critique of 1942’s I Married a Witch’でKristin Jones氏は、「彼女が主体性、力、選択権を持つことを可能にしていたのは彼女の魔法だった」と指摘しています。
ここで『奥様は魔女』の最後の方のシーンの画像をご覧ください。

これは編物をしているジェニファーが、箒にまたがっている娘を心配する場面です。ここでジェニファーが「良き妻」になるために一切の魔法を放棄したということが明らかになります。つまり、魔法を放棄することが、結婚や家庭という幸せを手に入れるために必要な代償だったわけです。Kristin Jones氏は前述の記事で次のようにも述べています。
「力強い女性が立派な社会へと受け入れられるにはかなりの代償が伴う。彼女は夜空を飛ぶのではなく、セーターを編んで周りの人たちに奉仕するために箒を針と交換しなければならないのだ」。
「魔女」のままでは社会に受け入れられず、「女性」としての幸せ(愛と結婚と家庭)を手に入れることはできない。「魔女」であることをやめる、すなわち自身の主体性や力を手放すことで父権制社会の中で許容される「普通の女性」になって初めて、女性は幸せを手に入れることができる。だとしたら、もし「魔法」を放棄せずに社会的に受け入れられる「良き妻」の役割も引き受けなかったら、どうなるのでしょう?
『オズの魔法使い』の邪悪な「西の魔女」を始め、典型的な意地悪な悪役の魔女は決まって独身です。そう、愛することも結婚することもない「魔女」の末路は、孤独で性格の悪い「醜い老婆」の姿の「魔女」になることが運命づけられていると暗に語られているかのようです。
では、そろそろ今まで見てきたことを踏まえ、「ヒョウ柄」の衣装を着た魔女が登場する映画『媚薬』の方に移っていきましょう。と言いたいところですが、続きが長くなりそうなので次回にします。
最後に今回の記事の内容と関連する本を紹介しておきます。先ほど引用した記事の著者ヘザー・グリーン氏が2021年に出版したLights, Camera, Witchcraft: A Critical History of Witches in American Film and Television(2018年にMcFarland社から出版されたBell, Book and Camera: A Critical History of Witches in American Film and Televisionの拡張版)という本です。

同書は、『ライト、カメラ、ウィッチクラフトーーアメリカの映画とテレビの中の魔女のクリティカル・ヒストリー』と題名から想像できるように、サイレント映画から現代の大ヒット映画まで200を超える作品の中に登場する魔女のイメージの変遷をたどりながら、家父長制社会の中での女性の主体性とかかわる問題を鋭く分析しています。翻訳本は今のところ(2024年1月15日)出ていないようです。個人的には日本語訳も出版されるといいのにと思っている一冊です。
この記事が気に入ったら下のボタンでシェア!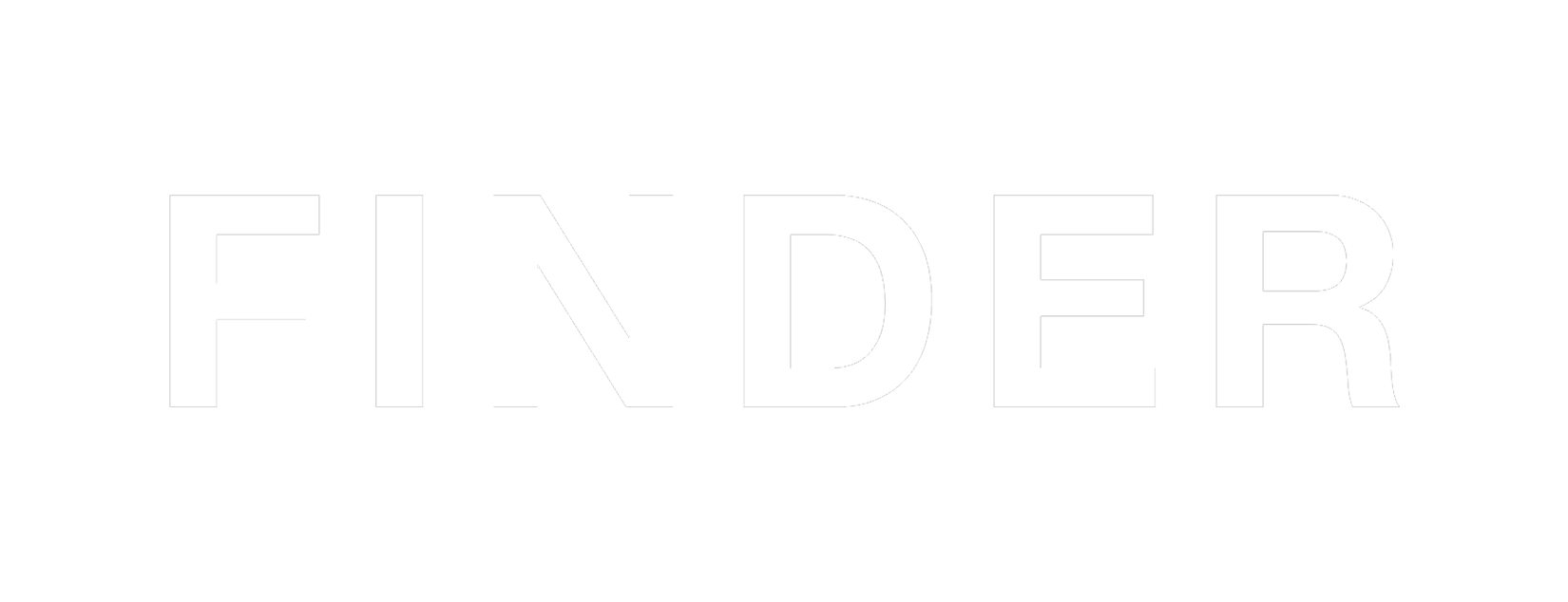 映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど
映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど


