最近の投稿
魔力の象徴としての「ヒョウ柄」:映画『媚薬』(1958年)の魔女ギルの衣装とインテリアから見る50年・・・映画『媚薬』(1958年)の中のビートニクな魔女とジャズが流れる占星術クラブ
「醜い老婆」から「若い女性」の姿へと変わっていく魔女(witch): 映画『オズの魔法使い』(193・・・
男性支配の物質主義的な世界の中で女性たちが求めること:映画『紳士は金髪がお好き』で「ヒョウ柄」の衣装・・・
記号としての「アニマル柄」:1934年の映画『特急20世紀』と1945年の『失われた週末』の中で「ヒ・・・
カテゴリ
フード&ドリンクビデオ・ゲーム
映画ポスター
ブック・カバー
ファッション
映画
インテリア
建築
音楽
ミュージック・ビデオ
コマーシャル映像
車・バイク
テレビ・シリーズ
アニメーション
アーカイブ
2024年1月2023年12月
2023年11月
2023年7月
2023年6月
2023年5月
2023年4月
2023年3月
2023年2月
2023年1月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
ブログについて
映画やTVドラマなどを観ていて、その中で流れてくる音楽、撮影に使われた建築やセットのデザイン、舞台の背景となるインテリア、登場人物が手にしているガジェットやプロダクトなどが気になったことはありませんか?
このブログでは、映画やTVドラマの中に登場するさまざまなものを調べて紹介していきます。そうしたものにも目を向けてみると、映画やTVドラマが今まで以上に楽しくなるはずです。映画、TVドラマ、音楽、建築、インテリアのどれかに興味がある方に、また自分と同じようにそのどれもが寝ても覚めても好きでたまらないという方に、面白いと思ってくれるような記事を発見してもらえたらという思いで書いています。
執筆者:伊泉龍一(いずみりゅういち)
ブログ以外には、以下のような書籍の翻訳をしたり、本を書いたりもしています。

ロバート・C・コトレル 著 伊泉 龍一 訳
『60sカウンターカルチャー ~セックス・ドラッグ・ロックンロール』

ドン・ラティン 著
『ハーバード・サイケデリック・クラブ ―ティモシー・リアリー、ラム・ダス、ヒューストン・スミス、アンドルー・ワイルは、いかにして50年代に終止符を打ち、新たな時代を先導したのか?』

デヴィッド・ヘップワース 著
『アンコモン・ピープル ―「ロック・スター」の誕生から終焉まで』

サラ・バートレット 著
『アイコニック・タロット イタリア・ルネサンスの寓意画から現代のタロット・アートの世界まで』
イアン・イームズ監督のミュージック・ビデオ(2)――デュラン・デュランの「ザ・ショーファー」と写真家ヘルムート・ニュートン。そしてリリアナ・カヴァー二監督の映画『愛の嵐』。
映画 ミュージック・ビデオ コマーシャル映像 / 2023.02.02
早速ですが、今回取り上げたいのは、デュラン・デュラン(Duran Duran)の一九八二年のアルバム『リオ(Rio)』の中の「ザ・ショーファー(The Chauffeur)」のミュージック・ビデオです。80年代初頭に「洋楽」を聴きながら「ニュー・ロマンティック(New Romantic)」のムーヴメントにはまっていた人にとっては、懐かしい曲ですね。
先に言っておくと、実はこれ、デュラン・デュランのミュージック・ビデオとしては、ちょっと変わっていて、メンバーは一人も登場せず、いわゆる「フェティッシュ」でエロティックな描写の映像がひたすら続いていきます。デュラン・デュランのファンではない、あるいは良く知らないという方でも、ヨーロッパのミステリアスで官能的な映画のワンシーンを観ている気分で、ご覧になってみていただければと思います。
それと言い忘れるところでしたが、デュラン・デュランの「ザ・ショーファー」のミュージック・ビデオを今回あえて取り上げるのは、前回の続きで、イアン・イームズ(Ian Emes)監督の作品だからです。では、どうぞご覧ください。
はっきり言ってしまうと、ストーリー自体は意味不明です。ですが、メランコリーな曲調と不可解な歌詞と性的な暗示に富む映像の組み合わせから謎めいた雰囲気が醸し出されていますね。デュラン・デュランの熱心なファンの方ならご存じのように、この曲の歌詞自体が、そもそも多様な解釈を誘発するのに十分なほど思わせぶりです。
ランジェリー姿の女性たちが、それぞれロンドンの暗い通りを通過して地下駐車場に到着します。そこで二人の女性がレズビアン的な身振りで互いに向き合って体を揺すります。それを少し離れて見ている運転手。さらにそこにやってきた三人目の女性がトップレスの姿になって踊ります。
確かにエロティックなイメージを、単に羅列した映像と言ってしまえば、そうかもしれません。ですが、このブログの以前の記事でも掲載したデュラン・デュランの「ガールズ・オン・フィルム(Girls On Film)」のミュージック・ビデオのような『プレイボーイ』誌的なこれみよがしの健全(?)なヌード映像とは、まるで趣が違います。それよりも格段にエレガントとでも言えばいいのか、あるいは、むしろよりタブーな雰囲気が漂う危険なエロティシズムとでも言えばいいのでしょうか?
Duran Duran wikiによると、このミュージック・ビデオは、1982年の秋にバンドがツアーで不在の間、ノッティング・ヒル周辺で撮影され、企画・デザイン・編集を監督のイアン・イームズが担当したとのことです。
IMDbの中のイアン・イームズのプロフィールによると、イアン・イームズは、当初「エロティックなアニメーション」の制作を依頼されたそうです。予定としては、フィルムで撮影した実写をトレースしてアニメーションにするロトスコープの手法で製作されるはずでした。ですが、撮影された映像が非常に美しかったため、アニメーションをやめて実写にすることになったようです。
ちなみに、この実写の撮影をしたのは、映画史に残る数々の傑作で撮影監督を務めているイギリス出身のシネマトグラファーのギルバート・テイラー(Gilbert Taylor)です。
映画制作の裏側に詳しい方ならば、ギルバード・テイラーと言えば、おそらくスタンリー・キューブリック(Stanley Kubrick)監督の『博士の異常な愛情 または私は如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか(Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb)』あたりを、まず思い出されるのかもしれません。
『博士の異常な愛情』をご覧になった方ならば同感していただけるのではないかと思いますが、4役を演じたイギリスのコメディアンで喜劇俳優のピーター・セラーズ(Peter Sellers)の大げさなコミック・ブック的演技に加えて、テイラーの撮影したモノクロームの映像が、当時の冷戦下の核の脅威をブラック・ユーモアで表現した同映画の全体を包み込む異様なムードを作り出すのに、非常に大きな効果を発揮しています。
まだ観たことがないという方は、以下のトレイラーで、モノクロームならではの超現実感を感じさせる陰影の世界を覗いてみてください。
爆発音と狂気をはらんだ笑い声、そしてマリンバの音とともに画面全体に現れる文字と映像が交互に繰り返される出だしからして、強烈なインパクトがありますよね。この映画のエキセントリックな内容が十二分に伝わってくる、すばらしく良くできたトレイラーなのではないでしょうか?
ついでに言うと、ギルバード・テイラーは、同じくモノクローム映像の一九六四年のリチャード・レスター(Richard Lester)監督のビートルズ主演の映画『ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!(A Hard Day’s Night)』や一九六五年のロマン・ポランスキー(Roman Polanski)監督の映画『反撥(Repulsion)』も撮影しています。
また、カラー作品で言えば、一九七六年のリチャード・ドナー(Richard Donner)監督の映画『オーメン(The Omen)』や一九七七年のジョージ・ルーカス(George Lucas)監督の映画『スターウォーズ(Star Wars)』も、テイラーが撮影監督を務めています。
そんないわば大御所のシネマトグラファーが、デュラン・デュランの『ザ・ショーファー』のミステリアスで美しいモノクローム映像を撮影したわけです。
また、Duran Duran wikiによると、このミュージック・ビデオは、ドイツ出身のファッション・フォトグラファーのヘルムート・ニュートン(Helmut Newton, 1920-2004)の作品に着想を得たそうです。確かに言われてみると、「ザ・ショーファー」のミュージック・ビデオの全編に渡る暗示的なショットからは、ヘルムート・ニュートンの女性を被写体としたエロティックな写真を想起させられます。
そう言えば、ニュートン生誕一〇〇年となる二〇〇二年には、ゲロ・フォン・ベーム(Gero von Boehm)監督によるドキュメンタリー映画『ヘルムート・ニュートンと12人の女たち(Helmut Newton: The Bad and the Beautiful)』が公開されていました。ファッション写真に関心がある方だったらご覧になられているかもしれませんが、以下にトレイラーを掲載しておきました。ヘルムート・ニュートンの写真を知らないという方は、ひとまずトレイラーの中に映っている写真を、どうぞご覧ください。
ニュートンの挑発的な写真は、エロティックというよりかは、むしろその背後に感じられる不穏な物語性によって、いつ見ても心をざわつかさせられます。
以下は同映画の宣伝広告ですが、ヘルムート・ニュートンが撮影したこの写真に映っているのは、デヴィッド・リンチ(David Lynch)監督と女優のイザベラ・ロッセリーニ(Isabella Rossellini)です。以下の画像は、Inside Imagingの中の記事‘Was Helmut Newton a feminist or pervert?’から引用しました。

目を閉じたロッセリーニが非常に美しく写っています。ですが、彼女は生きている人間というよりも、同映画の中でロッセリーニ本人も述べていますが、あたかも「人形」のように見えます。そして、彼女のあごに触れている男性(デヴィッド・リンチ)の方は、あたかも「人形」を吟味している、あるいは好きなように扱おうとしているようにも見えます。
今日のいわゆる「ポリティカル・コレクトネス」という観点からニュートンの写真について語るとなると、否定的な見解が出くることは致し方のないことでしょう。ですが、同ドキュメンタリー映画の監督ゲロ・フォン・ベームは、次のようにも述べています。
「このドキュメンタリーが、限界へと進み、常にポリティカル・コレクトでいるのではなく、もう少しアナキスティックになる勇気を持つよう、若い写真家や芸術家たちを促すことができたら幸いだ」(Inside Imagingの中の記事‘Was Helmut Newton a feminist or pervert?’から)。
ゲロ・フォン・ベームのこうした意見に対しても、もちろん批判的な見解はありえるでしょう。また、同映画では、かつてニュートンの被写体となった女優やモデルたちの現在の声も聞けますが、それらに対しても偏った好意的な意見を集めているのではないかと思われなくもありません。実際、同映画の中でニュートンへの唯一の批判的な見解が見られるのは、アメリカの作家で社会運動家のスーザン・ソンタグ(Susan Sontag)が、ニュートンとともにフランスのテレビ番組に出演して、本人に向かって作品への批判の言葉を述べる場面ぐらいしかありません。そういったことから、RogerEbert.comの中で同映画のレヴューを書いた批評家のRoxana Hadadi氏は、「称賛的なもの以外の見解を入れる余地を作っていない」と述べ、5段階評価での2.5の星をつけています。
とはいえ、映画の前半の女優やモデルたちの数々インタヴュー、それらの中でも、とりわけイザベラ・ロッシーニとシャーロット・ランプリング(Charlotte Rampling)の発言には、耳を傾ける価値があることは間違いありません。ニュートンの作品に賛否両論いずれであっても、彼の作品をどう見るべきなかという点を改めて考えさせられる興味深い映画ですので、未見の方は、ぜひご覧になってみてください。
ついでの話ですが、同映画のオープニングとエンディングには、イギリスのグラム・ロック・バンド、スティーヴ・ハリー&コックニー・レベル(Steve Harley & Cockney Rebel)の1975年の曲「メイク・ミー・スマイル(カム・アップ・アンド・シー・ミー)(Make Me Smile (Come Up and See Me))」が使われていました。
「君はあらゆることやった。君はあらゆる作法を破った(You’ve done it all, you’ve broken every code)」という歌詞で始まり、「俺を笑わせてよ(Make me smile )」とサビで歌われる同曲は、確かに破天荒でありながら、おどけた姿を同映画の中で見せるヘルムート・ニュートンにぴったりな選曲です。
同曲をご存じない方は、以下のミュージック・ビデオをどうぞ。
さて、デュラン・デュランの「ザ・ショーファー」のミュージック・ビデオへと話を戻します。
その全体の映像の中でも、最も不可解で最も印象に残る場面と言えば、やはり終盤でトップレスの女性が踊っているシークエンスではないでしょうか。
Duran Duran wikiによると、ミュージック・ビデオのその場面は、リリアナ・カヴァーニ(Liliana Cavani)監督の1974年の映画『愛の嵐 (Il Portiere di notte)(英題:The Night Porter)』で、シャーロット・ランプリング(Charlotte Rampling)演じる強制収容所の生存者であるルチア(Lucia)が、「7つのベールの踊り」を踊る場面へのオマージュだそうです。
この「7つのベールの踊り」というのは、もともとオスカー・ワイルドの戯曲『サロメ』(1891年)に由来するそうですが、同映画ではルチアがナチス親衛隊の制服に身を包み、マレーネ・ディートリヒ(Marlene Dietrich)の曲「ウェン・イッヒ・ミーア・ヴァス・ヴンシュン・ドゥルフテ(Wenn ich mir was wünschen dürfte)」を歌いながら看守のために踊っています。以下のトレイラーでは、ちょうど22秒のあたりに、その場面が一瞬だけ映っています。
ナチスと性的な主題を組み合わせた、きわめて挑発的なこの映画の評価を巡っては、当然のことながら、これまでにも賛否両論さまざまな見解が生まれてきました。実際に『愛の嵐』をご覧になっていない方でも、このトレイラーを観ただけで、いろいろな意味でタブーを含んだ映画であることは、なんとなく想像がつくのではないかと思います。
The Guardianの中のRyan Gilbey氏の記事‘The Night Porter: Nazi porn or daring arthouse eroticism?’によると、公開当時、「この映画はヨーロッパでは概して敬意をもって扱われたが、アメリカの批評家からは猛烈に攻撃され、ニューヨーカー誌のポーリーン・カエルは「人間的にも美学的にも不快だ」と評した」そうです。
ここで念のために誤解のないように言っておくと、監督のリリアナ・カヴァー二は、ファシズムを賛美しているわけではまったくありません。そもそも祖父母が反ファシスト運動の一員でもあったカヴァー二は、1940年代のドイツ軍のイタリアへの侵攻に抵抗した女性たちを描いたTVドキュメンタリー『ラ・ドナ・ネッラ・レジステンザ(La donna nella Resistenza)』(1965年)も製作しています。
同ドキュメンタリーは、以下でご覧になれます。イタリア語ですが、この映像では英語の字幕もつけられています。
ついでに言うと、前述のThe Guardian記事によると、『愛の嵐』の撮影現場の雰囲気は、「このような陰気な映画にしては、意外にも陽気だった」そうです。監督のリリアナ・カヴァー二は次のようにも述べています。
「本当にいい雰囲気だったわ。明るくて、役者たちはみんな仲が良かったのよ。シャーロットに赤ちゃんが生まれたばかりで、子守りと一緒に撮影現場に連れてきていたわ」。
淫靡でタブーな男女の関係を描いた『愛の嵐』を、実際にご覧になったことがある方からすると、撮影現場が明るい雰囲気だったというのは、本当に意外ですよね。
もう一つ念のために言っておくと、デュラン・デュランの「ザ・ショーファー」(お抱え運転手を意味する)の歌詞自体は、ファシズムを匂わせる内容を含んでいません。
それはそうと、今回「ザ・ショーファー」のことをいろいろ調べていたら、フランスのラグジュアリーなファッション&ライフスタイル誌『ロフィシェル・オム(L’Officiel Hommes)』のための2013年のショート・フィルムで、まるっと曲が使われているのを発見しました。以下でどうぞご覧ください。
デュラン・デュランのオフィシャル・サイトのNewsページの中の‘New York La La La Featuring Duran Duran’s “The Chauffeur”‘によると、撮影したのは、アメリカの映画監督アーロン・ローズ(Aaron Rose)です。また、見事なスケートボードの走りを見せてくれる三人の男性は、有名なプロのスケートボーダーのジェリー・シュー(Jerry Hsu)とオースティン・ジレット(Austyn Gillette)とジョシュ・ハーモニー(Josh Harmony)で、ディオール・オム、サンローラン、プラダの服を着ているそうです。そして、レースのランジェリーを身に着けて颯爽と歩いている女性は、ベルギー出身のモデルのアヌーク・ルペール(Anouck Lepère)だそうです。
それにしても凡人の発想だと、オカリナの奏でるメロディーが印象的な「ザ・ショーファー」とストリートのスケートボードとハイブランドのファッションという組み合わせは、全くもって思いつかないような気がします。仮に自分がプロデューサーだったとしたら、「そもそも曲調や歌詞と映像が全く合わないだろう」と、そのアイデアを即却下してしまいそうです。
ですが、この作品を実際に観てみると、三人のスケートボーダーを含め、全編スローモーションの動きにしていることで、ゆったりとしたテンポの「ザ・ショーファー」と見事に同期しています。しかも、『ロフィシェル・オム』誌が訴えたいセルフ・イメージも「なるほどそういう感じを狙っているのね」と明瞭に伝わってきます。
唐突ではありますが、ここでデュラン・デュランを含め、80年代初頭のニュー・ロマンティックが好きだった方に尋ねます。「ザ・ショーファー」の最後のシークエンスで、『愛の嵐』へのオマージュとして踊っている女性が誰かをご存じでしょうか?
今回、この記事を書くまで、私自身は気にすることもなかったので知らなかったのですが、調べてみるとニュー・ロマンティック・ムーヴメントと深いかかわりのあるダンサーであり、シンガーであり、女優であるペリ・リスター(Peri Lister)でした。
以前、このブログの記事でも取り上げたイギリスのシンセ・ポップ・バンド、ヴィサージ(Visage)の1982年のアルバム『アンヴィル(Anvil)』にもペリ・リスターはバッキング・ボーカルを提供しています。また、ヴィサージのテレビ出演の際にも、しばしばダンスのパフォーマンスを披露しています。
また当時、交際中だったイギリスのシンガーのビリー・アイドル(Billy Idol)のミュージック・ビデオにも、ペリー・リスターは出演しています(「ホワイト・ウェディングPt 1(White Wedding Pt 1 )」(1983)、「トゥー・ビー・ア・ラヴァー(To Be a Lover)」(1986)、「ホット・イン・ザ・シティ(Hot in the City)」(1987))。
では、最後の締めくくりとして、その中からペリー・リスターの奔放なダンスを見ることができるビリー・アイドルの「ホワイト・ウェディング Pt 1」のミュージック・ビデオをご覧ください。
花嫁姿でモダン・ダンスを生き生きと踊っていた女性が、ペリー・リスターです。
このロック・ミュージックとモダン・ダンスという奇妙な組み合わせは、彼女がもともと所属していたダンス一座、ホット・ゴシップ(Hot Gossip)の頃からの定番です(ペリー・リスターの活動については、ニュー・ロマンティックを主題として書く機会があれば、そのときにでも改めて取り上げてみたいと思っています)。
それにしても、十字架やキャンドルなどといったゴシック・ロック寄りのセットの中で、上半身裸の姿となり口をひん曲げて歌うビリー・アイドルを撮影したこのミュージック・ビデオも、ヘルムート・ニュートンの写真や『愛の嵐』のエロティシズムを見てきた後だと、なんだかとても健全にすら感じてしまいませんか?
今回を含めて3回の記事で、イアン・イームズ監督のアニメーションからミュージック・ビデオに至るまでの諸作品を取り上げきましたが、次回は以前の記事で話が途中になってしまっていた映画『トロン』誕生前の監督スティーヴン・リズバーガーについて、少し書いてみたいと思っています。
この記事が気に入ったら下のボタンでシェア!
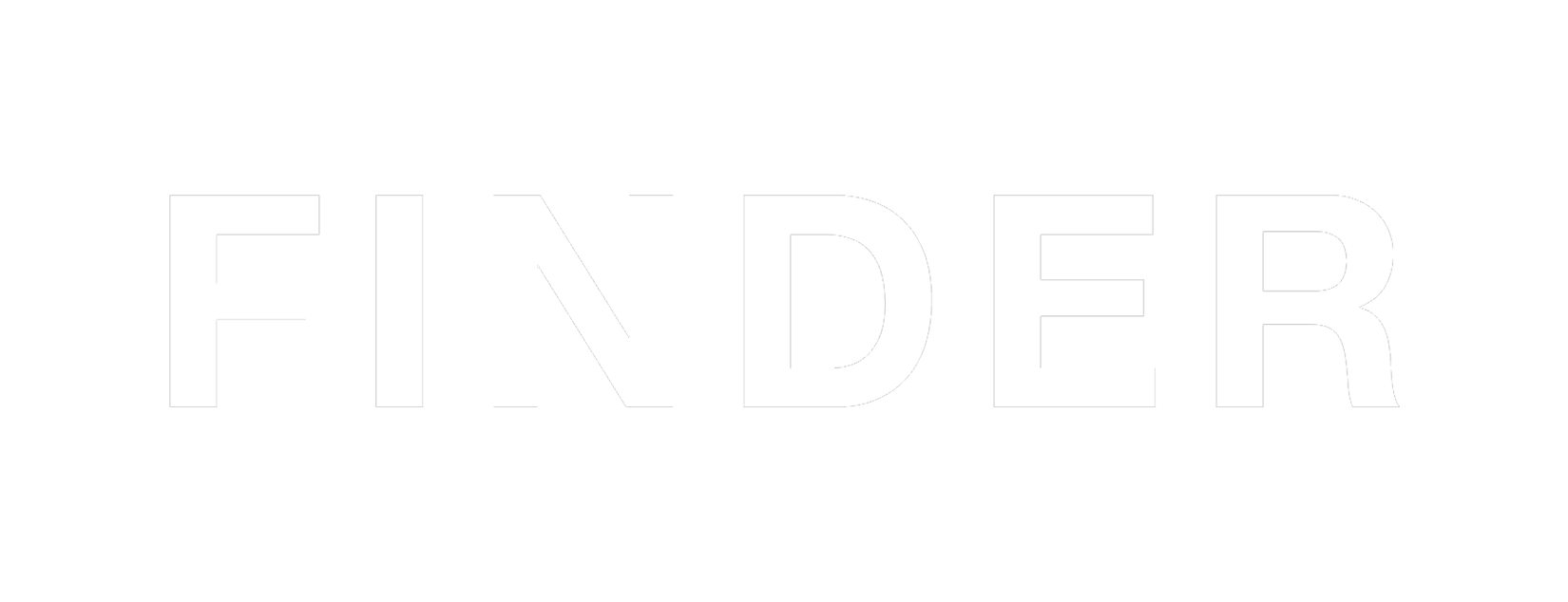 映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど
映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど


