最近の投稿
魔力の象徴としての「ヒョウ柄」:映画『媚薬』(1958年)の魔女ギルの衣装とインテリアから見る50年・・・映画『媚薬』(1958年)の中のビートニクな魔女とジャズが流れる占星術クラブ
「醜い老婆」から「若い女性」の姿へと変わっていく魔女(witch): 映画『オズの魔法使い』(193・・・
男性支配の物質主義的な世界の中で女性たちが求めること:映画『紳士は金髪がお好き』で「ヒョウ柄」の衣装・・・
記号としての「アニマル柄」:1934年の映画『特急20世紀』と1945年の『失われた週末』の中で「ヒ・・・
カテゴリ
フード&ドリンクビデオ・ゲーム
映画ポスター
ブック・カバー
ファッション
映画
インテリア
建築
音楽
ミュージック・ビデオ
コマーシャル映像
車・バイク
テレビ・シリーズ
アニメーション
アーカイブ
2024年1月2023年12月
2023年11月
2023年7月
2023年6月
2023年5月
2023年4月
2023年3月
2023年2月
2023年1月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
ブログについて
映画やTVドラマなどを観ていて、その中で流れてくる音楽、撮影に使われた建築やセットのデザイン、舞台の背景となるインテリア、登場人物が手にしているガジェットやプロダクトなどが気になったことはありませんか?
このブログでは、映画やTVドラマの中に登場するさまざまなものを調べて紹介していきます。そうしたものにも目を向けてみると、映画やTVドラマが今まで以上に楽しくなるはずです。映画、TVドラマ、音楽、建築、インテリアのどれかに興味がある方に、また自分と同じようにそのどれもが寝ても覚めても好きでたまらないという方に、面白いと思ってくれるような記事を発見してもらえたらという思いで書いています。
執筆者:伊泉龍一(いずみりゅういち)
ブログ以外には、以下のような書籍の翻訳をしたり、本を書いたりもしています。

ロバート・C・コトレル 著 伊泉 龍一 訳
『60sカウンターカルチャー ~セックス・ドラッグ・ロックンロール』

ドン・ラティン 著
『ハーバード・サイケデリック・クラブ ―ティモシー・リアリー、ラム・ダス、ヒューストン・スミス、アンドルー・ワイルは、いかにして50年代に終止符を打ち、新たな時代を先導したのか?』

デヴィッド・ヘップワース 著
『アンコモン・ピープル ―「ロック・スター」の誕生から終焉まで』

サラ・バートレット 著
『アイコニック・タロット イタリア・ルネサンスの寓意画から現代のタロット・アートの世界まで』
記号としての「アニマル柄」:1934年の映画『特急20世紀』と1945年の『失われた週末』の中で「ヒョウ柄」が語っていること

ここしばらくイギリスのテレビ・シリーズ『時空刑事1973 ライフ・オン・マーズ(Life on Mars)』の70年代を再現したリビング・ルームの各所をチェックしながら、当時のインテリアに関する話を書いています。
ところで、今回はいきなり質問から始めます。「アニマル柄」というモチーフから何が思い浮かびますか?
90年代半ばぐらいの日本ではアニマル柄のファッションと言えば、関西の少し年を重ねたお姉さま方が好まれる派手な服の柄という認識があったような気がします(関西と言っても、とりわけ大阪を連想することが多く、その中に神戸の女性が含まれることはあっても、京都の女性が含まれることはなかったように思います)。
ですが2000年代初頭ぐらいには、シンガーの浜崎あゆみさん、さらに当時の「ギャル」と呼ばれていた非常に若い女性たちがアニマル柄(おそらく主にヒョウ柄)の服をキュートに着こなしていたように記憶しています。
どちらにしても(関西のお姉さまであれ、ギャルであれ)、アニマル柄は、自己表現の重要なアイテムだったのではないでしょうか? とりわけ彼女たちが身に着けていたヒョウ柄は、おとなしく従順に生きることを拒み、自分の思いのまま自由かつ大胆に生きようとする活力に満ちた女性というイメージを連想させるものだったように思われます。
今回、こうしてアニマル柄の話を唐突に持ちだしたのは理由があります。後で詳しく述べますが、アニマル柄というのは実はここしばらく話題にしている70年代のインテリアのひとつの重要な要素なのです。
とはいえ、今日(2023年)の日本のインテリア・デザインの中でアニマル柄を積極的に取り入れられている例は、ないわけではないにせよ、実際の数としては非常に少ないような気がします。
特に2000年代に入ってから日本で広く見られるミニマリズムやナチュラル志向と相まった「北欧風インテリア」や「カフェ風インテリア」にこだわる方たちからすると、もしかするとアニマル柄は避けられるどころか、見向きもされないモチーフになってしまっているような気すらします。もしそうだとすると、いきなりアニマル柄を取り入れたインテリアの話をしても、多くの人に興味を持たれない可能性もなきにしもあらずです。
そこでこう思ったわけです。「何はともあれ、まずはアニマル柄への偏った見方を修正しておいた方が良いのではないか?」。そこで今回は、ほんの少しだけ過去の歴史に目を向けながら、アニマル柄の持つ象徴的な意味の変遷を思いつく限りで、少し振り返ってみたいと思います。
以下の写真をご覧ください。画像はNana Winters Interior Designの中の記事‘The Rise and Fall (and rise again) of Leopard’から引用しました。

ファッションの歴史に詳しい方なら、この写真をご覧になったことがあるのではないでしょうか? このレオパードのコートを上品に着こなしている女性は、かつてアメリカ第35代アメリカ合衆国大統領ジョン・F・ケネディの夫人となったジャクリーン(Jacqueline)です。
20世紀のファッションにおけるアニマル柄の歴史が言及される際に必ずといっていいほど指摘されているのが、このヒョウ柄のコートを着ているジャクリーンの姿です。どうやら、このファースト・レディの姿こそが、60年代のアメリカの女性たちにヒョウ柄へと改めて目を向けさせる一つのきっかけになったようです。もちろん、ここでのヒョウ柄から連想される象徴的意味には、富や権力だけでなく、洗練された女性の気品が含まれていたはずです。
このジャクリーンが着ているヒョウ柄のコートは、ロシア貴族の家系に生まれたフランス出身のファッション・デザイナーのオレグ・カッシーニ(Oleg Cassini)が1962年にデザインしました。カッシーニは大統領夫人だった時代のジャクリーンのために多くの服をデザインしたことで非常に有名になりました。
1940年代から1960年代頃の映画にもファッションにも造詣がある方なら、オレグ・カッシーニと言えば、当時のパラマウント・ピクチャーズの有名な女優たちの数々の衣装をデザインした人物として記憶されていることと思います。
また、アメリカの自動車に詳しい方だったら、インダストリアル・デザイナーのディック・ティーグ(Dick Teague)がデザインしたAMCのマタドール(Matador)の1974年に発売された特別高級モデルのクーペのインテリアのデザイナーとして、カッシーニの名前を思い出すかもしれません。
ちなみにですが、マタドールのデザイナーであるディック・ティーグは、1975 年にAMCのペイサー(Pacer)もデザインしています。ペイサーについては、以前にこのブログの記事で言及したことがあります。そこで書きましたが、映画『ウェインズ・ワールド(Wayne’s World)』の中でイギリスのロック・バンド、クイーンの1975年の曲「ボヘミアン・ラプソディ(Bohemian Rhapsody)」が歌われる名場面で使われています。詳しくは以下の記事をご覧ください。
「映画『ウェインズ・ワールド』のクイーンの「ボヘミアン・ラプソディ」とAMCのペイサーについて」
脱線を承知の上でついでの話をすると、まさに1974 年製のマタドールのクーペのカッシーニ・エディションは、ガイ・ハミルトン(Guy Hamilton)監督の1974年の「ジェームズ・ボンド」シリーズ第9作目の『007 黄金銃を持つ男(The Man with the Golden Gun)』に登場する悪役フランシスコ・スカラマンガの空飛ぶ車としても使われています。
映画をご覧になっていない方は、どうぞ以下で「空飛ぶ車」と化したマタドールの写真をご覧ください。画像は007の中の‘AMC MATADOR COUPÉ’から引用しました。

ご覧の通り、マタドールの上に大きな飛行機の翼が取り付けられています。子供の頃にこの時代の「007シリーズ」を見ていた方だったら、この車が飛んでいくシーンに興奮した人も多いのではないでしょうか? とはいえ、さすがに今冷静に見ると「これって本当に飛ぶの?」と思ってしまうような形状ですね。
『007 黄金銃を持つ男』をご覧になっていない方、ぜひ以下のトレイラーの2分8秒あたりをご覧ください。マタドールが空を飛ぶシーンが一瞬だけ映っています。
娯楽映画の諸要素がぎっしりと詰め込まれたわくわくするトレイラーですね。カー・アクションや美女という007シリーズのお決まりの要素だけでなく、ジェームズ・ボンドとアジア人との間での空手の格闘シーンまでありました。この映画の製作当時、ブルース・リー主演の「カンフー映画」がすでにヒットしていたので、それに乗じていることは明らかです。
さて、本題に話を戻しましょう。
ファッション史を少し紐解けば明らかなように、ヒョウ柄の毛皮の流行は、先ほどの写真のジャクリーンから始まったわけではありません。LA POLOの中の記事’LEOPARD PRINT A TREND FOR FOREVER AND EVER‘では、1920年代には「映画スターやフラッパーなど、エリート階級の女性たちは皆、本物のヒョウの毛皮」で着飾っていたと指摘されています。さらに1947 年にはクリスチャン・ディオールが、キャットウォークでヒョウ柄 (本物の毛皮ではなく) を最初に採用しています。
また、CULLED CULTUREの中のGenna Rivieccio氏の記事‘The Leopart Print in Film’(映画の中のヒョウ柄のプリント)を読むと、1930年代から1960年代の映画でさまざまな女優たちがヒョウ柄の衣装を身に着けていたことも指摘されています。
ここではRivieccio氏も例として挙げている1930年代と1940年代の映画をひとつずつ振り返りながら、それらの中でヒョウ柄がどのように使われ、どのような意味を暗示していたのかを少し考えてみたいと思います。
まずはハワード・ホークス(Howard Hawks)監督の1934年のスクリューボール・コメディ映画『特急20世紀(20th Century)』を見てみましょう。画像はDerek Winnertの中の記事‘Twentieth Century * (1934, John Barrymore, Carole Lombard, Walter Connolly, Roscoe Karns) – Classic Movie Review 1977′から引用しました。

これは、物語の中でランジェリー・モデルだったミルドレッド・プロトカがリリー・ガーランドという芸名で女優に転身した3年後、大成功して再び姿を見せる場面です。その役を生き生きと演じたのはキャロル・ロンバード(Carole Lombard)です。
映画の中で、成功する前のリリー・ガーランドが舞台の稽古でしごかれている場面を以下でご覧ください。
この映画の場面の中では、黒い地味な服装をしたリリーが舞台の稽古の途中で叱られて涙を流してていましたね。
一方、その3年後、対照的なヒョウ柄の衣装を身に着けた姿となって画面に現れた瞬間、映画を観ている側は、彼女が別人になったのだと一瞬で理解できます。このときの彼女は自信がなく気弱だった3年前と異なり、成功に酔いしれ、わがままで傲慢な性格になっています。
つまり、この場合のヒョウ柄は、女優としての名声と富の象徴として分かりやすく使われているわけです。しかも、ヒョウ柄という目を引き付けるモチーフが、キャロル・ロンバードの気ぜわしく振る舞うコミカルな演技を引き立てる役割を果たしています。
一方、1945年のビリー・ワイルダー(Billy Wilder)監督のアメリカ映画『失われた週末(The Lost Weekend)』の中で登場するヒョウ柄のコートは、単なる名声と富とは違った意味も暗示しているように思われます。
ご覧になっていない方のために、トレイラーを掲載しておきます。1分47秒当たりから数秒間、ジェーン・ワイマン(Jane Wyman)演じるヘレン・セント・ジェームズがヒョウ柄のコートを身に着けている場面が映ります。
では以下の静止画の方もご覧ください。画像はpinterestから引用しました。

ここではヒョウ柄のコートを身に着けたヘレン(ジェーン・ワイマン)が真剣な顔をしたレイ・ミランド(Ray Milland)演じるアルコール依存症の作家ドン・バーナムの顔を見つめながら腕に寄り添っています。
この場面のヘレンの姿から想像できるように、彼女は一途な性格の女性です。もしヒョウ柄を着た女性から自由奔放に生きる自己主張の強いイメージを連想するとしたら、ここでそれは当てはまりません。むしろ、ヘレンは裕福な家庭出身で教養があり、保守的な女性です。従って、ここでのヒョウ柄のコートが示しているのは彼女の性格というよりも、彼女が属している社会階層であることは確かです。
ただし、ヒョウ柄のコートの使用される場面と状況の方へと注目しながら『失われた週末』をご覧になっていただくと同意してくださるのではないかと思いますが、それはヘレンの社会的な身分を単に表しているというよりも、むしろ物語の重要な転換点を印象づけるために効果的な役割を果たしています。
その一つは、アルコール依存症のドン・バーナムと付き合うことになるきっかけとなったオペラ・ハウスでの最初の出会い場面です。そこではクロークで預かってもらっていたヘレンのヒョウ柄のコートが間違ってドンへと渡されます。また、もう一つは物語の終盤で、ドンがヘレンのヒョウ柄のコートを質屋へ持っていきピストルと交換したことが発覚する場面です。
こうしたシーンを思い返すと、物語の表層の意味を越えて、ヒョウ柄のコートが象徴的な記号として交換されているのではないかと深読みしたくなる誘惑にかられますが、本題から離れて完全に妄想的なことを書き連ねてしまいそうなのでやめておきます。
続けて1950年代の映画に目を向けてみましょうと行きたいところですが、長くなりそうなので次回にします。
今回は1960年代の多くの女性の意識をヒョウ柄へと向けさせることになったオレグ・カッシーニのデザインしたコートを着たジャクリーン・ケネディから時代を遡り、1930年代と1940年代の映画をひとつずつ取り上げて、そうした過去の時代のヒョウ柄が暗示する意味を考えてみました。
次回は、その後の時代におけるヒョウ柄の意味の変遷を追っていくために、1950年代の映画へと目を向けてみたいと思います。
この記事が気に入ったら下のボタンでシェア!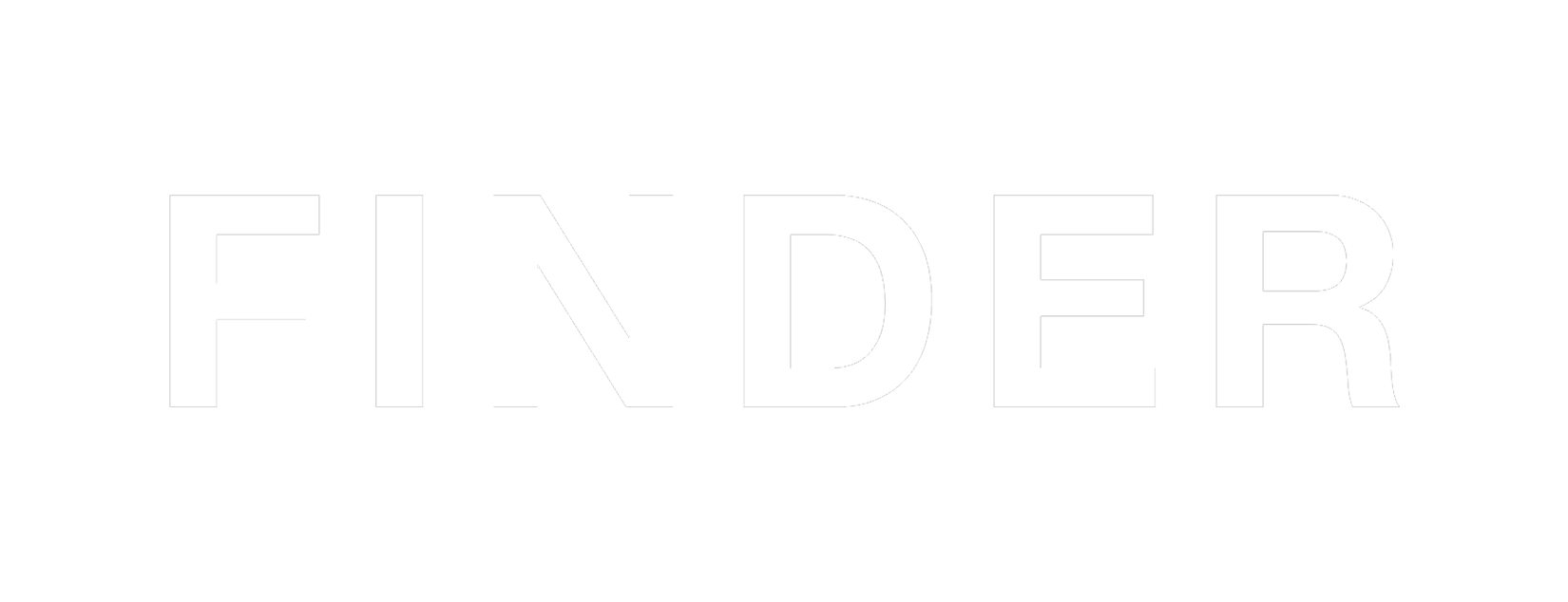 映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど
映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど


