最近の投稿
魔力の象徴としての「ヒョウ柄」:映画『媚薬』(1958年)の魔女ギルの衣装とインテリアから見る50年・・・映画『媚薬』(1958年)の中のビートニクな魔女とジャズが流れる占星術クラブ
「醜い老婆」から「若い女性」の姿へと変わっていく魔女(witch): 映画『オズの魔法使い』(193・・・
男性支配の物質主義的な世界の中で女性たちが求めること:映画『紳士は金髪がお好き』で「ヒョウ柄」の衣装・・・
記号としての「アニマル柄」:1934年の映画『特急20世紀』と1945年の『失われた週末』の中で「ヒ・・・
カテゴリ
フード&ドリンクビデオ・ゲーム
映画ポスター
ブック・カバー
ファッション
映画
インテリア
建築
音楽
ミュージック・ビデオ
コマーシャル映像
車・バイク
テレビ・シリーズ
アニメーション
アーカイブ
2024年1月2023年12月
2023年11月
2023年7月
2023年6月
2023年5月
2023年4月
2023年3月
2023年2月
2023年1月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
ブログについて
映画やTVドラマなどを観ていて、その中で流れてくる音楽、撮影に使われた建築やセットのデザイン、舞台の背景となるインテリア、登場人物が手にしているガジェットやプロダクトなどが気になったことはありませんか?
このブログでは、映画やTVドラマの中に登場するさまざまなものを調べて紹介していきます。そうしたものにも目を向けてみると、映画やTVドラマが今まで以上に楽しくなるはずです。映画、TVドラマ、音楽、建築、インテリアのどれかに興味がある方に、また自分と同じようにそのどれもが寝ても覚めても好きでたまらないという方に、面白いと思ってくれるような記事を発見してもらえたらという思いで書いています。
執筆者:伊泉龍一(いずみりゅういち)
ブログ以外には、以下のような書籍の翻訳をしたり、本を書いたりもしています。

ショーン・レヴィ著 伊泉龍一訳
『レディ・ステディ・ゴー! 60sスウィンギン・ロンドン』
伊泉龍一 (著)
『スピリチュアリズムの時代 1847-1903』
ポール・ガンビーノ (著), 伊泉 龍一 (監修, 翻訳)
『死を祀るコレクション:モダン・ゴシックという生き方、その住まい』
ドン・ラティン著 伊泉 龍一訳
『至福を追い求めて ―60年代のスピリチュアルな理想が 現代の私たちの生き方をいかに形作っているか』

ロバート・C・コトレル 著 伊泉 龍一 訳
『60sカウンターカルチャー ~セックス・ドラッグ・ロックンロール』

ドン・ラティン 著
『ハーバード・サイケデリック・クラブ ―ティモシー・リアリー、ラム・ダス、ヒューストン・スミス、アンドルー・ワイルは、いかにして50年代に終止符を打ち、新たな時代を先導したのか?』

デヴィッド・ヘップワース 著
『アンコモン・ピープル ―「ロック・スター」の誕生から終焉まで』

サラ・バートレット 著
『アイコニック・タロット イタリア・ルネサンスの寓意画から現代のタロット・アートの世界まで』
スージー・アンド・ザ・バンシーズの「キス・ゼム・フォー・ミー」とタブラ奏者タルヴィン・シンーー映画『よろめき休暇』とカクテルのスティンガーについて
フード&ドリンク 映画 音楽 ミュージック・ビデオ / 2023.05.14
数回前の記事で、イギリスのハード・ロック・バンド、レッド・ツェッペリン(Led Zeppelin)の1971年のアルバムの中の曲「ホウェン・ザ・レヴィー・ブレイクス(When the Revee Breaks)」のドラム・ビーツをサンプルしたイギリスのシューゲイザーのバンド、チャプターハウス(Chapterhouse)の1991年の曲「パール(Pearl)」の話をしました。
その記事の最後で述べたように、チャプターハウスの「パール」とイギリスのロック・バンド、スージー・アンド・バンシーズ(Siouxsie And The Banshees)の1991年の曲「キス・ゼム・フォー・ミー(Kiss Them For Me)」のリズム・トラックの中に非常に似ている部分があること気になったので、それについて調べてみたことを書いてみたいと思っています。
ですが、その前にまずはスージー・アンド・ザ・バンシーズの「キス・ゼム・フォー・ミー」をご存じない方のために、曲自体を紹介しておかなければなりませんね。ということで、まずは「キス・ゼム・フォー・ミー」のミュージック・ビデオをご覧ください。
前々回の記事で、ソフィア・コッポラ監督の映画『マリー・アントワネット(Marie-Antoinette)』で使われたスージー・アンド・ザ・バンシーズの1978年のデヴュー・シングル「ホンコン・ガーデン(Hong Kong Garden)」を紹介しましたが、その頃のポスト・パンク期のサウンドとは、ずいぶんと雰囲気が違いますね。
この「キス・ゼム・フォー・ミー」は、何といっても「ホンコン・ガーデン」をリリースしてから13年後の1991年のアルバム『スーパースティション(Superstition)』からのシングル曲です。「ホンコン・ガーデン」の飛び跳ねたくなるリズムとは対照的に、「キス・ゼム・フォー・ミー」はゆったりとしたグラマラスなダンス志向の曲になっていますね。そして、全体を覆うインド的な味付けにシンガーのスージー・スー(Siouxsie Sioux)の濃密かつ麗しい歌声が重なり合い、幻想のオリエントへと誘われてしまいます。
ここで個人的に少し触れておきたいと思うのは、この曲の魅力を明らかに倍増させているオリエンタルな雰囲気は、レコーディングに参加しているイギリス出身のタブラ奏者のタルヴィン・シン(Talvin Singh)のおかげだということです。
タルヴィン・シンをご存じのない方のために言うと、90年代後半のエレクトロニカのシーンの中で、西洋のダンス・ミュージックと主に南アジアの伝統的な音楽を結び付けた「アジアン・アンダーグラウンド(Asian Underground)」とも呼ばれたジャンルの中心にいた人です。
また、これまでタルヴィン・シンの名前を聞いたことがなかったという人でも、1990年代後半から2000年代初頭のイギリスやアメリカのポピュラー・ミュージックをよく聴いていた方だったら、どこかで彼の演奏するタブラの音を耳にしている可能性もあります。というのも、このスージー・アンド・ザ・バンシーズの「キス・ゼム・フォー・ミー」に参加したことがきっかけで、その後、タルヴィン・シンは他のポピュラー・ミュージックのアーティストの作品にも呼ばれるようになりました。
例えば、以前にこのブログで言及したアーティストで言えば、アイスランド出身のシンガー、ビョーク(Björk)の1993年のアルバム『ディビュー(Debut)』にもタルヴィン・シンは参加しています。
もう一つ例を挙げると、イギリスのロック・バンド、デュラン・デュランの1997年の9 枚目のアルバム 『メダザランド(Medazzaland)』 からのシングル「アウト・オブ・マイ・マインド(Out Of My Mind)」でもタルヴィン・シンの演奏が聞こえてきます。
ここでは、デュラン・デュランの「アウト・オブ・マイ・マインド」のミュージック・ビデオをご覧ください。
デュラン・デュランのファンだったら、アルバムの中に必ず一曲は入っていて欲しいお決まりのメランコリックな曲なのではないでしょうか(ていうか、彼らのアルバムの中には必ずといっていいほど一曲入ってますよね、このタイプの曲)。
それにしても、この種のスローなデュラン・デュランの曲は、どれも胸の奥から情感を引きずり出すような物悲しいメロディーとシンガーのサイモン・ル・ボン(Simon Le Bon)の独特のくせになる粘っこい歌声が相まって、いやおうなしに心をつかまれますね。
ついでに言うと、このミュージック・ビデオを監督したのは、アメリカの写真家でもあるディーン・カー(Dean Karr)です。このブログの過去の記事「『ツイン・ピークス』の後のジュリー・クルーズ(3)――ユーリズミックスの「スウィート・ドリームス」のカヴァー曲」を読んで記憶しくださっている方なんてまずいないと思いますが、その際に、マリリン・マンソン(Marilyn Manson)の1995年のカヴァー曲「スウィート・ドリームス(Sweet Dreams)」のミュージック・ビデオとラブ・アンド・ロケッツ(Love & Rokets)の1996年の曲「スウィート・ラヴァー・ハングオーヴァー(Sweet Lover Hangover)」のミュージック・ビデオを監督していることで、ディーン・カーについては言及したました。
このデュラン・デュランのミュージック・ビデオも、私が思うところのディーン・カーらしい映像、つまり一瞬一瞬の絵画的な質感を持った美しい写真を連続して動画にしたような映像になっています。光の入れ方とそれによって生まれる陰影に注目していると、いわゆる古典的な名画を観ているときの感覚と近いものを感じませんか?
ところで、このブログのそもそものタイトルになっている「映画の中の音楽」に引き付けて言うと、このデュラン・デュランの「アウト・オブ・マイ・マインド」は、フィリップ・ノイス(Phillip Noyce)監督の1997 年の映画『セイント(The Saint )』のエンディングで、ヴァル・キルマー(Val Kilmer)演じるプロフェッショナルな泥棒サイモン・テンプラーが、ロシアでのあれやこれやを見事に解決して帰国した後、クールな表情で赤いボルボに乗って走り去っていく場面で使われています。よろしければ、以下でその場面をどうぞ。
映画『セイント』をご覧になった方だったら覚えてらっしゃるかもしれませんが、このエンディングは、エリザベス・シュー(Elisabeth Shue)演じるエマ・ラッセルが壇上でスピーチをしているオックスフォード大学から、ヴァル・キルマー演じるサイモン・テンプラーが車に乗って走り去っていく場面から始まります。そして続けて、くすんだ色合いの街の風景が映り、カメラが少しずつ上空に離れていきながら撮影したような映像になっていきます。そこに「アウト・オブ・マイ・マインド」が流れているわけです。
その物悲しいメロディーで歌われる「君がいなければ、どんな信じるべきことが残っているというのか?(Without you, what’s left to believe in?)」という歌詞が、映像に重ね合うされることで、過去の悲しみから現在に至ったサイモン・テンプラーの心情が語らずとも伝わってくるようにも感じられます。そればかりか、彼のこの先の人生の続きを知りたくなる気持ちにすらさせられます。映画の結末を単なるめでたしめでたしの清々しさで締めくくらない最後の最後のここが、全編の中で最も暗示に富んでいて深みを感じさせてくれるシーンのようにも思えます。
実際にご覧になった方は、本編の話の展開などに関して面白かった、面白くなかったなどのさまざまな意見があるとは思いますが、どちらにしても改めてこのエンディングを観てどうでしょう。「アウト・オブ・マイ・マインド」が流れる中、上空に遠ざかっていきながら映し出される街の光景。心地よい余韻を残してくれるいい終わり方だと思いませんか?
さて、本題のスージー・アンド・ザ・バンシーズの「キス・ゼム・フォー・ミー」に話を戻しましょう。
実は、この「キス・ゼム・フォー・ミー」も映画と関係があります。とはいっても、サウンドトラックで使われたわけではありません。映画と関係があるのは、この曲の題名で、60年代から70年代初頭のアメリカでのセックス・シンボルとも言われていたジェーン・マンスフィールド(Jayne Mansfield)が出演したスタンリー・ドーネン(Stanley Donen)監督の一九五七年のコメディ映画『キス・ゼム・フォー・ミー(Kiss Them For Me)』(邦題:よろめき休暇)に由来しています。
同映画の中で、アリス役を演じるジェーン・マンスフィールドが「ユー・キス・ゼム・フォー・ミー(代わりに君がその人たちへキスして)」という台詞を口にします。実際の場面は以下でご覧いただけます(最後の方の2分29秒あたりのところです)。
ここで誤解のないように言っておくと、スージー・アンド・ザ・バンシーズの「キス・ゼム・フォー・ミー」には、同映画の題名がそのまま使われているとはいえ、映画のストーリーとその歌詞の内容はまったく関係ありません。
「キス・ゼム・フォー・ミー」の歌詞は、実際のところ、マリリン・モンローの模倣などとも言われ、ときとして低い評価を与えられてしまいがちだったジェーン・マンスフィールドに対して、シンガーのスージー・スーがトリビュートの思いを込めて書いたものです。
例えば、歌詞の中の「ハート型の名声のスイミングプール(in the heart shaped pool of fame)」や「ピンクのシャンペイン(pink champagne)」や「彼女が出席しないパーティーはない(No party she’d not attend)」などは、マンスフィールドのお気に入りだったものを、そのまま表しています。また、「ニューオーリンズへ向かう路上(On the road to New Orleans)/星々のしぶきがスクリーンを打つ(a spray of stars hit the screen)」という歌詞の部分は、1967年6月29日のニューオリンズへ向かう途上での交通事故によるマンスフィールドの実際の悲劇的な死を示唆しています。
ところで、本題とはまったく関係ないですが、この映画『キス・ゼム・フォー・ミー(よろめき休暇)』をご覧になったことがある方の中で、ケーリー・グラント(Cary Grant)演じるアンディ・クルーソンが、カクテルのスティンガー(Stinger)を好んで飲んでいたことを覚えていらっしゃいますか? しかもしつこいぐらい何度もスティンガーを飲み続けます。
昔この映画を観たとき、内容自体はまるで心に響きませんでした(あくまで個人の感想です。この映画を好きな方にはごめんなさい)が、スティンガーを飲みまくっているシーンだけはしっかりと記憶に残ってしまいました。
それにしても、なぜこの映画でひたらすスティンガーを飲むのでしょう? まあ、本当にどうでもいい疑問かもしれませんが、気になり始めると調べずにはいられない性分なので、ちょっと調べてみました。以下は、よっぽどのカクテル好きでもなければ、どうでもいい話と思われそうなことを承知の上で、あえて書きます。
まずはスティンガーというカクテルの歴史を遡って探ってみました。
カクテルの歴史家の間でもスティンガーの正確な起源は不明なようですが、 少なくとも1910 年代にはすでに人気の飲み物だったようです。DRINKSKOOLの中の‘Chapter Ten: The Purr of Liqueur, aka The Stinger’によると、その初期のレシピは、サンフランシスコのバーテンダー、アーネスト・ローリング著書(Ernest Rawling)『ローリングのミックス・ドリンクの本(Rawling’s Book of Mixed Drinks)』 (1914 年) 、シカゴのソムリエ、ジャック・ストローブ(Jacques Straub)の著書『ドリンク(Drinks)』(1914年)、 ニューヨークのバーテンダー、ヒューゴ・エンスリン(Hugo Ensslin)の著書『ミックス・ドリンクのレシピ(Recipes for Mixed Drinks)』(1916年)などに登場しているとのことです。
同記事によると、スティンガーはこれら 3 冊の本のいずれにおいても「カクテル」のセクションではなく、「その他の飲み物」に特化したセクションに掲載されています。 これは、それが正式なカクテルではなく、「食後の飲み物」や「液体デザート」と考えられていたからです。
では、当時のレシピはどんな感じだったのだろう、と気になったので、前述の本の中の一冊、アーネスト・ローリング著『ローリングのミックス・ドリンクの本』 (1914 年)を、実際に見てみました(こちらで閲覧できます。‘1914 Rawling’s of Book Mixed Drinks by E P Rawling’)。すると、同書でのスティンガーのレシピは以下の通りでした。
氷を入れた小さなミキシンググラスの中に
ハーフポニー・グラスのコニャック
ハーフポニー・グラスのクレーム・ド・メンテ
よくシェイクしてベルモット・グラスに注ぐ
非常にシンプルなレシピですね。要は、コニャックとクレーム・ド・メンテ(Crème de menthe)を同量入れれば良いわけですから。
ここでカクテル好きの方ならお分かりの通り、クレーム・ド・メンテは甘いミント系の味です。なので、コニャックと同量だと当然ながら、かなりの甘口になりますね。なるほど、やはりデザートのような扱いになるわけですよ。ちなみに、最近のレシピだと、おおよそコニャック3に対してクリーム・ド・メンテ1、ないしは2に対して1ぐらいの割合が多い感じでしょうか。
それはそうと、以下で非常に美しく、かつ最高においしそうなスティンガーの写真をどうぞ。こちらはPunchの中の記事‘Stinger’に掲載されているDANIEL KRIGER氏の写真を引用させていただきました。

ちなみに、こちらのレシピでは、クレーム・ド・メンテの量は控えめでした。2 1/4オンスのコニャックと3/4オンスのクレーム・ド・メンテ、それに1ダッシュのオレンジ・ビターズとなっています。そして、飾ってあるのはミントの葉です。
さらにスティンガーについての歴史を、LIQUOR.COMの中の記事‘Stinger’で読んでみると、アメリカの大富豪「ヴァンダービルド家」の一族の中のレジナルド・ヴァンダービルト(Reginald Vanderbilt, 1880-1925)が、このカクテルを発明した可能性もあるようです。同記事によると、1923年のオハイオ州の新聞記事で、彼がその発明者であり、20年前から自宅の来客に好んで提供していたとが記されているそうです(また、同記事によると、このことについて詳しくは、David Wondrich氏の著書 Imbibe! Updated and Revised Edition: From Absinthe Cocktail to Whiskey Smash, a Salute in Stories and Drinks to “Professor” Jerry Thomas, Pioneer of the American Bar(2015)に書かれているとのことです。この本の内容をチラ見したところ、かなり面白そうな内容だったので読んでみたくなりました)。
さて、大富豪のレジナルド・ヴァンダービルトが嗜好していたということはです。そう、当然ながら、スティンガーは上流社会を連想させるカクテルとなったわけですよ。
実際、同記事によると、チャールズ・ウォルターズ(Charles Walters)監督の1956年のミュージカル・コメディ映画『上流社会(High Society)』にもスティンガーが登場するそうです(あのジャズのトランぺッターのルイ・アームストロング(Louis Armstrong)も本人役で出演している映画です)。
随分昔に観た映画なので、スティンガーを飲んでいたシーンを憶えていませんが、確かにタイトル通り、「上流階級」の人々のさまざまな生活の場面が登場する映画です。
一方、映画『キス・ゼム・フォー・ミー』(よろめき休暇)ですが、スティンガーを最初に飲むシーンが出てくるのは、ケーリー・グラント演じるアンディ・クルーソン少佐を含めた勲章を授与された海軍パイロット3名が、4日間の休暇を過ごすために滞在したザ・フェアモント・サンフランシスコ・ホテルの豪華なスイートでのことです。
ということはです。この映画ではスティンガーを飲むという行為は、上流階級ないしは少なくとも贅沢をすることと結びつけられていたということなのでしょう。先ほどの「なぜこの映画でひたらすスティンガーを飲むのか?」という疑問も、これで自分的にはなんとなく腑に落ちました。
脱線が長くなってしまいました。本来は、チャプターハウスの「パール」とスージー・アンド・ザ・バンシーズの「キス・ゼム・フォー・ミー」のリズム・トラックが似ているのはなぜなのかということを書くはずでした。ですが、「キス・ゼム・フォー・ミー」を簡単に紹介しておこうと思って書き始めたら、思いのほか長い話になってしまいました。ということで、そもそもの本題については次回に譲ります(次回は脱線せずに冒頭から本題に入ります)。
今回の記事の最後として、最初の方で言及したタブラ奏者のタルヴィン・シンについてちょっとだけ。
いきなりですが、インド料理は好きですか? 私は大好きなので、家でインド料理をたまに作るのですが、そのときに背景にかける音楽として、結構な頻度で選んでしまうのがタルヴィン・シンの作品なのです。音楽好きかつ料理好きという方なら共感してもらえると思いますが、好きな音楽を聴きながらだと料理をしている時間がよりいっそう楽しくなりますよね?
ここでインド風の音楽が好きな方のために、タルヴィン・シンの楽曲を一曲だけ紹介しておきます。
どれにするかと迷うところですが、ここではビートルズのジョージ・ハリスンにも影響を与えたことでもよく知られているインドのシタール奏者ラヴィ・シャンカル(Ravi Shankar)の弟子にあたるニラードリ・クマール(Niladri Kumar)とのコラボレーションの2011年のアルバム『トゥゲザー(Together)』の中から「リバー(River)」という曲を選んでみました。ぜひとも、以下でお聴きください。
純粋なインド音楽ではなく、エレクトロニカがうまい具合にミックスされています。それにしても、南アジアの方の音楽はエレクトロニカと、すっと馴染みやすくていいですね。しかも互いの間から生まれてくるにシナジーすら感じられます。
ですが、同じアジアでも日本も含む東アジアの方の音楽だと、これほどストレートな形での組み合わせによって互いの良い所を殺さずに同水準のシナジーを出すのはなかなか難しいような気もします。
今回はひとまずこの辺で終わりにしますが、先ほども述べたように本題の続きは次回で。
この記事が気に入ったら下のボタンでシェア!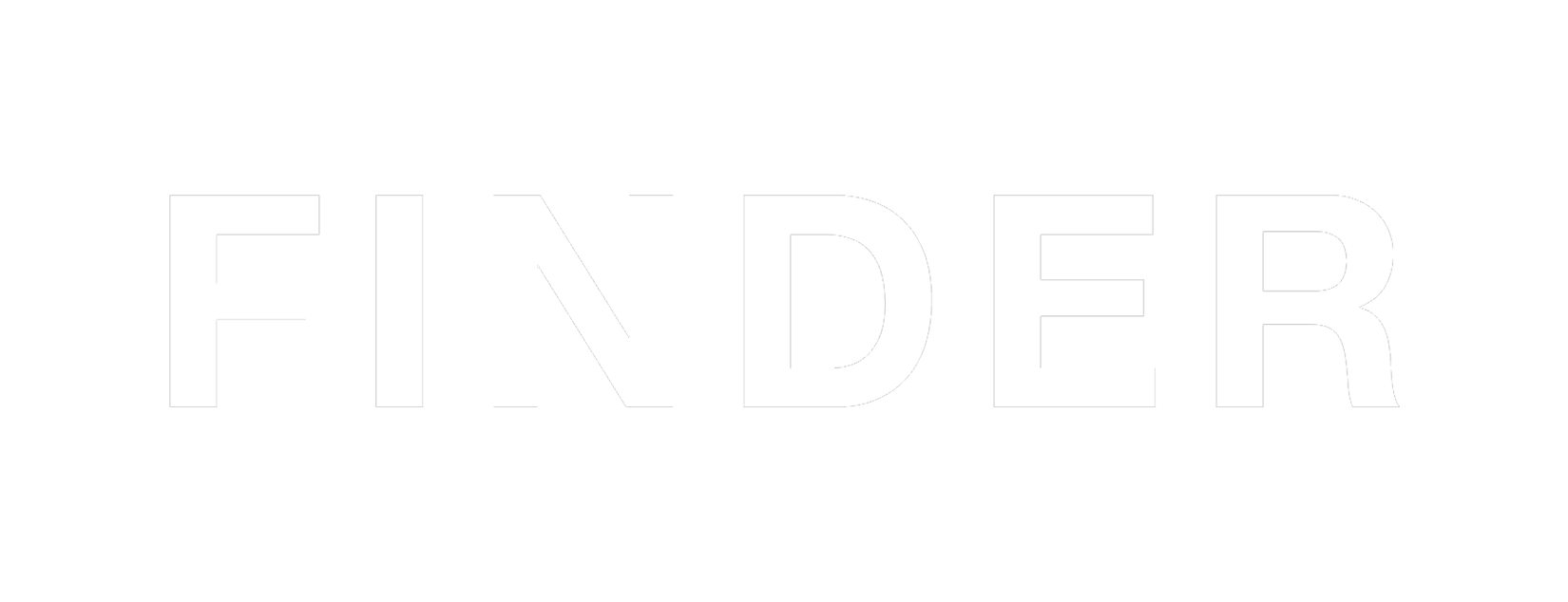 映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど
映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど





