最近の投稿
魔力の象徴としての「ヒョウ柄」:映画『媚薬』(1958年)の魔女ギルの衣装とインテリアから見る50年・・・映画『媚薬』(1958年)の中のビートニクな魔女とジャズが流れる占星術クラブ
「醜い老婆」から「若い女性」の姿へと変わっていく魔女(witch): 映画『オズの魔法使い』(193・・・
男性支配の物質主義的な世界の中で女性たちが求めること:映画『紳士は金髪がお好き』で「ヒョウ柄」の衣装・・・
記号としての「アニマル柄」:1934年の映画『特急20世紀』と1945年の『失われた週末』の中で「ヒ・・・
カテゴリ
フード&ドリンクビデオ・ゲーム
映画ポスター
ブック・カバー
ファッション
映画
インテリア
建築
音楽
ミュージック・ビデオ
コマーシャル映像
車・バイク
テレビ・シリーズ
アニメーション
アーカイブ
2024年1月2023年12月
2023年11月
2023年7月
2023年6月
2023年5月
2023年4月
2023年3月
2023年2月
2023年1月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
ブログについて
映画やTVドラマなどを観ていて、その中で流れてくる音楽、撮影に使われた建築やセットのデザイン、舞台の背景となるインテリア、登場人物が手にしているガジェットやプロダクトなどが気になったことはありませんか?
このブログでは、映画やTVドラマの中に登場するさまざまなものを調べて紹介していきます。そうしたものにも目を向けてみると、映画やTVドラマが今まで以上に楽しくなるはずです。映画、TVドラマ、音楽、建築、インテリアのどれかに興味がある方に、また自分と同じようにそのどれもが寝ても覚めても好きでたまらないという方に、面白いと思ってくれるような記事を発見してもらえたらという思いで書いています。
執筆者:伊泉龍一(いずみりゅういち)
ブログ以外には、以下のような書籍の翻訳をしたり、本を書いたりもしています。

ショーン・レヴィ著 伊泉龍一訳
『レディ・ステディ・ゴー! 60sスウィンギン・ロンドン』
伊泉龍一 (著)
『スピリチュアリズムの時代 1847-1903』
ポール・ガンビーノ (著), 伊泉 龍一 (監修, 翻訳)
『死を祀るコレクション:モダン・ゴシックという生き方、その住まい』
ドン・ラティン著 伊泉 龍一訳
『至福を追い求めて ―60年代のスピリチュアルな理想が 現代の私たちの生き方をいかに形作っているか』

ロバート・C・コトレル 著 伊泉 龍一 訳
『60sカウンターカルチャー ~セックス・ドラッグ・ロックンロール』

ドン・ラティン 著
『ハーバード・サイケデリック・クラブ ―ティモシー・リアリー、ラム・ダス、ヒューストン・スミス、アンドルー・ワイルは、いかにして50年代に終止符を打ち、新たな時代を先導したのか?』

デヴィッド・ヘップワース 著
『アンコモン・ピープル ―「ロック・スター」の誕生から終焉まで』

サラ・バートレット 著
『アイコニック・タロット イタリア・ルネサンスの寓意画から現代のタロット・アートの世界まで』
映画『マリー・アントワネット』のポスト・パンクとニュー・ロマンティックの感性(2)――ギャング・オブ・フォーとニュー・オーダーとザ・キュア
映画 音楽 ミュージック・ビデオ / 2023.04.28
前回から、70年代末のイギリスのポスト・パンク期にデビューしたバンド、スージー・アンド・ザ・バンシーズを、普通に映画好きの方のために紹介するという目的から、映画『マリー・アントワネット(Marie-Antoinette)』の話を書き始めました。
そもそも映画『マリー・アントワネット』自体をご覧になっていなという方のために、ここでひとまずトレイラーをご覧ください。
前回にも似たようなことを言いましたが、普通の「時代劇」を期待して観てしまうと、その期待を完全に裏切られます。というか、このトレイラーを観ただけでも、普通の時代劇ではないことは想像がつくことと思います。何といっても流れてくる音楽が、まるで劇中の時代と違和感がありまくりのサウンドです。
これまた前回も同じことを書きましたが、Vogueの記事の中で監督のソフィア・コッポラ自身が述べているように、映画『マリー・アントワネット』の製作の前提にあったのは、ティーンエイジャーだったマリー・アントワネットの感性を表現するために、80年代初頭にイギリスで台頭した「ニュー・ロマンティック(New Romantic)」というポピュラー・ミュージックの「レンズ」から18世紀末フランスの宮廷にアプローチすることでした。
ということで、トレイラーの27秒あたりでギターのリフから始まるぎくしゃくとしたファンクなリズムの曲は、まさしくコッポラのその意図の表現なのです。で、この曲と言うと、イギリスのポスト・パンクのバンド、ギャング・オブ・フォー(Gang of Four)の1979年のデビュー・アルバム『エンターテインメント!(Entertainment!)』の中の2曲目「ナチュラルズ・ノット・イン・イット(Natural’s Not in It)」です。
この「ナチュラルズ・ノット・イン・イット」という曲は、映画『マリー・アントワネット』の中でも、とりわけ重要な役割を果たしているといってもいいでしょう。実際に映画をご覧になった方は、その冒頭のシーンを覚えていらっしゃいますか?
そう、いきなり出だしから、こちら側を切りつけてくるかのような「ナチュラルズ・ノット・イン・イット」の耳障りなギターのリフが聞こえてくるのです。そして、最初に画面に現われるのは、キルスティン・ダンスト(Kirsten Dunst)演じるマリー・アントワネットが体を横たえ、その足下にはメイドがいるという短いショットです。以下で、その冒頭の場面をご覧ください。
この映画の冒頭のシーンについて、ソフィア・コッポラはVOGUEのKEATON BELL氏の記事‘‘It Was Like Hosting the Ultimate Party’: An Oral History of Sofia Coppola’s Marie Antoinette’の中で次のように述べています。
「冒頭のイメージは、横たわっている女性と足下にいるメイドというギイ・ブルダン(Guy Bourdin)の写真を基にしています。その意図は、人が彼女に対して抱いているデカダンな感じを通して、女王を紹介するためでした」。
ファッション写真が好きな方はご存じかと思いますが、ギイ・ブルダンと言えば、以前にこのブログでも言及した写真家ヘルムート・ニュートンと同時代の写真家ですね。フランスの『ヴォーグ』誌などのファッション誌のために、挑発的で官能的な数々の作品を残しています。
先ほどの冒頭の場面では、ギャング・オブ・フォーの「ナチュラルズ・ノット・イン・イット」から始まり、ギイ・ブルダンの写真に着想を得たショットで、マリー・アントワネットがケーキの砂糖衣を指ですくって舐め、画面に顔を向けた瞬間、この映画の全体的な意図がきわめて明瞭になります。
このことについて、コッポラは前述の記事で次のようにも述べています。
「ギャング・オブ・フォーの曲 [「ナチュラルズ・ノット・イン・イット」] は、そのパンクのエネルギーを体現し、この物語のトーンを確立するように意図されました。 それは、こんな精神を持っているのです。私たちは城を乗っ取った子供たちだ。だから、自分たちはやりたいことを何でもすることができる」。
ギャング・オブ・フォーのシンガーのジョン・キング(Jon King)自身も、映画『マリー・アントワネット』での自分たちの「ナチュラルズ・ノット・イン・イット」の使われ方を気に入ったようです。同記事の中で、ジョン・キングは次のようにも述べています。
「気に入ったよ。アンディ[ギル] のドライなギターのリフで始まるオープニングをね――それはまったく予想外だった。……富に満ち溢れてはいたが、生まれながらに取引される商品だった十代の少女が、世界で最も権力のある男性の一人と結婚するために、彼女が知っている全てのものから引きずり出される。それは自分の歌詞――「余暇の問題/楽しみのために何をすべきか/理想の愛、新たな購入品/官能のマーケット……」――にぴったりの素晴らしい映像だった」。
確かに、このイントロの場面のすぐ後で、マリー・アントワネットは、会ったこともないフランス王太子との結婚のために、祖国オーストリアの一切のものを剥ぎ取られた上でフランスのヴェルサイユ宮殿へと移動させられます。そう、ジョン・キングが言うように、ある意味「取引される商品」であるかのようにです。そして、その後は「余暇の問題/楽しみのために何をすべきか」の人生を送らなければならなくなるわけです。
ところで、先ほどのトレイラーでは、1分30秒あたりから別の曲が流れてきますが、こちらはイギリスのロック・バンド、ニュー・オーダー(New Order)の「セレモニー(Ceremony)」です。実際の映画では、マリー・アントワネットの18歳の誕生日の「セレモニー」が行われている夜のパーティーの場面から日の出を見る早朝までの間のシーンで流れてきます。以下でその場面をご覧ください。
楽しく陽気に誕生日を祝っているはずなのにもかかわらず、うっすらと漂う物悲し気なマリーの気分を、ニューオーダーの「セレモニー」がこの上なく見事に演出してくれます。
映画『マリー・アントワネット』の話からは外れてしまいますが、この「セレモニー」という曲は、ニュー・オーダーの経歴の中で最も重要な位置を占めている曲です。
「セレモニー」は、ニュー・オーダーのデビュー・シングルとして1981年にリリースされました。ですが、曲自体は、ニュー・オーダーの前身となったバンド、ジョイ・ディヴィジョン(Joy Division)で活動していた頃、しかもその最も末期に作られました。また、歌詞の方は、ジョイ・ディヴィジョンのシンガー、イアン・カーティス(Ian Curtis)によって書かれました。
ですが残念なことにも、イアン・カーティスは、1980年5月18日に死去します。その後、ジョイ・ディヴィジョンの残された三人のメンバーが、バンド名をニュー・オーダーに変えて音楽活動を継続し、その最初のシングルとして「セレモニー」を録音してリリースすることになりました。つまり、「セレモニー」はジョイ・ディヴィジョンとニュー・オーダー、また故イアン・カーティスと残された三人のメンバーの間をつなぐ重要な曲なのです。
ジョイ・ディヴィジョンがどれほどポスト・パンクのバンドとして重要であったか、そしてその後の音楽シーンに与えた影響については、ここで私ごときがヘタなことを書くよりも、もっと事情に通じた方の話を読んでいただいた方がよいに決まっています。
ということで、現時点(2023年4月28日)のウェブ上の記事で、私が気づいた範囲で紹介すると、例えばthred.の中のチャーリー・クームズ氏の記事「ジョイディヴィジョンが音楽をどのように変えたか」、またFEMの中のc__keny(ケニー)氏の記事「【衝撃】joydivision(ジョイディヴィジョン)の魅力や名前の意味とは?名盤おすすめレコード3選」をお読みくだされば、ジョイ・ディヴィジョンがどれほど後世のバンドに大きな影響を与えたかがご理解いただけるはずです。
さらに、ジョイ・ディヴィジョンやイアン・カーティスに関してのしっかりとした翻訳本もいくつか出ています。現時点(2023年4月28日)で私が知っているものだけを挙げておきます(他にも良書があって、下記から漏れていたらすいません)。各書の内容をひとつひとつ解説していくと長くなってしまうので、リンク先のページの方でどうぞご確認ください。
ジョン・サヴェージ著、坂本麻里子訳、『この灼けるほどの光、この太陽、そしてそれ以外の何もかも──ジョイ・ディヴィジョン ジ・オーラル・ヒストリー』(Pヴァイン、2019年)
バーナード・サムナー著、萩原麻理訳、『ニュー・オーダーとジョイ・ディヴィジョン、 そしてぼく』(Pヴァイン、2015年)
デボラ・カーティス著、小野良造訳、『タッチング・フロム・ア・ディスタンス―イアン・カーティスとジョイ・ディヴィジョン』(蒼氷社、2006年)
それから『レコード・コレクターズ』誌の2019年 6月号で「ジョイ・ディヴィジョン ニュー・オーダー」が特集されています。
さらに映画好きの方のために言えば、ジョイ・ディヴィジョンのドキュメンタリー映画もあります。グラント・ジー (Grant Gee) 監督の2007年の『ジョイ・ディヴィジョン(Joy Division)』です。よろしければ、以下でトレイラーをご覧ください。
それからもう一つ。先ほどのジョイ・デイヴィジョンのドキュメンタリー映画と同年には、多数のロック・ミュージシャンを撮影していることでも知られる写真家アントン・コービン(Anton Corbijn)監督によるジョイ・ディヴィジョンの伝記映画『コントロール』も公開されています。以下でトレイラーをご覧ください。
映画『コントロール』の脚本は、イギリスの脚本家マット・グリーンハルシュ(Matt Greenhalgh) によって書かれましたが、その基になったのは、共同プロデューサーを務めたイアン・カーティスの妻デボラ・カーティス(Deborah Curtis)の伝記 Touching from a Distance が基になっています(同書の日本語訳は、先ほど紹介したデボラ・カーティス著、小野良造訳、『タッチング・フロム・ア・ディスタンス―イアン・カーティスとジョイ・ディヴィジョン』です)。
ついでに、前回と今回話題にしたポスト・パンクやニュー・ウェイヴについての書籍も紹介しておくと、『CROSSBEAT Presents from PUNK to POST-PUNK』 (シンコー・ミュージック、2018年)があります。それから『ロッキングオン』誌でも2022年 07 月号で「ニューウェイブ/ポストパンク 1978-1987」が特集されています。
さらに、ポスト・パンクに関する本で忘れてならない重要な本も日本語訳が出版されています。
サイモン・レイノルズ著、 野中モモ訳、新井崇嗣訳、『ポストパンク・ジェネレーション 1978-1984』(シンコーミュージック、2010年)
今(2023年4月28日)調べてみたら、このサイモン・レイノルズの本の日本語訳は、とてもとても残念なことに絶版でした。これは絶対に復刊した方がいいと個人的に強く思う本です。
ジョイ・ディヴィジョン及びニュー・オーダーの話から離れて、映画『マリー・アントワネット』の最後に流れてくる曲を紹介して今回の記事を締めくくりたいと思います。
70年代末のポスト・パンク期にデビューしたイギリスのバンド、ザ・キュアー(The Cure)の1981年のアルバム『フェイス(Faith)』の中の曲「オール・キャッツ・アー・グレイ(All Cats Are Grey)」です。どうぞ以下でお聴きください。
どこまでも暗い憂鬱を平穏さが包み込み、聞いているうちに不思議と癒しさえも与えてくれるかのような、この「オール・キャッツ・アー・グレイ」という曲が、『マリー・アントワネット』の最後のショットの後のエンディングに流れてくるのです。
ところで、映画『マリー・アントワネット』をご覧になっていない方は、史実としてのフランス革命のあの残酷な最後がどう描かれるか気になりませんか? もちろん、ここでは伏せておきますが、その最後のショットに関してだけ言うと、マリーの寝室が民衆の暴徒によって略奪され、ボロボロに破壊されているのが映し出されます。
そして、その後に流れてくる「オール・キャッツ・アー・グレイ」の長いイントロの後に、ザ・キュアーのシンガーのロバート・スミス(Robert Smith)の深いリバーブに包まれた物憂げな声が聴こえてきます。その歌詞の一節の「ホームに向かう自分に振られる旗はない(And no flags wave me home)」(homeは「家」、「故郷」、「墓場」、「死に場所」という多義的な意味に取れます)が、エンディングの少し前の場面――馬車に乗りながら離れていくベルサイユ宮殿を眺めながら、その地に最後の「さようなら」を言うマリーの姿――に重ね合わされて、映画を観終わった後にまで続くとても深い余韻を残すのです。
映画『マリー・アントワネット』について、まだいろいろ書くことがあります。今回はまったく触れなかった話題でしたが、ヴェルサイユ宮殿の思わず息をのむほどの美しい景色はもちろんのこと、一瞬一瞬に映し出されるインテリアやファッションなどを作り出した撮影監督やプロダクション・デザイナーやコスチューム・デザイナーなど製作者たちの信じられないほどの精緻な仕事ぶりにも目が離せません。それから音楽の話も、前回と今回ではポスト・パンクに焦点を絞ったたため、それ以外のジャンルの曲には触れていません。
こうした面を補ってくれるお勧めの記事が、CINEMOREの中にありました。宮代大嗣氏の記事「マリー・アントワネット」です。この宮代氏の記事では、映画『マリー・アントワネット』について多方面から書かれたレヴューが読めますので、どうぞご覧ください。
次回は、前回紹介したスージー・アンド・バンシーズの1991年の曲「キス・ゼム・フォー・ミー(Kiss Them For Me)」と前々回紹介したチャプターハウスの1991年の曲「パール(Pearl)」のリズムトラックが部分的に似ているのはなぜなのかという非常にニッチと思われる、おそらくほとんどの人にはどうでも良さそうな話題について書いたみたいと思います。
この記事が気に入ったら下のボタンでシェア!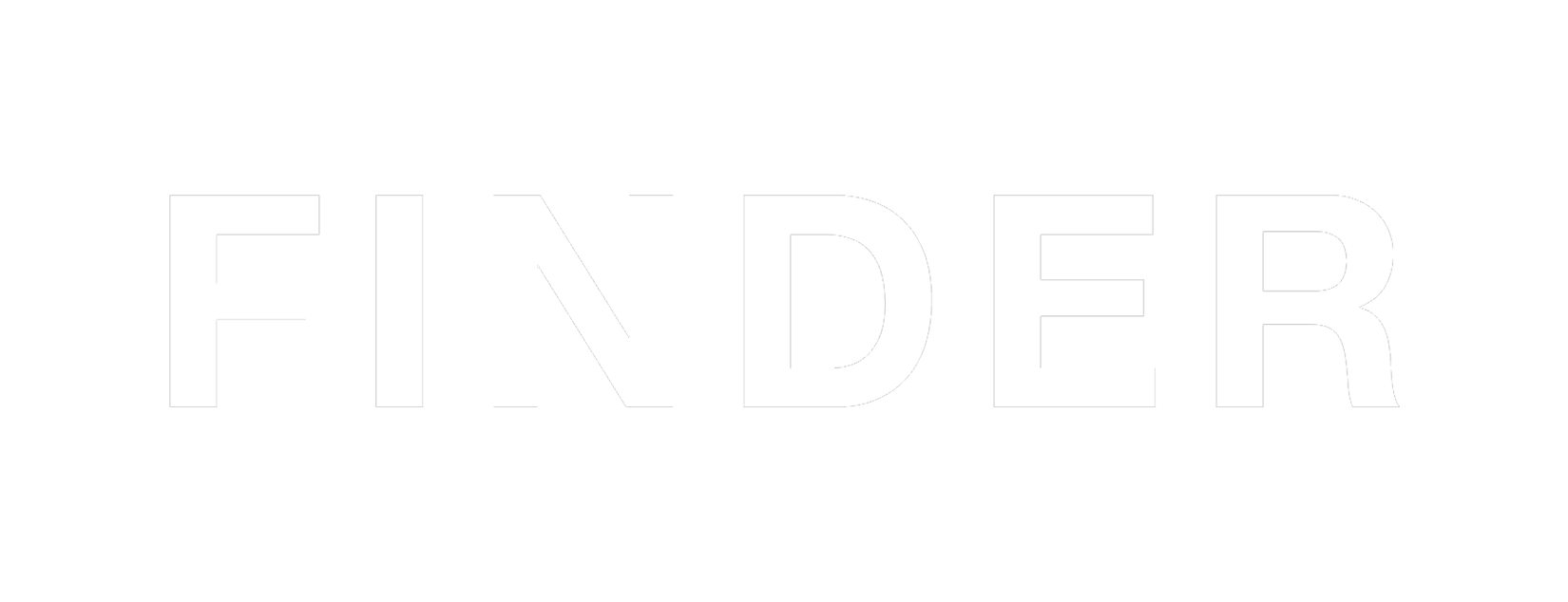 映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど
映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど





