最近の投稿
魔力の象徴としての「ヒョウ柄」:映画『媚薬』(1958年)の魔女ギルの衣装とインテリアから見る50年・・・映画『媚薬』(1958年)の中のビートニクな魔女とジャズが流れる占星術クラブ
「醜い老婆」から「若い女性」の姿へと変わっていく魔女(witch): 映画『オズの魔法使い』(193・・・
男性支配の物質主義的な世界の中で女性たちが求めること:映画『紳士は金髪がお好き』で「ヒョウ柄」の衣装・・・
記号としての「アニマル柄」:1934年の映画『特急20世紀』と1945年の『失われた週末』の中で「ヒ・・・
カテゴリ
フード&ドリンクビデオ・ゲーム
映画ポスター
ブック・カバー
ファッション
映画
インテリア
建築
音楽
ミュージック・ビデオ
コマーシャル映像
車・バイク
テレビ・シリーズ
アニメーション
アーカイブ
2024年1月2023年12月
2023年11月
2023年7月
2023年6月
2023年5月
2023年4月
2023年3月
2023年2月
2023年1月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
ブログについて
映画やTVドラマなどを観ていて、その中で流れてくる音楽、撮影に使われた建築やセットのデザイン、舞台の背景となるインテリア、登場人物が手にしているガジェットやプロダクトなどが気になったことはありませんか?
このブログでは、映画やTVドラマの中に登場するさまざまなものを調べて紹介していきます。そうしたものにも目を向けてみると、映画やTVドラマが今まで以上に楽しくなるはずです。映画、TVドラマ、音楽、建築、インテリアのどれかに興味がある方に、また自分と同じようにそのどれもが寝ても覚めても好きでたまらないという方に、面白いと思ってくれるような記事を発見してもらえたらという思いで書いています。
執筆者:伊泉龍一(いずみりゅういち)
ブログ以外には、以下のような書籍の翻訳をしたり、本を書いたりもしています。

ロバート・C・コトレル 著 伊泉 龍一 訳
『60sカウンターカルチャー ~セックス・ドラッグ・ロックンロール』

ドン・ラティン 著
『ハーバード・サイケデリック・クラブ ―ティモシー・リアリー、ラム・ダス、ヒューストン・スミス、アンドルー・ワイルは、いかにして50年代に終止符を打ち、新たな時代を先導したのか?』

デヴィッド・ヘップワース 著
『アンコモン・ピープル ―「ロック・スター」の誕生から終焉まで』

サラ・バートレット 著
『アイコニック・タロット イタリア・ルネサンスの寓意画から現代のタロット・アートの世界まで』
アーケード・ビデオ・ゲーム黄金時代のゲーム『バザーク』と『ストラトヴァクス(スピーク&レスキュー)』――フレッド・セイバーヘイゲンのSF小説『バーサーカー』の加藤直之氏によるカバー・アート。リチャード・M・パワーズのシュルレアリスム的なSFのカバー・アート。
ビデオ・ゲーム ブック・カバー 音楽 / 2023.02.28
前回は1970年代を代表する二つのアーケード・ビデオ・ゲーム、ナムコの『ギャラクシアン(Galaxian)』、アタリの『アステロイド(Asteroids)』について書きました。
このブログで、こうした古典的なアーケード・ビデオ・ゲームの話をしているのは、そもそも以前に1982年のスティーヴン・リズバーガー監督の映画『トロン(Tron)』の話をした流れからそうなりました。以前に書いたように、リズバーガー監督が同映画を生み出す発想の源となったのは、1972年のアタリのアーケード・ビデオ・ゲーム『ポン(Pong)』でした。そして同映画が製作されていた背景として、当時のいわゆる「アーケード・ビデオ・ゲーム黄金時代」の隆盛があったわけです。
ということで、前回に引き続き、今回はその当時にリリースされて大きな反響のあったアーケード・ビデオ・ゲームを見ていきます。
まずは、アメリカのプログラマー、アラン・マクニール(Alan McNeil )によって考案され、シカゴのスターン・エレクトロニクス(Stern Electronics) 社から1980年にリリースされたシューティング・ゲーム、『バザーク(Berzerk) 』から見ていきましょう。
迷路のような部屋の中で、プレイヤーはジョイ・スティックで緑色の棒状の人間を動かしながら、ボタンを押してレーザーを発射し、武装ロボットを倒していくシンプルなゲームです。プレイされたことがない方は、どうぞ以下でご覧ください。
プレイ中にときおりランダムに聞こえてくる「侵入者、警戒せよ! 侵入者、警戒せよ!(Intruder alert! Intruder alert!)」などのヴォイス・シンセサイザーによる機械的で耳障りなセリフが、敵と戦っている切迫感ないしは恐怖感を倍化させるのに絶大な効果を発揮しています。
『バザーク』はアーケード・ゲームの歴史の中で、音声合成を使用した最初のビデオ ゲームの 1 つです。
一方、日本のサン電子が開発し、同年に先んじてリリースした『スピーク&レスキュー』でも音声合成が使われています(アメリカでは『ストラトヴァクス(Stratovox)』というタイトルでタイトーがリリースしました)。
以下は、アメリカでリリースされた『ストラトヴァクス』のプレイ動画です。
降下してくる敵を撃退するという点では、前回の『ギャラクシアン』と似ていますね。当時としては、ビデオ・ゲームが言葉を発するという点で非常に画期的でしたが、合成音声の質自体は、いまだやはりあまりよくありませんね。しかも、『ストラトヴァクス』では前述の『バザーク』ほど、それがゲームの気分を盛り上げてくれるようには、残念ながらあまり感じられません。
ところで、Museum of the Gameの『バザーク』の解説ページによると、この当時、音声合成はLPC コーディングという技術を使用して行われたそうですが、圧縮するのに 1 ワードあたり 1,000 ドルもかかったそうです(現在の金額だと、おそよその三倍ぐらいの価格だと思われます)。
また、The Dot Eatersの中の記事‘Berzerk – Coins Detected in Pocket!’によると、『バザーク』というタイトルは、アメリカのサイエンス&ファンタジー作家フレッド・セイバーヘイゲン(Fred Saberhagen)の「バーサーカー(Berserker)」という小説のシリーズにちなんで名付けられました。
SF小説ファン以外の方には、「バーサーカー」と言っても、あまりなじみがないと思われますので、本題から話は逸れてしまいますが、ここで簡単に紹介しておきます。
セイバーヘイゲンの一連の小説に登場するバーサーカーは、はるか昔、地球外の 2 つの種族間の星間戦争の際に製造された知能を持ち、自己複製ができる機械です。その形もさまざまで人間に近い大きさの場合もあれば、小惑星規模の大きさになる場合もあります。そして、その目的は、全ての生命体を根絶することです。
と、説明をしてはみたものの、そもそもSF小説に興味のない人からすると、右から左の内容ですよね。だとしてもですよ、機械の自動化や人工知能の研究が進んできた現在の現実の世界でも、バーサーカーのような主体的に殺戮を行うようにプログラムされた戦争機械は、不気味な現実味を帯びてきていると言わざるをえません。
ついでに言っておくと、セイバーヘイゲンの作品にバーサーカーが登場するのは、1963年1月の『イフ(If)』誌の別冊アンソロジー『ワールズ・オブ・イフ(Worlds of If)』に掲載された短編小説「フォートレス・シップ(Fortress Ship) 」です。その後、1965 年までに雑誌に掲載された短編小説を集めた『バーサーカー(Berserker)』と題した短編集が1967年に出版されます(この短編集では、前述のバーサーカーの最初の短編「フォートレス・シップ」は「ウィズアウト・ア・ソート(Without a Thought)」と改題されています)。
その後、セイバーヘイゲンは、亡くなる2年前の2005年に出版された『ロウグ・バーサーカー(Rogue Berserker)』まで、「バーサーカー」のシリーズを書き続けました(シリーズは、単行本として17冊出版されています)。
「バーサーカー」が最初に登場するセイバーヘイゲンの1967年の短編集『バーサーカー』は、日本でも1980年に浅倉久志氏と岡部宏之氏の訳で『バーサーカー 赤方偏移の仮面』と題して早川文庫から出版されています。以下は、私自身の所有している初版本です。ぜひともバーサーカーの具体的な姿形が描かれた表紙の絵に、ご注目ください。

このカバー・アートの中の機械の姿は、早川書房の『SFマガジン』の挿絵や数多くのSF小説の表紙の絵を手掛けている加藤直之氏による「バーサーカー」のビジュアライズです(加藤直之氏は、田中芳樹氏の有名なSF小説『銀河英雄伝説』のイラストを描いていますので、そちらでのファンの方も非常に多いかと思われます)。
ここで、さらに本題から逸れることを承知の上であえて力説しておきたいのは、日本で翻訳されているSF小説の表紙の数々のイラストが持っている魅力です。
これは私個人の昔の思い出とも関連しています。10代の頃、私は海外のSF小説の翻訳本が大好きでした。書店で手にとっては、これもあれも面白そうと、いつも読む前から胸を高鳴らせてくれたのが、想像力をかきたてられずにはいられなくなる翻訳本独自のカバー・アートでした。加藤直之氏によるバーサーカーも、私にとって、そうした思い出深い絵の一つであることは言うまでもありません。
ところで、書評家の冬木糸一氏が、noteでの記事「好きなSF小説の表紙イラストレーターをずらずら並べる」で次のように語っていました。
「僕は基本的に本は全部電子書籍があるならそれで買うが、素晴らしい装幀だとそれは紙の本で持っていたくなる。中身を読むためではなくて、そのもの自体がほしいから」。
思わず「わかります、その気持ち」と共感してしまいました。
ついでに書くと、冬木氏が近々(2023年3月1日)出版される予定の本『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』(ダイヤモンド社)はすごく面白そうですね(もちろん、予約注文しました。届くのが楽しみです! )。内容については、冬木氏のブログ『基本読書』の紹介ページをどうぞご覧ください。
同じくnoteでSmall World氏が書かれている記事「SF小説を彩るイラストたちの記憶」では、「サイバーパンク」を中心にSF小説の表紙を飾ったイラストレーターたちが実際のカバー・アートとともに紹介されています。昔それらを読んでいた方は、きっと懐かしい気持ちになれると思います。しかも加藤直之氏のことにも触れられていますので、ぜひともお読みください。
さらにさらにのついでの話になりますが、『バーサーカー』の原著の表紙の方もご覧ください。

これはアメリカのバランタイン・ブックス(Ballantine Books)から1967年に出版された『バーサーカー』の初版の際のカバー・アートです。
ご覧の通り、日本での翻訳本のカバー・アートとはまったく違うイメージとなっています。つまり、先ほどの早川文庫のバーサーカーの絵は、加藤直之氏の独創的な想像力の賜物なのです。
ところで、こちらのバランタイン・ブックスからの原著の方の絵も、また違う味わいがあって魅力的だと思いませんか? それこそ絵画のお好きな方だったら、この絵を見て、1920年代のシュルレアリスムの絵画を彷彿させられませんか?
実は、この絵を描いたのは、シュルレアリスムからの影響をSFのイラストに持ち込んだことで知られているアメリカのイラストレーター、リチャード・M・パワーズ(Richard M. Powers)です(上の画像は、THE SCIENCE FICION COVER ART OF RICHARD M.POWERSの中の1960年代の作品ページから引用しました)。
英語圏のSF小説の熱心なファンの方だったら、リチャード・M・パワーズがカバー・アートに描いた見知らぬ世界の異様な景色を何度も目にしたことがあるでしょう。というか、SFマニアの方の中には、パワーズの絵自体のファンだという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
先ほど「シュルレアリスムからの影響」と言いましたが、中でもイヴ・タンギー(Yves Tanguy, 1900- 1955)の絵がお好みの方だったら、たとえSF自体に興味がなかったとしても、パワーズの作品に目を奪われるのではないかと思います。例えば、以下の二つの絵はいかがでしょうか?


一つ目は、アメリカのバークリー・メダリオン(Berkley Medalion)から1962年に出版されたイギリスの作家J・G・バラードの短編集『時の声(The Voices of Time)』のカバー・アートです。二つ目は、同じくバークリーから1963年に出版されたバラードの短編集『永遠へのパスポート(Passport to Eternity)』です(どちらも日本語訳が出ています。J・G・バラード著、吉田誠一訳、『時の声 』、創元SF文庫、1969年。J・G・バラード著、永井淳訳、『永遠へのパスポート』 、創元推理文庫、1970年)。
パワーズによるこれらのカバー・アートの普通ではない点を言えば、その絵が小説の中の特定のシーンや登場人物を描写しているわけでもなければ、物語の内容ともほぼ無関係だということです。
DAILY BEASTの中の‘Cover Story: Richard Powers’s Pulp Surrealism’という記事の中で、Mark Dery氏は次のようにパワーズの絵を評しています。
「ニューヨーク近代美術館で見られるようなものに染まっている彼のモダニスト的な感性は、何十年にもわたってこのジャンルを支配してきたパルプ誌のスタイル――宇宙飛行士が目の飛び出たエイリアンに胸筋を波打たせられ、一方で宇宙の色っぽい若い女性が恐怖に怯えている――とは一線を画している」。
実際、パワーズ自身も次のように語っています。
「サイエンス フィクションが私にとって魅力的だったことの 1 つは、その本のカバーとして必ずしも機能していなくても、それ自体で効力のあるシュルレアリストの絵を描くことが可能だったことだ」(引用は、Jane Frank , Richard Gid Powers , Vincent Di Fate ,The Art of Richard Powers, Paper Tiger, 2001より)。
ここで、パワーズとシュルレアリスムの絵を比較するため、一例として、イヴ・タンギーの1947年の作品『パルユ・ダンソムニ(Parure D’insomnie)』をご覧ください。以下の画像はArtsyの中のページから引用しました。

イヴ・タンギーからリチャード・M・パワーズへの影響は、ご覧の通り一目瞭然で、もはやあえて語る必要もないですよね。
SPACIAL ANOMALYの中のsockii氏の記事‘The Surreal Science Fiction Art of Richard M. Powers’には、パワーズの作品の明解な批評がありましたので、一部をそのまま引用しておきます。
「実際、パワーズは、タンギーや同時代のシュルレアリスト、一方でモダン・アートのクレー、ミロ、ピカソ、ゴーリキーのような人たちから影響を受けていることは間違いない。 多くの人は、これらの20世紀の現代の巨匠たちのアートの中に、リチャード・パワーズのアートは確かに位置づけられるべきだと言うだろう。だが、その「商業的」性質のために、彼の作品はイラストレーターとして、その当時の「純粋な芸術家」による作品に与えられたのと同レベルの敬意を与えられていない」。
また、前述のDAILY BEASTの中の記事では、Mark Dery氏がパワーズのアート・ワークを正当に評価すべく、次のように述べています。
「パワーズの作品は、遊び心のあるものでありながら本気の転覆だった。つまり、 イラスト(お金のために量産される)とファイン・アート(はるかに多くのお金のために量産される)の間のお高くとまった区別に異議を唱え、 エリート好み(ハイブロウ・モダニズム)と大量消費(パルプ・フィクション)の間の飛行禁止区域を違反したのだ」。
リチャード・M・パワーズは1996年に亡くなられるまで、途方もない数の素晴らしい作品を残しています。実際その中には、異彩を放っている見事な傑作も多数あります。それらについては、また別の機会に改めて紹介してみたいと思います。
今回は、以前の記事で書いた映画『トロン』からの流れで、「アーケード・ビデオ・ゲーム黄金時代」を代表するゲームの一つ『バザーク』を紹介するところから始まり、その題名の基になったSF作家フレッド・セイバーヘイゲンの一連の小説「バサーク」へと話が移り、そのカバー・アートに言及したことで、リチャード・M・パワーズの話題へと移ってしまいました。
今回の記事の最後として、リチャード・M・パワーズの作品からインスピレーションを受けて作られた音楽を紹介しておきます。
1977年にデヴューしたイギリスのロック・バンドのXTCのファンの方だったらご存じかもしれませんが、同バンドのシンガーでギタリストのアンディ・パートリッジ(Andy Partridge)が、2010年に500枚限定のCDとしてリリースしたアルバム『パワーズ(Powers)』です。
以下は、そのプロモーション動画です。同アルバムの曲の抜粋を聴きながらパワーズの作品がご覧いただけます。
念のために言うと、この動画で流れている音楽はイントロではありません。実際のアルバムのどの曲にも歌は含まれていません。全編にわたって、ただひたすら異世界的な音のみが響き渡るインストゥルメンタルの作品になっています。
アンディ・パートリッジは、子供の頃に地元の図書館でパワーズの絵を目にして、その異様な光景に魅入られたようです。で、このアルバムの中の曲は、少年時代に想像力をかきたてられたリチャード・M・パワーズのカバー・アートへのサウンドトラックなわけです。
確かに、遥か未来のどこかの世界の光景のようなものをシュルレアリスム的に表現しているパワーズの作品と重ね合わせて、アンドリュー・パートリッジの『パワーズ』のサウンドを聴いていると、何とも不思議な気持ちになっていきますね。
次回は、書く前から自分でこう言うのもなんですが、あまり読んでくれる人が少なそうな気のする話、『バザーク』と同じ年にリリースされた別のビデオ・ゲーム『ミサイル・コマンド』とそれに関連することを書いてみようかなと思っています。
この記事が気に入ったら下のボタンでシェア!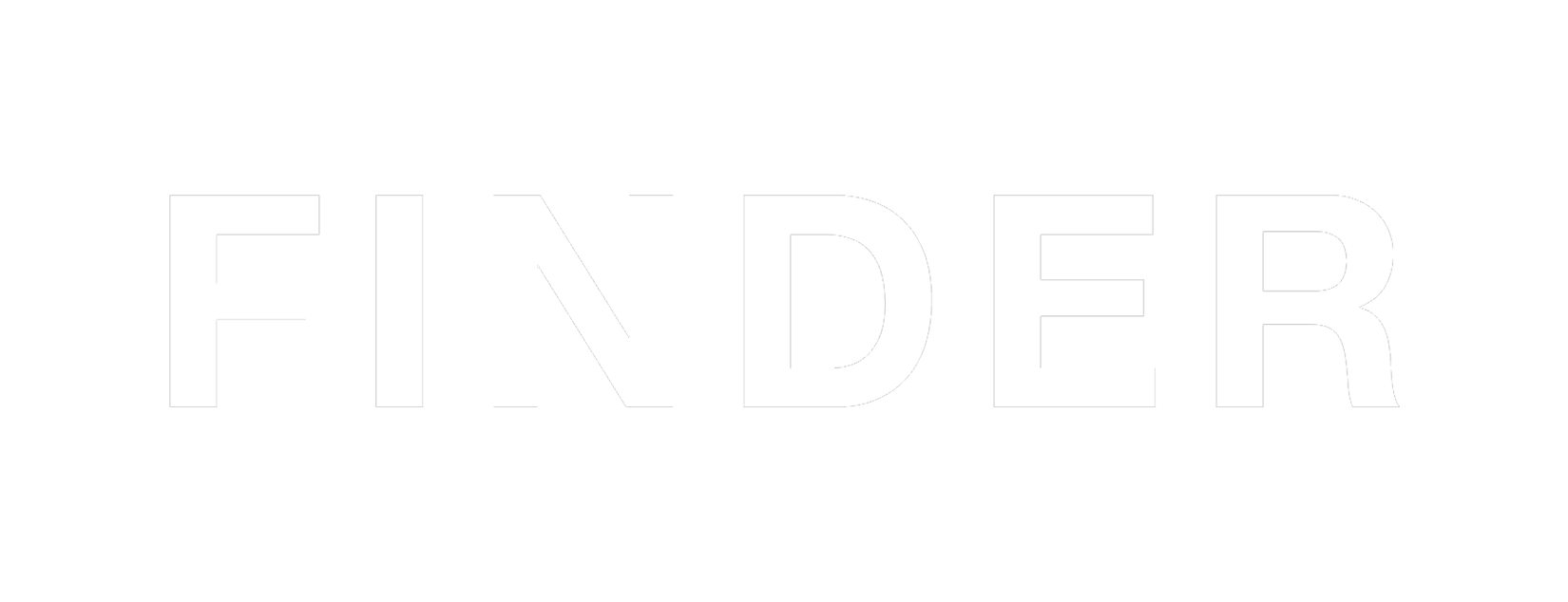 映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど
映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど


