最近の投稿
魔力の象徴としての「ヒョウ柄」:映画『媚薬』(1958年)の魔女ギルの衣装とインテリアから見る50年・・・映画『媚薬』(1958年)の中のビートニクな魔女とジャズが流れる占星術クラブ
「醜い老婆」から「若い女性」の姿へと変わっていく魔女(witch): 映画『オズの魔法使い』(193・・・
男性支配の物質主義的な世界の中で女性たちが求めること:映画『紳士は金髪がお好き』で「ヒョウ柄」の衣装・・・
記号としての「アニマル柄」:1934年の映画『特急20世紀』と1945年の『失われた週末』の中で「ヒ・・・
カテゴリ
フード&ドリンクビデオ・ゲーム
映画ポスター
ブック・カバー
ファッション
映画
インテリア
建築
音楽
ミュージック・ビデオ
コマーシャル映像
車・バイク
テレビ・シリーズ
アニメーション
アーカイブ
2024年1月2023年12月
2023年11月
2023年7月
2023年6月
2023年5月
2023年4月
2023年3月
2023年2月
2023年1月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
ブログについて
映画やTVドラマなどを観ていて、その中で流れてくる音楽、撮影に使われた建築やセットのデザイン、舞台の背景となるインテリア、登場人物が手にしているガジェットやプロダクトなどが気になったことはありませんか?
このブログでは、映画やTVドラマの中に登場するさまざまなものを調べて紹介していきます。そうしたものにも目を向けてみると、映画やTVドラマが今まで以上に楽しくなるはずです。映画、TVドラマ、音楽、建築、インテリアのどれかに興味がある方に、また自分と同じようにそのどれもが寝ても覚めても好きでたまらないという方に、面白いと思ってくれるような記事を発見してもらえたらという思いで書いています。
執筆者:伊泉龍一(いずみりゅういち)
ブログ以外には、以下のような書籍の翻訳をしたり、本を書いたりもしています。

ショーン・レヴィ著 伊泉龍一訳
『レディ・ステディ・ゴー! 60sスウィンギン・ロンドン』
伊泉龍一 (著)
『スピリチュアリズムの時代 1847-1903』
ポール・ガンビーノ (著), 伊泉 龍一 (監修, 翻訳)
『死を祀るコレクション:モダン・ゴシックという生き方、その住まい』
ドン・ラティン著 伊泉 龍一訳
『至福を追い求めて ―60年代のスピリチュアルな理想が 現代の私たちの生き方をいかに形作っているか』

ロバート・C・コトレル 著 伊泉 龍一 訳
『60sカウンターカルチャー ~セックス・ドラッグ・ロックンロール』

ドン・ラティン 著
『ハーバード・サイケデリック・クラブ ―ティモシー・リアリー、ラム・ダス、ヒューストン・スミス、アンドルー・ワイルは、いかにして50年代に終止符を打ち、新たな時代を先導したのか?』

デヴィッド・ヘップワース 著
『アンコモン・ピープル ―「ロック・スター」の誕生から終焉まで』

サラ・バートレット 著
『アイコニック・タロット イタリア・ルネサンスの寓意画から現代のタロット・アートの世界まで』
映画『媚薬』(1958年)の中のビートニクな魔女とジャズが流れる占星術クラブ
ファッション 映画 音楽 テレビ・シリーズ / 2024.01.16

前々回まではファッションにおける「ヒョウ柄」のイメージの変遷を考えるために、1930年代から1950年代の映画から一つずつ作品を選び(『特急二十世紀(Twentieth Century)』(1934年)、『失われた週末(The Lost Weekend)』(1945年)、『紳士は金髪がお好き(Gentlemen Prefer Blondes)』(1953年))、それらに登場する女優たちの衣装の意味に目を向けきました。
一方で前回は、映画『オズの魔法使い(The Wizard of Oz)』(1939年)と映画『奥様は魔女(I Married a Witch)』(1942年)とテレビ・シリーズ『奥さまは魔女(Bewitched)』(1964年-1972年)を通して魔女の姿と描かれ方の移り変わりを辿ってみました。続いて今回は、1958年のリチャード・クワイン(Richard Quine)監督の映画『媚薬(Bell, Book and Candle)』に登場する魔女の姿に目を向けてみたいと思います。
ところで、この時代の映画を好きな方だったら、仮に『媚薬』を観たことがなくても、その同年に公開されたアルフレッド・ヒッチコック(Alfred Hitchcock)監督の映画『めまい(Vertigo)』はご覧になられているのではないでしょうか?
映画『めまい』の話を持ちだしたのは、『媚薬』の主役の魔女ギルを演じるキム・ノヴァク(Kim Novak)とその相手役のシェプを演じるジェームズ・ステュアート(James Stewart)が、同年の前者の映画でも主役の二人として共演しているからです。ということは、5月に公開された『めまい』の中では謎に満ちた女性を演じたキム・ノヴァクの姿の記憶が新しいまま、12月に公開された『媚薬』では魔女の姿となってスクリーンに登場したわけです。
ひとまず『媚薬』を未見の方は、以下のトレイラーでその雰囲気をご覧ください。
トレイラーの冒頭の場面では、ベルと本が置かれているテーブルに魔女ギルが近づいてきてキャンドルを置きます。もちろんこれは、この映画の原題「Bell, Book and Candle(ベルと本とキャンドル)」を示すアイテムです。また、そもそもこの題名となっているこの「ベルと本とキャンドル」自体が、中世のローマ・カトリック教会で行われていた罪深い人間を追放する儀式を示唆しています。
また、役者名のクレジットが出る場面のたびに、アフリカの土着的な呪術を連想させるエキゾチックで少々不気味にも見える仮面や彫刻品が映し出されていました。これは自分が魔女であることを隠しながらギルがニューヨークのグリニッジ・ヴィレッジで経営しているプリミティヴな民族的アートを販売するショップに置かれている商品です。ここで映画のオープニングの方もご覧ください。
冒頭から先ほどのトレイラーと同じ曲が流れてきました。リチャード・クワイン監督の他の映画でもしばしばサウンドトラックを提供している作曲家ジョージ・ダニング(George Duning)が作った耳に残る軽快な曲が、魔女を主題としながらもコミカルな映画であることを最初から感じさせてくれます。そして、そこからすぐに「ジングル・ベル」のメロディーへとつながり、ギルの店の外の雪が降っている景色が映し出されます。そう、この映画はホリデー・シーズンにぴったりなクリスマス映画なのです。
「クリスマス」と言えば、一般的にキリスト教の行事ですから異教徒の魔女にとっては好ましくない日のはずです。けれども、この映画の魔女たちはプレゼントまで交換し合いクリスマスを祝っています。しかもギルは、飼い猫のパイワケットに「クリスマスに私へ何かくれない?」と話しかけもします。過去の実際の歴史において、教会から「魔女」と呼ばれた人々は悪魔に使えていると断じられ、激しく迫害されてきたにもかかわらずです。
先ほどのオープニング・タイトルの動画でも、ジルのショップの窓から、ちょっと風変わりなデザインのクリスマスツリーが見えました。以下のよりはっきり映っている別の場面をご覧ください。

このクリスマスツリーはもみの木などの生木ではなく、フレームの部分は見たところ青銅のようです。そこにゴールドのオーナメントが飾りつけられているだけの非常にミニマルな作りですが、とてもモダンな美しいクリスマスツリーだと思いませんか?
前回の記事で取り上げた1942年の映画『奥様は魔女』の場合、その冒頭でキリスト教から異端の烙印を押された魔女という点を示唆するシーンがありました。そこでは、アメリカの過去の歴史の中でピューリタンによって行われた魔女裁判と関連する場面が描かれていました。ですが、クリスマスツリーを飾っている魔女が主役の『媚薬』の方には、そういったことへの言及はありません。
ただし、『媚薬』にも魔女裁判を暗示するモチーフがないわけではありません。それはジルの飼い猫です。その「パイワケット(Pyewacket)」という名前が指し示しているのは、17世紀のニューイングランドの魔女狩りの記録です。
マサチューセッツ州の魔女の伝承や史実を集めたWitches and Warlocks of Massachusetts: Legends, Victims, and Sinister Spellcastersの著者Peter Muise氏のNEW ENGLAND FOLKLOREの中の記事‘Pyewacket: A Familiar Spirit with Origins in New England’によると、「パイワケット」は、ニューイングランドの悪名高い魔女狩りの推進者マシュー・ホプキンス(Matthew Hopkins)が1644年に魔女の集会で見たと称しているファミリア・スピリット(familiar spirit)の名前です(ファミリア・スピリットというのは、日本語では「使い魔」と訳されていますが、魔女のアシスタントとしての役目を果たす大概は動物の姿をした霊のことです)。
実際、映画『媚薬』の中でギルが魔法を使うときは、いつもパイワケットの助力を借ります。以下で、翌日に婚約者との結婚式を控えているシェプに魔法をかけて、自分に恋をさせるようとして呪文を唱える場面をご覧ください。
ギルの美しいブルーの目とシャム猫の目がクローズアップされたこの場面で聞こえてくる呪文のハミングは、映画のイントロダクションで使われていたテーマ曲と同じ旋律です。その後、魔法が効き始めたときに、再びストリングスが同じ旋律を奏で始めたかと思うと、そのままロマンティックなメロディーへと途切れることなく移行しながら、うっとりとしたラブシーンへと向かうわけです。
ここでのギルのファッションにも注目してみましょう。長袖で背中が大きく開いたダークな色のイブニング・ドレスを着ています。これは前回見た『オズの魔法使い』の「西の魔女」に代表されるハリウッドが生み出した古典的な魔女の姿とは異なります。とはいえ、1950 年代後半に多くのアメリカの女性たちが好んで着ていたような明るく陽気なファッションとは明らかに異なります。
とりわけ、以下のジリアンの服装をご覧ください。これも当時のアメリカで受け入れられていた「女性らしさ」の理想とはかけ離れているように見えます。

ここで映画の舞台が1959年のニューヨークのグリニッジ・ヴィレッジだということを前提にしながら見直してみると、このギルのファッションは、やはりビートニクとのつながりを連想させます。cut print filmの中の記事‘Insidious Fashion: Costuming as Propaganda in Bell, Book, and Candle’でAmy Anna氏は次のように指摘しています。
「映画の序盤で、ジルは黒のタートルネックに黒のパンツ(50年代!)を身に着け、黒ヒョウのしなやかさとビートニクのシックさを一体化している。彼女は素足でこのアンサンブルを完成させ、彼女のワイルドで型にはまらない性質を強調している」。
ここで念のため「ビートニク(beatnik)」という言葉についても簡単に説明しておきましょう。
20世紀のアメリカの文学史に詳しい方だったら、「ビート・ジェネレーション(Beat Generation)」と呼ばれる第二次世界大戦後の1940年代後半から1960年代前半にかけてのアメリカ文学のサブカルチャーをご存じかと思います。当時の消費主義的で物質主義的で順応主義的な主流の価値観や規範を拒否し、精神的な探求を重視した詩人や小説家たちが、その動向の中核となりました。
歴史家のロバート・C・コトレル(Robert C. Cottrell)氏は、ビート作家たちがいかに当時の社会の全般的な価値観に対して反逆的であったかを次のように述べています。
「[彼らは]広く浸透している文学の様式や主題にも異議を申し立てた。宗教、政治、労働倫理、核家族、婚姻、一夫一婦制、教育、さらに折に触れて西洋思想全体なども含めて、神聖で侵さざるべきものなどほとんどなかった」(Robert C. Cottrell, Sex, Drugs, and Rock ‘n’ Roll: 1960’s American Counterculture, Rowman & Littlefield Publishers, 2017より)。
ビート文学を代表する作品として有名なのは、アレン・ギンズバーグ(Allen Ginsberg)の「吠える(Howl)」(1956 年にHowl and Other Poemsとして出版)、ジャック・ケルアック(Jack Kerouac)の小説『路上(On the Road)』(1957 年)、ウィリアム・S・バローズ(William S. Burroughs)の小説『裸のランチ(The Naked Lunch)』(1959 年)などです。
映画『媚薬』の舞台となったニューヨークのグリニッジ・ヴィレッジに1958年にオープンしたガスライト・カフェ(Gaslight Cafe)では、アレン・ギンズバーグやグレゴリー・コーソ(Gregory Corso)らによるビート詩の朗読が行われていました。ちなみに、後のガスライト・カフェにはボブ・ディランやジョニ・ミッチェルのようなフォークのミュージシャンたちも出演するようになります。
一方、「ビートニク(beatnik)」という語は、1958 年4月2日に『サンフランシスコ・クロニクル(San Francisco Chronicle)』紙のコラムニスト、ハーブ・ケイン(Herb Caen)によって作られました。これは1957 年 10 月に打ち上げられた史上初の人工衛星「スプートニク」の接尾辞「nik」をもじったもので、ビートたちに対する軽蔑的な意味を込めて用いられました(Herb Caen, “Herb Caen,” San Francisco Chronicle, April 2, 1958; Jesse Hamlin, “How Herb Caen Named a Generation,” San Francisco Gate, November
26, 1955を参照)。
歴史家のスティーヴン・ペトルス(Stephen Petrus)氏は、1957年から1960年にかけての数年間は、「ビートニクの異議の受け入れと流行の出現、つまり文化的抗議が商品に変わった」時期だったと指摘し、その頃のメディアの報道がビートニクのステレオタイプ的なイメージを形作っていくことになったと述べています(Stephen Petrus, Rumblings of Discontent: American Popular Culture and its Response to the Beat Generation, 1957-1960, in Studies in Popular Culture, Vol. 20, No. 1, October 1997, pp. 1-17)。
それに伴いタートルネックのセーター、サンダル、タイトな黒のパンツ、サングラスを身に着け、顎鬚を生やし、詩を朗読し、ボンゴ・ドラムを演奏するというのが、ビートニクの一般的なイメージとして広く認知されていくことになります。
ただし、ムーヴメントの実際の中心にいたビート作家たちが必ずしもそうした服装をしていたわけではありません。その証拠に、ロバート・フランク(Robert Frank)とアルフレッド・レスリー(Alfred Leslie)が監督した1959年のアメリカの短編映画『プル・マイ・デイジー(Pull My Daisy)』を以下でご覧ください。ジャック・ケルアックがナレーションを提供し、ビート詩人のアレン・ギンズバーグ、グレゴリー・コーソ、ピーター・オーロフスキー(Peter Orlovsky)が本人役で出演しています。
ご覧の通り、ビート作家や詩人たちは誰も先ほど述べたようなビートニクの典型的服装をしていませんね。
ところで、1959年9月29日から1963年6月5日までCBSで放送されたアメリカのテレビ・シリーズ『ドビー・ギリスの青春(The Many Loves of Dobie Gillis)』を観たことがある方はいらっしゃいますか? で、その中のボブ・デンバー(Bob Denver)が演じたメイナード・クレブスというキャラクターを覚えていらっしゃいますか?
彼のキャラクターは当時の典型的なビートニクを描いたもので、顎鬚を生やし、「ヒップ」な言葉遣いをし、ジャズを好み、主流社会の規範を嫌い、「仕事」、「結婚」、「警察」といった言葉に過剰反応をします。 しかも、ビートニクのステレオタイプであるボンゴ・ドラムを演奏するシーンすらあります。以下でご覧ください。
この『ドビーの青春』は、現時点(2024年1月16日時点)で、残念ながら日本でのDVDやブルーレイの販売はされいないようです(配信もありません)。こういう昔のドラマは、どういうわけかその当時の日本語吹き替えとかで見ると妙に面白いと思うのは私だけでしょうか? なので、日本語吹き替えをどこかで再放送、ないしは配信してくれることを切に期待しています。
もう一つ当時のビートニクのステレオタイプ的なイメージを確認するために、『媚薬』の前年の1957年に公開されたスタンリー・ドーネン(Stanley Donen)監督のミュージカル映画『パリの恋人(Funny Face)』の中の一場面をご覧ください。ジョー・ストックトンを演じる主役のオードリー・ヘプバーン(Audrey Hepburn)がパリのボヘミアンなバーで前衛的な踊りを披露する姿が見れます。
『パリの恋人』の中でヘプバーン演じるジョー・ストックトンは、パリでモデルの仕事をする前は、当時のビートニクのまさに中心地グリニッジ・ヴィレッジにある書店で働く地味な恰好をした店員でした。このパリのボヘミアンな地下のバーで、フレッド・アステア(Fred Astaire)が演じるファッション写真家ディック・エイヴリーが持っている古い男女の規範についての考え方に対して、ジョーは次のように言います。「あなたは石器時代からやってきたに違いないわ」。そして、ジョーは自身を解放し、自由に表現するために即興的な踊りを開始するわけです。
ご覧の通り、ここでのヘプバーンの衣装は先ほどのキム・ノヴァク演じる魔女ギルと同様、上から下までビートニクのファッションの特徴のひとつである黒です。
こうした当時のビートニク的なファッションは、クリスチャン・ディオールが1947年春夏コレクションとして発表し、1950年代を通して人気となった細く絞ったウエストや長いゆったりとしたスカートが特徴的なエレガントでフェミニンな「ニュー・ルック(New Look)」と呼ばれたスタイルへの反逆のようにも見えます。
とすると、ニュー・ルックとはまったく異質なギルのビートニク的な衣装は、その時代に一般的に求められる「女性らしさ」に従わず、「スクエア」な価値観から逸脱し、自由奔放に生きる女性を表現しているようにも思えます(「スクエア」と言うのは当時のビートニクたちが、主流に属する堅苦しくつまらない人間や生き方を指すのに使っていた言葉です)。実際、先ほどのビートニク的な黒の服を着ているときのギルは(『パリの恋人』の中のジョーも)型にはまった慣習にとらわれない自由奔放な女性のように振る舞ってています。
ついでに言うと、当時のビート作家たちは、新たな経験や着想を求め、国内だけでなくメキシコ、モロッコ、インド、日本、フランスなどへも旅をしていました。映画の中でジルも過去にメキシコで一年間過ごしていたと語る場面があります。
さらに当時のビートについてもう一つだけ言うと、彼らが好んで聴いていた音楽は、サックス奏者のチャーリー・パーカー(Charlie Parker)やトランペット奏者のディジー・ガレスピー(Dizzy Gillespie)らによって開拓された即興を重視するビバップ(bebop)とも呼ばれたジャズでした(先ほど述べた『ドビー・ギリスの青春』に登場するビートニク、メイナード・クレブスも頭の中にはいつもジャズが流れているというほど大好きでした)。
「ジャズ」と関連して興味深いのは、映画『媚薬』の中の魔女たちや男性の魔法使い(warlock)たちも、グリニッジ・ヴィレッジの地下のジャズ・クラブをたまり場としている点です。しかも魔女ギルの弟のワーロックであるジャック・レモン(Jack Lemmon)演じるニッキーは、そのクラブの中で、ビートニクの典型としてすでに言及したボンゴ・ドラムを演奏しています。
以下で、『媚薬』の中のグリニッジ・ヴィレッジにあるジャズ・クラブをご覧ください。1分28秒あたりからクラブ内のシーンが始まり、最初はフランスのマイム・アーティストのフィリップ・クレイ(Philippe Clay)がカメオ出演し、「ル・ノイエ・アサシネ(Le Noyé Assassiné)」という曲に合わせて体をくねらせていますが、肝心のボンゴ・ドラムを伴う演奏シーンは5分10秒あたりから始まります。
この動画の終わりの方で、ジャニス・ルール(Janice Rule)演じるメルルは気も狂わんばかりなって立ちあがります。そのときに流れている曲「ストーミー・ウェザー(Stormy Weather)」のトランペットを実際に演奏しているのは、ジャズ・ミュージシャンのピート・カンドリ(Pete Candoli)とコンテ・カンドリ(Conte Candoli )の兄弟です。しかも、この場面で演技しているのも実際に本人たちです(どうでもいい細かい話ですが、ミュートしたトランペットのサウンドなのに、画面に映る二人のトランペットはミュートされていませんでした)。
CINEMA MEDIATIONSの中の記事‘IF I Could I Would Live in ‘Bell Book and Candle”でMary Gallacher氏は、この映画を「50年代のグリニッジ・ビレッジのビートニク・ジャズ・クラブ・コーヒー・ハウスやアート・シーンへのラブレター」でもあると述べていますが、確かにそう思えてなりません。
ただし、このジャズ・クラブは、さすがに魔女や魔術師たちの社交の場ということだけあって、ビートニクに加えて、ちょっとオカルト的な味付けがあります。
何と言っても、このクラブの名前は「ゾディアック・クラブ(Zodiac Club)」です。Zodiacという語は日本語では一般的「獣帯」と訳されていますが、ここでの「ゾディアック・クラブ」という名前は、明らかに占星術(astrology)(日本でのより一般的な言い方で言えば「星座占い」)との関連を示唆しています。確かに以下の場面をご覧になると明らかなように、クラブ内の壁も占星術的な天空をイメージさせる柄で装飾されています。

シェプとメルルの背景の壁に、円と点で構成された単純な図が見えますが、これは占星術で太陽を表す記号です。
また、先ほどの動画の最初の方で見られるように、シェプとメルルがゾディアック・クラブの入り口までやってきたとき、インド人風の服装をした受付の男に次のように誕生日を尋ねられる場面もあります。
「あなたの生年月日は?」
「ああ、3月12日だ」。
「魚のサインだね」。
この「魚のサイン(Sign of the fish)」というのは、いわゆる「魚座」のことです。
どうでもいい細かい話をすると、「星座占い」は通常12の星座です。ところがです。以下でゾディアック・クラブのエントランスの画像をご覧ください。

エントランスを囲むアーチを飾る円形の中には星座の絵が描かれています。ですが、数えてみると10しかありません。どういうわけか星座がふたつ足りないのです。その本当の理由は分かりませんが、まあ、たぶん製作者たちが星座占い自体にさしたる興味がなく、ここの場面のセットに正確さを求めなかったということなのでしょう。
いずれにせよ、ニューヨークという大都会で社会の規範から逸脱して生きる変わり者の魔女たちには、ビートニクに加えて、当時の若者たちの間でサブカルチャーとして浸透しつつあった占星術もふさわしいアイテムとして考えられていたわけですね。
ビートニクやジャズや占星術(星座占い)との関連を指摘したことで、思いのほか長くなってしまいました。ですので、本題として論じるつもりだった『媚薬』の中の「ヒョウ柄」の衣装の意味については次回に書くことにします。
最後に、今回のビートとジャズの話に関連する心底お勧めの本を紹介しておきます。昨年(2023年)4月20日に山形浩郎氏と森本正史氏の翻訳で出版されたマーティン・トーゴフ著『ジャズとビートの黙示録――人種、ドラッグ、アメリカ文化』です。2016年に出版された原著を楽しみにして即買ったものの本棚に置いたままにしてましたが、日本語訳も出たのがうれしくてこちらも即買いしました。題名通りの内容ですので、「ジャズ」、「ビート」、「人種」、「ドラッグ」というキーワードで好奇心を刺激された方は、ぜひともお読みください。
それとついでにもう一つだけ。先ほどビートニクの説明の際に引用したロバート・C・コトレル氏の著書Sex, Drugs, and Rock ‘n’ Roll: 1960’s American Countercultureが、今年(2024年)の春頃に『60sカウンター・カルチャーーーセックス・ドラッグ・ロックンロール』というタイトルで日本語訳が出版される予定です。同書の第2章と第3章では、アレン・ギンズバーグやジャック・ケルアックを中心とするビート・ジェネレーションの当時の状況について詳しく書かれています。実は私自身が翻訳した本なので宣伝的になってしまいますが、ご興味のある方はぜひチェックしてみていただけると幸いです。
この記事が気に入ったら下のボタンでシェア!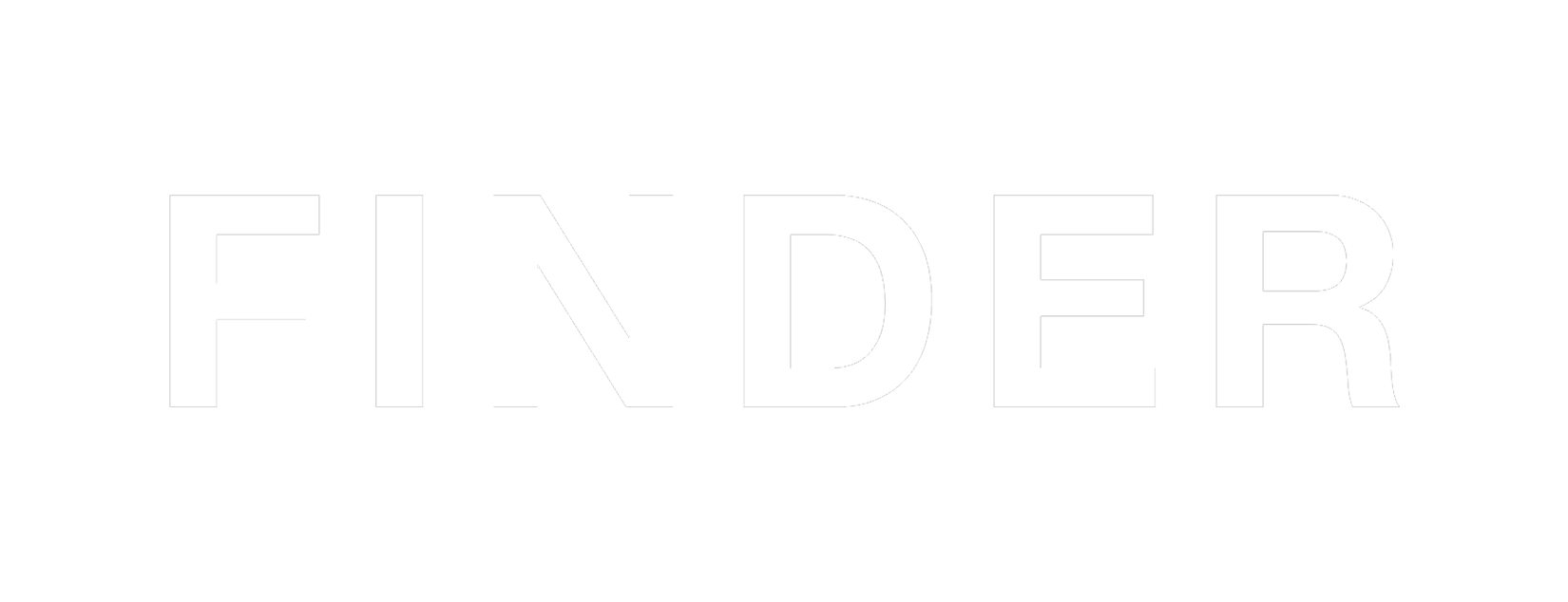 映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど
映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど





