最近の投稿
魔力の象徴としての「ヒョウ柄」:映画『媚薬』(1958年)の魔女ギルの衣装とインテリアから見る50年・・・映画『媚薬』(1958年)の中のビートニクな魔女とジャズが流れる占星術クラブ
「醜い老婆」から「若い女性」の姿へと変わっていく魔女(witch): 映画『オズの魔法使い』(193・・・
男性支配の物質主義的な世界の中で女性たちが求めること:映画『紳士は金髪がお好き』で「ヒョウ柄」の衣装・・・
記号としての「アニマル柄」:1934年の映画『特急20世紀』と1945年の『失われた週末』の中で「ヒ・・・
カテゴリ
フード&ドリンクビデオ・ゲーム
映画ポスター
ブック・カバー
ファッション
映画
インテリア
建築
音楽
ミュージック・ビデオ
コマーシャル映像
車・バイク
テレビ・シリーズ
アニメーション
アーカイブ
2024年1月2023年12月
2023年11月
2023年7月
2023年6月
2023年5月
2023年4月
2023年3月
2023年2月
2023年1月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
ブログについて
映画やTVドラマなどを観ていて、その中で流れてくる音楽、撮影に使われた建築やセットのデザイン、舞台の背景となるインテリア、登場人物が手にしているガジェットやプロダクトなどが気になったことはありませんか?
このブログでは、映画やTVドラマの中に登場するさまざまなものを調べて紹介していきます。そうしたものにも目を向けてみると、映画やTVドラマが今まで以上に楽しくなるはずです。映画、TVドラマ、音楽、建築、インテリアのどれかに興味がある方に、また自分と同じようにそのどれもが寝ても覚めても好きでたまらないという方に、面白いと思ってくれるような記事を発見してもらえたらという思いで書いています。
執筆者:伊泉龍一(いずみりゅういち)
ブログ以外には、以下のような書籍の翻訳をしたり、本を書いたりもしています。

ショーン・レヴィ著 伊泉龍一訳
『レディ・ステディ・ゴー! 60sスウィンギン・ロンドン』
伊泉龍一 (著)
『スピリチュアリズムの時代 1847-1903』
ポール・ガンビーノ (著), 伊泉 龍一 (監修, 翻訳)
『死を祀るコレクション:モダン・ゴシックという生き方、その住まい』
ドン・ラティン著 伊泉 龍一訳
『至福を追い求めて ―60年代のスピリチュアルな理想が 現代の私たちの生き方をいかに形作っているか』

ロバート・C・コトレル 著 伊泉 龍一 訳
『60sカウンターカルチャー ~セックス・ドラッグ・ロックンロール』

ドン・ラティン 著
『ハーバード・サイケデリック・クラブ ―ティモシー・リアリー、ラム・ダス、ヒューストン・スミス、アンドルー・ワイルは、いかにして50年代に終止符を打ち、新たな時代を先導したのか?』

デヴィッド・ヘップワース 著
『アンコモン・ピープル ―「ロック・スター」の誕生から終焉まで』

サラ・バートレット 著
『アイコニック・タロット イタリア・ルネサンスの寓意画から現代のタロット・アートの世界まで』
男性支配の物質主義的な世界の中で女性たちが求めること:映画『紳士は金髪がお好き』で「ヒョウ柄」の衣装を着たマリリン・モンローから「マテリアル・ガール」のマドンナまで
ブック・カバー ファッション 映画 音楽 ミュージック・ビデオ / 2023.12.26

前回から「アニマル柄」というモチーフについて書いています。その中でも、前回はとりわけ人の目を引き付けると同時に、そこに記号的な意味を読み込んでしまうがゆえに、好みが分かれがちな「ヒョウ柄」へと着目し、その過去におけるイメージを振り返ってみました。その際、1934年の映画『特急20世紀(Twentieth Century)』と1945年の『失われた週末(The Lost Weekend)』を取り上げてみました。
今回も過去の時代にヒョウ柄が意味していたことを見ていこうと思います。そこでハワード・ホークス(Howard Hawks)監督の1953年のミュージカル・コメディ映画『紳士は金髪がお好き(Gentlemen Prefer Blondes)』を一例として見てみます。
『紳士は金髪がお好き』を観たことがないという方は、ひとまず以下のトレイラーをご覧ください。
ミュージカル映画が好きな方はもちろんのこと、ミュージカル映画が苦手という方でも、『紳士は金髪がお好き』をまだ観たことがないというなら、ぜひ一度ご覧になることをお勧めします。非常に有名で人気のあるこの映画に対して今さら言うまでもないことかもしれませんが、きらびやかな舞台や音楽を背景に多彩な衣装を着て歌って踊る2人の主演の女優、マリリン・モンロー(Marilyn Monroe)とジェーン・ラッセル(Jane Russell)がそれぞれ個性的でユーモラスな素晴らしい演技を披露してくれます。しかも見事な娯楽作品であるだけでなく、その物語の背後にはその時代への風刺すら感じられます。
アメリカの映画批評サイトRotten Tomatoesを見ても『紳士は金髪がお好き』が、‘100 BEST MUSICAL MOVIES OF ALL TIME’(史上最高のベスト・ミュージカル映画100)の中の第6位に選ばれています。ちなみに、同サイトでの1位から10位は以下の通りとなっています。
第1位 『雨に唄えば (Singin’ in the Rain)』(1952年)、監督: スタンリー・ドーネン(Stanley Donen)、ジーン・ケリー(Gene Kelly)
第2位 『トップ・ハット(Top Hat)』 (1935年)、監督: マーク・サンドリッチ(Mark Sandrich)
第3位『セント・ルイスで会いましょう』 (1944年)、監督: ヴィンセント・ミネリ
第4位『オズの魔法使い(The Wizard of Oz) 』(1939年)、監督: ヴィクター・フレミング(Victor Fleming)
第5位『『ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!』(A Hard Day’s Night)』 (1964年)、監督: リチャード・レスター(Richard Lester)
第6位 『紳士は金髪がお好き(Gentlemen Prefer Blondes)』(1953年)、監督: ハワード・ホークス(Howard Hawks)
第7位 『スタア誕生(A Star Is Born)』 (1954年) 監督: ジョージ・キューカー(George Cukor)
第8位 『ロシュフォールの若い娘たち(Les Demoiselles de Rochefort)』 (1967年) 監督: ジャック・ドゥミ(Jacques Demy)
第9位 『シェルブールの雨傘(Les Parapluies de Cherbourg )』(1964年) 監督: ジャック・ドゥミ(Jacques Demy)
第10位 『ONCE ダブリンの街角で(Once)』 (2007年) 監督: ジョン・カーニー(John Carney)
さて、今回の主題の「ヒョウ柄」の話に移りましょう。まずは『紳士は金髪がお好き』の中のマリリン・モンロー演じるローレライ・リーの姿をご覧ください。画像はPinterestから引用しました。

マリリン・モンロー演じるローレライ・リーは、お金とダイヤモンドに目がなく、経済的に裕福な男性に近づき誘惑する小悪魔的なショーガールです。そして、この場面はパリへと向かう豪華客船に乗ろうとするシーンです。彼女がドレスの上にヒョウ柄のケープとマフを身に着けて登場すると、周囲の男性たちの目が彼女の美しい姿に釘付けになります。
実際のシーンは以下の動画でご覧ください。途中で切れてしまって残念ですが、冒頭から14秒までのあたりで確認ください。
このシーンのヒョウ柄の衣装は、自らの若さと美貌を使って金持ちの男を捕まえることで、富を手に入れると同時に社会的階級を上昇しようと狙っている女性の姿を強調しているように思えます。
このブログの前回の記事で見た1934年の映画『特急20世紀』では、大きな成功を手に入れて傲慢になった女優をヒョウ柄が際立たせていました。また、1945年の映画『失われた週末』では、その女性が裕福な階級出身であることをヒョウ柄が暗示していました。一方、この『紳士は金髪がお好き』の場面では、物欲に満ちたいまだ成功していない愚かしい女性の衣装としてヒョウ柄が採用されています。
今「愚かしい」と書きましたが、『紳士は金髪が好き』の面白いところは、このシーンからさらに物語が進んで行くにつれて、ローレライ・リーが単なる「愚かしい女性」だとは見えなくなっていきます。そして、彼女のダイヤモンドへの執着や厚かましい言動が、男性支配の資本主義が生み出す過剰な富の蓄積への皮肉にすら感じられるようにもなっていきます。
その観点から改めて振り返ると、ローレライ・リーの身に着けていたヒョウ柄は、男性中心的な社会的な性役割のルールに縛られたゲームの中で、それに従いながら男性の欲望を逆手に取ることのできるしたたかな女性のイメージにふさわしいもののようにも見えます。しかも、ショーガールという職業であるローレライは男性たちから品定めされる客体として見られる側にいるにもかかわらず、むしろ金を持った特権階級の愚かな男性たちを獲物として狙う捕食者となっていることをヒョウ柄が暗示しているようにすら感じられます。
とはいえ、『紳士は金髪がお好き』の物語の展開には、いろいろと考えさせられる点があります。映画の終わりで結婚という形での成功と幸せを手に入れた2人のショーガールは勝利したかのよう見えます。ですが、男性中心的な社会のゲームの外に出たわけではないため、結果的に当時の男女間の規範を肯定しつつ強化しているのではないかという見方もできなくもないでしょう。だとしても『紳士は金髪がお好き』が、その全体を通して1950年代の社会における階級やジェンダーへの風刺となっていることは確かです。
この点に関して、AV CLUBの記事‘Gentlemen Prefer Blondes is bubbly and smart, just like Marilyn Monroe’の中でCaroline Siede氏は次のようにも評しています。
「表面的には、社交界を這い上がろうとする 2 人の腹黒いショーガール、すなわち頭の弱いローレライ・リー (モンロー) と機知に富んだ男たらしのドロシー・ショー(ジェーン・ラッセル)の必死の悪だくみを中心とした90 分間の女性蔑視的な結末の落ちになっているように見えるかもしれない。ありがたいことにも『紳士は金髪がお好き』はまったく逆だ。これは夜会服とダイヤモンドで全てが飾り立てられ、女性の巧妙な策と結束の称賛にもなっているジェンダーと階級に関する小癪な社会風刺なのだ」。
社会風刺という点で言えば、そもそも映画『紳士は金髪がお好き』の原作となった小説『紳士は金髪がお好き――プロフェッショナル・レディの輝かしい日記(Gentlemen Prefer Blondes: The Intimate Diary of a Professional Lady)』にも目を向けてみる必要があります。
1925年に出版されて大ヒットした同小説は、ハリウッドの脚本家だった作者のアニタ・ルース(Anita Loos)が自身の人生の経験、とりわけ「自分の職業上の野心に対して場所を開けようとしない家父長制的な世界に対する絶え間ない戦い」を小説の中へ風刺的に反映させています(「」の引用文はAV CLUBの記事‘Gentlemen Prefer Blondes is bubbly and smart, just like Marilyn Monroe’より)。
以下は、グロセット&ダンラップ(Grosset & Dunlap)社から1926年に出版された『紳士は金髪がお好き』のセカンド・エディションのカバーです。表紙の絵を描いたのは、アメリカの漫画家で風刺画家のラルフ・バートン(Ralph Barton)です。画像はWikipediaから引用しました。

アニタ・ルースは、1953 年の映画版の製作に直接関わってはいません。ですが、その小説の風刺的な特徴は確かに映画版へと引き継がれています。THE CINESSENTIALの中の記事‘The Hawksian Women: Dorothy and Lorelei’ でPatrick Brown氏は、小説と映画を比較して次のように述べています。
「ルースの小説 [1925年] は、狂騒の 20 年代の過剰と偽善の風刺だった。この映画は、この風刺を 1950 年代という繁栄と非常に強力な家父長制の戦後文化に書き換えている」。
実際に映画の終わりの方で、家父長制への風刺があからさまに示唆されている場面があります。婚約者の父であるエズモンド・シニアに金目当てで結婚しようとしているのではないかと言われたローレライが、それに対して次のように言い返します。
「男性がお金持ちであることは、女の子が美しいのと似たようなことだってお分かりにならない? その子が可愛いという理由だけでは結婚しないかもしれませんが、おやまあ、それって役に立つのではありませんか? 娘さんが結婚するとしたら、貧しい男と結婚しないほうがいいとお思いになりませんこと?」
この後、エズモンド・シニアが驚きながら、君は人から聞いていたほど愚かじゃないようだと言うと、ローレライは次のよう答えます。
「賢さが重要なときにはそうなれますわ。でも、ほとんどの男性は賢いのが嫌いですから」。
以下の動画で、上記の台詞を含んだシーン全体をご覧ください。
目を丸くしたり、唇を尖らせたりしながらローレライが堂々と自説を語り続けていましたね。 前述の記事‘Gentlemen Prefer Blondes is bubbly and smart, just like Marilyn Monroe’の中でCaroline Siede氏が「1950年代のミュージカル・ロマンティック・コメディは伝統的なジェンダーの役割が支配するまじめで健全なものだったという考えを直ちに覆す。それは今日でも生意気で破壊的だと感じられる」と述べていますが、まさにその通りだと実感する一場面です。
こうして書いてきた流れからすると、この映画の中で流れる最も有名な曲であると同時にポップ・カルチャーの歴史全体の中でも最も有名な曲の一つと言える「ダイヤモンズ・アー・ア・ガールズ・ベスト(Diamond’s Are a Girl’s Best)」に言及しないわけにはいかなくなりました。
「ダイヤモンズ・アー・ア・ガールズ・ベスト」は、もともと1949年のブロードウェイ版の『紳士は金髪がお好き』のためにジュール・スタイン(Jule Styne)が作曲し、レオ・ロビン(Leo Robin)が作詞し、主演のキャロル・チャニング(Carol Channing)が歌ったジャズ・ソングです。
比較的最近のミュージカル映画をご覧になっている方だったら、2001年のバズ・ラーマン(Baz Luhrmann)監督の映画『ムーラン・ルージュ(Moulin Rouge! )』でサティーン役を演じたニコール・キッドマン(Nicole Kidman)が歌った曲として記憶されているのではないでしょうか?
ここでは、『紳士は金髪がお好き』の中でマリリン・モンローが「ダイヤモンズ・アー・ア・ガールズ・ベスト」を歌う場面を以下でご覧ください。
パリでのショーに出演したマリリン・モンロー演じるローレライが婚約者のガス・エズモンド・ジュニアへと向かって「ダイヤモンズ・アー・ア・ガールズ・ベスト」を歌っている場面です。この動画には含まれていませんが、歌が終わったとき、ローレライの婚約者は愕然としてしまいます。というのも、男性からの愛なんかよりも、ダイヤモンドの方がもっと価値があると自分に向かって歌われたからです。以下に歌詞の一部を紹介しておきます。
「男たちは冷たくなるわ/女の子は年を取るし/そして最後に私たちはみんな魅力を失うのよ/でもスクエア・カットでもペアシェイプでも/これらのダイヤモンドたちはその形を失わない/ダイヤモンドは女の子の最高の友達よ(Men grow cold/As girls grow old/And we all lose our charms in the end/But square-cut or pear-shaped/These rocks don’t loose their shape/Diamonds are a girl’s best friend)」
非常に率直な歌詞ですね。もちろん、こういった歌詞は、女性が愚かにも物質主義的なのだという性差別的な固定観念を永続させてしまうという意味で女性蔑視を助長するという意見もあるでしょう。ですが一方で、男性支配の世界が女性を物のように使い捨てるのだとしたら、その世界から永遠に裏切らないもの――愛ではなくダイヤモンド――を手に入れた方がよっぽどいいというこの歌の主張は、1950年代の拝金主義と家父長制への皮肉かつ風刺のようにも聞こえてきます。
ところで、ファッションに関心のある方だったら、この場面でマリリン・モンローが身に着けている大きなリボンのついたピンクのドレスに目を奪われることは間違いありません。モンローの衣装を数多く手がけているデザイナー、ウィリアム・トラヴィラ(William Travilla)によってデザインされたこのドレスは、その後のポップ・カルチャーのアイコニックな衣装のひとつになりました。
とりわけ1980年代のポピュラー・ミュージックに詳しい方だったら、あのマドンナ(Madonna)が自身のイメージを決定づけることになった「マテリアル・ガール(Material Girl)」のミュージック・ビデオで、このマリリン・モンローのドレスを模した衣装を身に着けていたことをご存じかと思われます。
「マテリアル・ガール」は1984年のアルバム『ライク・ア・ヴァージン(Like a Virgin)』からのシングルとして1985年1月23日にリリースされ、アメリカのビルボード・ホット100で第2位を記録しています。以下で「マテリアル・ガール」のミュージック・ビデオをご覧ください。
このメアリー・ランバート(Mary Lambert)が監督したミュージック・ビデオでは、マリリン・モンローのパフォーマンスが意図的に模倣されているだけでなく、ご覧の通り、背景の階段やシャンデリア、またタキシードを着た大勢のコーラス・ボーイなど『紳士は金髪がお好き』での場面が再構成されています。そして、ポスト・ディスコ時代に特徴的なメリハリの効いたビートのダンサブルな曲(ちなみにプロデューサーはナイル・ロジャースです)に合わせて、耳の奥まで貫くかのようなマドンナの独特の声が次のように歌っています。
「現金を持っている男がいつだって理想の男性だからよ/だって私たちは物質世界に生きているのよ/それで私は物欲の強い女の子なのよ(’Cause the boy with the cold hard cash is always Mister Right/’Cause we are living in a material world/And I am a material girl)」
「マテリアル・ガール」では、「ダイヤモンド」ではなく「現金」が言及されていますが、この曲の歌詞は男性の愛以上に物質的なものをやはり求めています。
ですが、このミュージック・ビデオをじっくりとご覧になった方はお気づきの通り、俳優のキース・キャラディーン(Keith Carradine)が演じるハンサムな男性のプロデューサーが、マドンナが演じる女優の心を掴もうと目録むという「マテリアル・ガール」の歌詞自体にはない(歌詞の内容に反しさえする)次のようなストーリーが組み込まれています。
マドンナ演じる女優の心をお金で手に入れることはできないと気づいたプロデューサーは、終盤に近付いた場面で、高価な贈り物ではなく、自分で摘んできたかのような素朴な白い花(マーガレット)を手に持って楽屋に姿を現わして、彼女を喜ばせます。さらにその後、自分が裕福ではないふりをするために、労働者の男へ大金を払って古いトラックを借ります。そこにピンクのドレスではなく白い服を着たマドンナが現れ、そのトラックの助手席に喜んで乗り込みます。最後には彼とマドンナが親密なキスをしているシーンが映し出され、プロデューサーの計画がうまくいったことが示されます。
そう、歌詞の内容とは裏腹にストーリーの中のマドンナはまったく「マテリアル・ガール」ではないのです。『紳士は金髪がお好き』のマリリン・モンロー演じるローレライだったら一蹴するはずの男性からの愛を受け取って、お金以上の大切なものを手に入れて幸せになったかのような結末です。
この歌詞と矛盾するミュージック・ビデオのメッセージをどう受け止めればいいのでしょうか? 物質主義が支配する世界の中で、その拝金主義的な価値観に惑わされない女性だからこそ、真の愛を見つけることができたということなのでしょうか? ですが、どうしても最初のシーンからの男性プロデューサーの動きを追っていくと、結局はあざといプレイボーイに女性が心を奪われてしまうという皮肉な話のようにも見えなくもありません。
いずれにしても、その後に年を重ねてからのマドンナの実人生での生き方は「マテリアル・ガール」のイメージから離れ、スピリチュアル(霊的)な方へと向かっていきます。ファンの方ならご存じのように、とりわけ1990年代半ば頃からのマドンナは、ヒンドゥー教や仏教などに関心を示し、ヨガを実践し、またロサンゼルスのカバラ・センターにも通うようになり、神秘主義的な教えへと完全に深く傾倒していきます。
ついでに言うと、自分で翻訳した本の宣伝のようになってしまいますが、マドンナの秘教的な思想とのかかわりについては、ピーター・ビーバガル著『シーズン・オブ・ザ・ウィッチ』という本の第6章にも簡潔にまとめられています。ご興味のある方はぜひそちらをお読みください。
今回は、1953年の映画『紳士は金髪がお好き』の中のマリリン・モンローのヒョウ柄の衣装に目を向けるとともにともに、その中の最もアイコニックな曲「ダイヤモンズ・アー・ア・ガールズ・ベスト」に注目してみました。そして、その関連でマドンナの「マテリアル・ガール」のミュージック・ビデオについても触れてみました。
次回は、さらに「ヒョウ柄」の象徴的な意味の変遷を追っていくため、1958年の魔女を題材にした映画『媚薬(Bell, Book and Candle)』を振り返ってみたいと思います。
この記事が気に入ったら下のボタンでシェア!
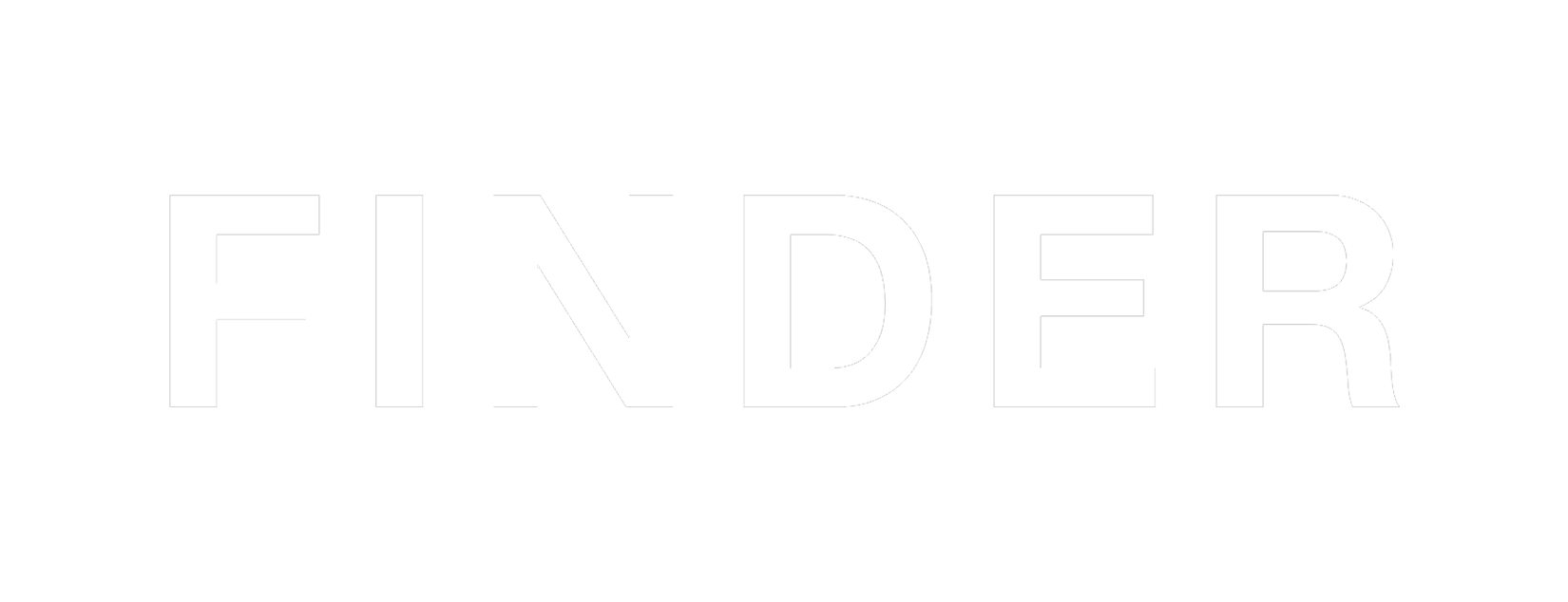 映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど
映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど





