最近の投稿
魔力の象徴としての「ヒョウ柄」:映画『媚薬』(1958年)の魔女ギルの衣装とインテリアから見る50年・・・映画『媚薬』(1958年)の中のビートニクな魔女とジャズが流れる占星術クラブ
「醜い老婆」から「若い女性」の姿へと変わっていく魔女(witch): 映画『オズの魔法使い』(193・・・
男性支配の物質主義的な世界の中で女性たちが求めること:映画『紳士は金髪がお好き』で「ヒョウ柄」の衣装・・・
記号としての「アニマル柄」:1934年の映画『特急20世紀』と1945年の『失われた週末』の中で「ヒ・・・
カテゴリ
フード&ドリンクビデオ・ゲーム
映画ポスター
ブック・カバー
ファッション
映画
インテリア
建築
音楽
ミュージック・ビデオ
コマーシャル映像
車・バイク
テレビ・シリーズ
アニメーション
アーカイブ
2024年1月2023年12月
2023年11月
2023年7月
2023年6月
2023年5月
2023年4月
2023年3月
2023年2月
2023年1月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
ブログについて
映画やTVドラマなどを観ていて、その中で流れてくる音楽、撮影に使われた建築やセットのデザイン、舞台の背景となるインテリア、登場人物が手にしているガジェットやプロダクトなどが気になったことはありませんか?
このブログでは、映画やTVドラマの中に登場するさまざまなものを調べて紹介していきます。そうしたものにも目を向けてみると、映画やTVドラマが今まで以上に楽しくなるはずです。映画、TVドラマ、音楽、建築、インテリアのどれかに興味がある方に、また自分と同じようにそのどれもが寝ても覚めても好きでたまらないという方に、面白いと思ってくれるような記事を発見してもらえたらという思いで書いています。
執筆者:伊泉龍一(いずみりゅういち)
ブログ以外には、以下のような書籍の翻訳をしたり、本を書いたりもしています。

ショーン・レヴィ著 伊泉龍一訳
『レディ・ステディ・ゴー! 60sスウィンギン・ロンドン』
伊泉龍一 (著)
『スピリチュアリズムの時代 1847-1903』
ポール・ガンビーノ (著), 伊泉 龍一 (監修, 翻訳)
『死を祀るコレクション:モダン・ゴシックという生き方、その住まい』
ドン・ラティン著 伊泉 龍一訳
『至福を追い求めて ―60年代のスピリチュアルな理想が 現代の私たちの生き方をいかに形作っているか』

ロバート・C・コトレル 著 伊泉 龍一 訳
『60sカウンターカルチャー ~セックス・ドラッグ・ロックンロール』

ドン・ラティン 著
『ハーバード・サイケデリック・クラブ ―ティモシー・リアリー、ラム・ダス、ヒューストン・スミス、アンドルー・ワイルは、いかにして50年代に終止符を打ち、新たな時代を先導したのか?』

デヴィッド・ヘップワース 著
『アンコモン・ピープル ―「ロック・スター」の誕生から終焉まで』

サラ・バートレット 著
『アイコニック・タロット イタリア・ルネサンスの寓意画から現代のタロット・アートの世界まで』
映画『マリー・アントワネット』のポスト・パンクとニュー・ロマンティックの感性(1)ーースージー・アンド・ザ・バンシーズとアダム・アンド・ジ・アンツとバウ・ワウ・ワウ
映画 音楽 ミュージック・ビデオ / 2023.04.26
前回は、史上最もサンプリングされている70年代を代表するイギリスのハード・ロック・バンド、レッド・ツェッペリン(Led Zeppelin)の曲「ホウェン・ザ・レヴィー・ブレイクス(When the Revee Breaks)」のドラム・ビーツを使っている意外な曲の一例として、イギリスのシューゲイザー・バンド、チャプターハウスの「パール(Pearl)」という曲について書きました。
今回は、前回の最後に述べた個人的な疑問、チャプターハウスの「パール」とイギリスのロック・バンド、スージー・アンド・ザ・バンシーズ(Siouxsie and the Banshees)の「キス・ゼム・フォー・ミー(Kiss Them For Me)」のドラム・トラックの一部にそっくりな部分があるのはなぜなのかということについて書くつもりでいたのですが、前回最後に自問したように、あまりにも興味を持ってくれる人が少なそうな話題のような気もするので、その前に寄り道を。
今回は、一般的な映画ファンの方に少しでも関心を向けてもらうべく、ソフィア・コッポラ監督の2006年の映画『マリー・アントワネット(Marie-Antoinette)』を通して、まずはスージー・アンド・ザ・バンシーズを少し紹介してみようかとと思います。
では、さっそく以下で『マリー・アントワネット』の一場面をご覧ください。背景に流れているのは、スージー・アンド・ザ・バンシーズの1978年のデヴュー・シングルの「ホンコン・ガーデン」です。
イントロが軽快なストリングスの演奏で始まっていますね。ですが、このヴァージョンの「ホンコン・ガーデン」は、原曲そのままではありません。イントロの部分にアレンジが加えられた映画用のヴァージョンになっています。
このアレンジを行ったのは、マイク・ミルズ監督の2010年の『人生はビギナーズ(Beginners)』や2016年の『20センチュリー・ウーマン(20th Century Women)』などのスコアも書いているアメリカの作曲家ロジャー・ニール(Roger Neill)です。「ホンコン・ガーデン」の原曲を知っている人ならば、この軽快で優美なクラシック風のイントロをとても見事なアレンジだと思ったのではないでしょうか。
ロジャー・ニールは、その箇所のアレンジについて、次のように述べています。
「曲そのものとは対照的なものにしたかったのです。「ホンコン・ガーデン」のハーモニックな要素を採用し、非常に優美でさっぱりと軽い感じのオーケストラ・モードにアレンジしました。私たちは、 マリーと彼女の友人たちが舞踏会に向かって急いでいるときに、この曲を一種のまやかしにしたかったのです。というのも、それが18世紀の衣装のドラマから期待されるような音楽に最初は聴こえるからです――そう聴こえなくなるまでは。(VOGUEのKEATON BELL氏の記事‘‘It Was Like Hosting the Ultimate Party’: An Oral History of Sofia Coppola’s Marie Antoinette’から引用)
確かにロジャー・ニールの語っている「まやかし」の目論見は見事にうまくいっているのではないでしょうか。そもそもスージー・アンド・ザ・バンシーズの「ホンコン・ガーデン」を聴いたことがない人だったら、このイントロの段階だけだとクラシック音楽のようにも聴こえるはずです。
ここで、イントロにストリングスを使っていないオリジナルのヴァージョンの「ホンコン・ガーデン」をお聴きください。イントロは、オリエンタルな雰囲気のフレーズを奏でる木琴の音に、普通にはなかなか思いつかなさそうな印象的なギターのリフが重なって始まります。
「ホンコン・ガーデン」のリリース時のことを改めて調べてみると、UKシングル・チャートで7位にまで上がっていました。
そもそも1978年と言えば、ロンドンのパンク・ムーヴメントを起動させたセックス・ピストルズ(Sex Pistoles)が解散した年です。つまり、ロンドンの音楽シーンの流れで言えば、同年の「ホンコン・ガーデン」は、ポスト・パンク、さらにはニュー・ウェィヴと呼ばれることになるサウンドへと移行していこうとしていた過渡期を象徴する曲です。
INDEPENDENTの中のGraeme Ross氏の記事‘Playlist: 10 best new wave singles of 1978’(1978年のニュー・ウェイヴ・シングルのベスト10)では、「ホンコン・ガーデン」が8位に選ばれています。ちなみに、ベスト10は以下の通りです。
10位 マガジン(Magazine) – 「ショット・バイ・ボズ・サイズ(Shot by Both Sides)」
9位 イアン・デューリー・アンド・ザ・ブロックヘッズ( Ian Dury and the Blockheads) – 「ホワット・ア・ウェイスト(What a Waste)」
8位 スージー・アンド・ザ・バンシーズ(Siouxsie and the Banshees) – 「ホンコン・ガーデン(Hong Kong Garden)」
7位 トーキング・ヘッズ(Talking Heads) – 「テイク・ミー・トゥー・ザ・リヴァー(Take Me to the River)」
6位 パティ・スミス・グループ(Patti Smith Group) – 「美コーズ・ザ・ナイト(Because the Night)」
5位 パブリック・イメージ・リミテッド(Public Image Ltd) – 「パブリック・イメージ(Public Image)」
4位 エルヴィス・コステロ・アンド・ジ・アトラクションズ( Elvis Costello and the Attractions) – 「レディオ・レディオ(Radio Radio)」
3位 アンダートーンズ(The Undertones) – 「ティーンエイジ・キックス(Teenage Kicks)」
2位 バズコックス(The Buzzcocks) – 「エヴァ―・フォールン・イン・ラブ(Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn’t’ve))」
1位 オンリー・ワンズ(The Only Ones) – 「アナザー・ガール、アナザー・プラネット(Another Girl, Another Planet)」
当時の音楽が好きだった方には、このアーティスト名と曲名の羅列を見ただけでも郷愁の念がこみあげてくるのではないでしょうか? そんな方は今日この後、かつてのポスト・パンクなスピリットを蘇らせるべく、これら懐かしの曲を聴きまくって過ごすというのはいかがでしょう。
映画『マリー・アントワネット』の方に話を戻します。改めて、この映画の公開当時のレヴューにあれこれ目を向けてみると、評価は極端な賛否へと分かれていました。
否定的なレヴューの方では、概ねその理由となっているのが、同映画でのさまざまな描写が、歴史的な事実に忠実ではないこと、それに加えて現代の曲をサウンドトラックに使用しているといった点のようです。確かに、いわゆる普通の「時代劇」的な映画を求めて観てしまったならば、不満を言いたくなるのも分かります。
しかしながら、逆に考えてみましょう。先ほどの18世紀末の貴族たちの仮面舞踏会の場面、普通だったら、それにふさわしい当時の優雅なクラシック音楽を使うはずです。なのにもかかわらず、そこにスージー・アンド・ザ・バンシーズの「ホンコン・ガーデン」をあえて流すなどということを、よくも思いついたものだと思いませんか?
このことについて監督のソフィア・コッポラ(Sofia Coppola)は、VOGUEの2021年10月29日のKEATON BELL氏の記事‘‘It Was Like Hosting the Ultimate Party’: An Oral History of Sofia Coppola’s Marie Antoinette’の中で、こう述べています。「最初から現代の音楽を使うことを考えていました。クラシック音楽が、あの同じ感覚を呼び起こすようには思えなかったのです」。
そもそもコッポラは、子供の頃にアントニア・フレイザー(Antonia Fraser)による伝記『マリー・アントワネットーーザ・ジャーニー(Marie Antoinette: The Journey)』を読み夢中になったそうです(同書は、野中邦子氏の訳で早川書房から翻訳書が出ています)。そして、その本の中で最も衝撃だったのは、「マリーの犬が取り上げられ、森の中でオーストリアの服を脱がされたとき」であり、「これが実際、マリーの人生の中で最も劇的な瞬間の一つだった」とコッポラは述べています(実際、マリーがフランス王太子との結婚のためにオーストリアからフランスに連れてこられたときは、まだ14歳でした)。
要するに、コッポラが少女の頃に共感したマリー・アントワネットの物語を描こうとしたわけですね。従って、着眼点は通常の政治面を強調した歴史では当然なくなります。コッポラが言うには「マリーだったら自分の人生についての映画をどのように見せたいと思うだろうか?」という観点から取り組むことになるわけです。「彼女[マリー・アントワネット]の人生を学問的な型にはまった形ではなく、若々しくガーリーな感じに解釈」しようしたともコッポラは述べています。
そこでコッポラは、ティーンエイジャーだったマリーの感受性を表現するために、この映画の音楽を自分自身のティーンエイジャーのときの音楽と関連づけることにしました。それに関してコッポラはこうも述べています。「子供の頃に大好きだった アダム・アンド(Adam Ant) のミュージック ビデオのような感じにしたかったのです」。
ここでコッポラが言及しているアダム・アントは、70年代末から80年代初頭にポスト・パンクからニュー・ウェイヴ及びニューロマンティック・ムーヴメントへというイギリスのミュージック・シーンの流れの中で人気のあったアダム・アンド・ジ・アンツ(Adam and the Ants)のシンガーです。
例えば、以下の1981年のアルバム『プリンス・チャーミング(Prince Charming)』からのシングルで、UKシングルチャートの1位となった「スタンド・アンド・ディリバ(Stand and Deliver)」のミュージック・ビデオをご覧ください。コッポラが「アダム・アントのミュージック ビデオのような感じにしたかった」と言っているのが、なるほどとうなずけます。
冒頭で、曲の題名通り、アダム・アントが裕福な貴族の馬車を襲う「追いはぎ」を演じていますね。曲調もメイクも衣装も何もかもが、ただ観ていて楽しくなるミュージック・ビデオです。間違いなく子供たちは大好きになりそうですね。ソフィア・コッポラは次のようにも述べています。
「私が80 年代に大人に向かっていったので、その時代と最初に触れたのは、アダム・アンド・ジ・アンツのようなバンドを通じてだったのです。 そのニュー・ロマンティックなレンズを通して、18世紀のフランスにアプローチするのは面白くなるだろうと思ったのです」。
「ニュー・ロマンティック」ということに関して言えば、映画『マリー・アントワネット』で音楽監督を務めたブライアン・ライツェル(Brian Reitzell)が、同じくVogueの記事の中で、次のようなことも述べています。
「ソフィアは好きなアーティストの写真や、彼女の想像力をとらえたファッション写真を、ゼロックスで複写していた。その 写真の 1つは、バウ・ワウ・ワウが [エドゥアール・] マネの絵画 [草上の昼食(Le Déjeuner Sur L’Herbe)] を再現したものだった。 そのニュー・ロマンティックな感性全体が取り掛かるときからの映画の精神だったんだ」。
ブライアン・ライツェルが述べている「マネの絵画」というのは、これです。以下の画像は、WIKIPEDIAの‘Le Déjeuner sur l’herbe’から引用しました。

さらに、この19世紀のフランスの画家エドゥアール・マネの絵画「草上の昼食」を「再現した」バウ・ワウ・ワウ(Bow Wow Wow)の写真というのが以下です。画像はDiscogsの‘Bow Wow Wow – The Last Of The Mohicans’から引用しました。

確かにしっかりと再現していますね。パンクな解釈ですが。
これはイギリスのニュー・ウェーヴのバンド、バウ・ワウ・ワウの1982年にリリースされた4曲入りEP盤『ザ・ラスト・オブ・ザ・モヒカンズ(The Last of the Mohicans)』のカヴァーです。また、この写真は、その当時デュラン・デュランやスパンダー・バレーなどのニュー・ロマンティックのバンドのアルバム・カヴァーなどを撮影していたことでも知られる写真家アンディ・アール(Andy Earl)によるものです。
確かに裸体の女性も含め、しっかりと「再現」していますね。で、その裸体の女性はバウ・ワウ・ワウのシンガーのアナベラ・ルーウィン(Annabella Lwin)なんですが、なんと当時まだ14歳でした。The GuardianのCraig McLean氏の記事‘Bow Wow Wow haven’t lost their bite’によると、このルーウィンの裸体の写真は、彼女の母親にショックと怒りを与えたようです。
ポスト・パンク時代の音楽に詳しい方はご存じのように、そもそもバウ・ワウ・ワウは、以前にセックス・ピストルズを売り出したファッション・デザイナーのマルコム・マクラーレン(Malcolm McLaren)のいわばその次のプロジェクトでした。つまり、セックス・ピストルズのときもそうですが、非難を浴びる過激な話題作りは、マクラーレンの得意とするところなわけです。
先ほどのアダム・アンド・ジ・アンツもマクラーレンがマネージしていました。そして、当初13歳だったシンガーのアナベラ・ルーウィンの周りに、アダム・アンド・ジ・アンツからメンバーを移動させてバウ・ワウ・ワウが作られました。そして、バンドのメンバーたちには、マクラーレン本人がヴィヴィアン・ウェストウッド(Vivienne Westwood)と一緒にデザインしていたパンクな服を着させたわけです。
ちなみに、マルコム・マクラーレンについては、GQ日本語版にフレッド・ヴァーモレル氏の記事の日本語訳「パンクの父、マルコム・マクラーレンが遺したもの」がありますので、ぜひそちらをお読みください。
また、山田耕史氏の『山田耕史のファッションブログ』の中の記事「SM趣味をファッションにしたパンクの父、マルコム・マクラーレン」では、DU BOOKSから2016年に出版された桜井真砂美氏による翻訳本『ヴィヴィアン・ウェストウッド自伝』とともに、ファッション・デザイナーとしてのマクラーレンについて紹介されていますので、こちらもどうぞお読みください。
バウ・ワウ・ワウは、ヴィジュアル的に映画『マリー・アントワネット』の「ニュー・ロマンティックな感性」の源泉となっただけでなく、曲自体もしっかりと使われています。そのサウンドトラックとなった3曲の中から、ここでは先ほどのEP盤『ザ・ラスト・オブ・ザ・モヒカンズ』の一曲目の「アイ・ウォント・キャンディ(I Want Candy)」が流れてくる場面をご覧ください。
いわゆる「ボ・ディドリー・ビート(Bo Diddley beat)」のアフリカンなリズムに乗って心浮き立たせる曲が始まり、すぐさま美しく豪華な服や靴やジュエリー、そして続いて、色鮮やかなスイーツや贅沢なシャンパーニュを楽しんでいる場面が流れ始めます。そしてその間、「キャンディが欲しい(I want candy)」という単純な歌詞が繰り返されて、初めてこの曲を観いた人でも、そのフレーズが耳に残ってしまうはずです。
ここのシーンは、物欲をこの上なく満たす少女たちのほんの束の間のきらきらとした夢のような時間です。その最高に「ガーリー」な場面の喜びと軽薄さを「アイ・ウォント・キャンディ」が表現してくれているわけです。
先に引用したソフィア・コッポラの「クラシック音楽が、あの同じ感覚を呼び起こすようには思えなかったのです」という言葉の通り、ここでクラシックからどんなに軽快な曲を選んだとしても、当然ながら、この場面での心浮き立つ「ガーリー」な感じを作り出すことはできないでしょう。
ここに出てくる衣装やジュエリーがどれほど高級なものだとしても、映画の流れからすると、この場の雰囲気には優雅さや気品はむしろ不必要です。何といってもここで表現されなければらないのは、あくまでティーンの女の子たちが感じている物質的なものの美や快や贅沢への純粋な喜び、そして曲が止まった瞬間に映し出される、その後の倦怠感ですからね。
ちなみに、先ほど「ボ・ディドリー・ビート」と言いました。聞き慣れない言葉だと思われた方も当然いると思いますので、一応ごく簡単に説明を加えておくと、アフリカンの伝統音楽の中でハンド・ベルを使ったリズム・パターンに由来するビートの一つのことです。50年代後半のロックンロールに詳しい方ならご存じのアメリカのギタリストでシンガーのボ・ディドリーの曲でとりわけ有名になったため、「ボ・ディドリー・ビート」と呼ばれるようになりました。
ここでボ・ディドリーの1955年の曲「ボ・ディドリー」を聴いてみてください。「アイ・ウォント・キャンディ」が、「ボ・ディドリー・ビート」を単に使っているばかりか、曲自体もかなり似ていることが分かるはずです。以下は、ボ・ディドリーが1955年11月20日の『エド・サリヴァン・ショー(The Ed Sullivan Show)』に出演したときの映像です。
ついでの話をすると、「アイ・ウォント・キャンディ」は、バウ・ワウ・ワウのオリジナル曲ではありません。ニューヨークのバンド、ストレンジラバーズ(The Strangeloves)の1965年のシングルのカヴァー曲です。ちなみに、この曲のプロデューサーは、リチャード・ゴッテリア(Richard Gottehrer)で、以前の記事で書いたゴーゴーズのデヴュー・アルバムもプロデュースしています。ストレンジラバーズによるオリジナルが気になる方は、以下でどうぞ。
こちらストレンジラバーズのオリジナルの「アイ・ウォント・キャンディ」も、この上なくハッピーなパーティー・ソングですね。もしかすると最近はあまり使われない昭和的な表現の言葉かもしれませんが、心を「ウキウキ」させてくれると言うのがぴったりの曲だと思います。夏の暑い日中に外でサングラスをしてピナ・コラーダでも飲んでいるとき、背景に流れてきたら、間違いなく幸せな気分になれそうです。
もう一つだけ「アイ・ウォント・キャンディ」について細かい話をします。実際に映画『マリー・アントワネット』で使われている「アイ・ウォント・キャンディ」は、バウ・ワウ・ワウの「アイ・ウォント・キャンディ」を、ケヴィン・シールズ(Kevin Shields)がリミックスしたヴァージョンです。
ケヴィン・シールズと言えば、ちょうど前回の記事でチャプターハウス(Chapterhouse)という「シューゲイザー」のバンドの話をしましたが、それとたまたま関係があります。そう、ケヴィン・シールズは、その分野の頂点に位置するともいうべきバンド、マイ・ブラッディ・バレンタイン(My Bloody Valentinee)のシンガーでギタリストでした。
ファンの方はご存じの通り、ケヴィン・シールズがソフィア・コッポラと仕事をしたのは、この『マリー・アントワネット』だけでなく、2003年の映画『ロスト・イン・トランスレーション(Lost in Translation)』ではオリジナルの楽曲も提供しています(この映画については、また別の機会に)。
ふと思いまいしたが、前回のチャプターハウスの曲を聴いて「シューゲイザー」にちょっと興味がわいたけど、よく知らないという方も当然いらっしゃいますよね。なので、前回の記事のときに紹介しておけばよかったのですが、遅ればせながらお勧めの本を。
佐藤一道氏と黒田隆憲氏の『シューゲイザー・ディスク・ガイド revised edition』(シンコーミュージック、2021年)です。情報量も非常に多いので、これを熟読しながら、気になった音源を聴いていると、かなりのシューゲイザー通になれそうです。気になる方はぜひお読みください。
また、RollingStoneには、同書の著者の一人である黒田隆憲氏による「マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン、ケヴィン・シールズが語る過去・現在・未来」というケヴィン・シールズの貴重なインタヴュー記事が掲載されています。さらにMikikiの中にも「黒田隆憲のシューゲイザー講座」という連載記事があります。そのちょうど第2回目で「シューゲイザーはどうやって生まれた? ケヴィン・シールズの足元から辿る、美しい轟音の作り方と甘やかな浮遊感のルーツ」という記事がありますので、どうぞこちらもお読みください。
さらにエレキギターの総合情報サイト『エレキギター博士』の中にもケヴィン・シールズのギター・サウンドに焦点を合わせた記事「ケヴィン・シールズ」がありました。こちらもどうぞご覧ください。
映画『マリー・アントワネット』とポスト・パンクやニュー・ロマンティックとのつながりについて、このまま書き続けるとまだまだ長くなりそうなので、今回はこの辺で終わりにして、続きは次回にします。
この記事が気に入ったら下のボタンでシェア!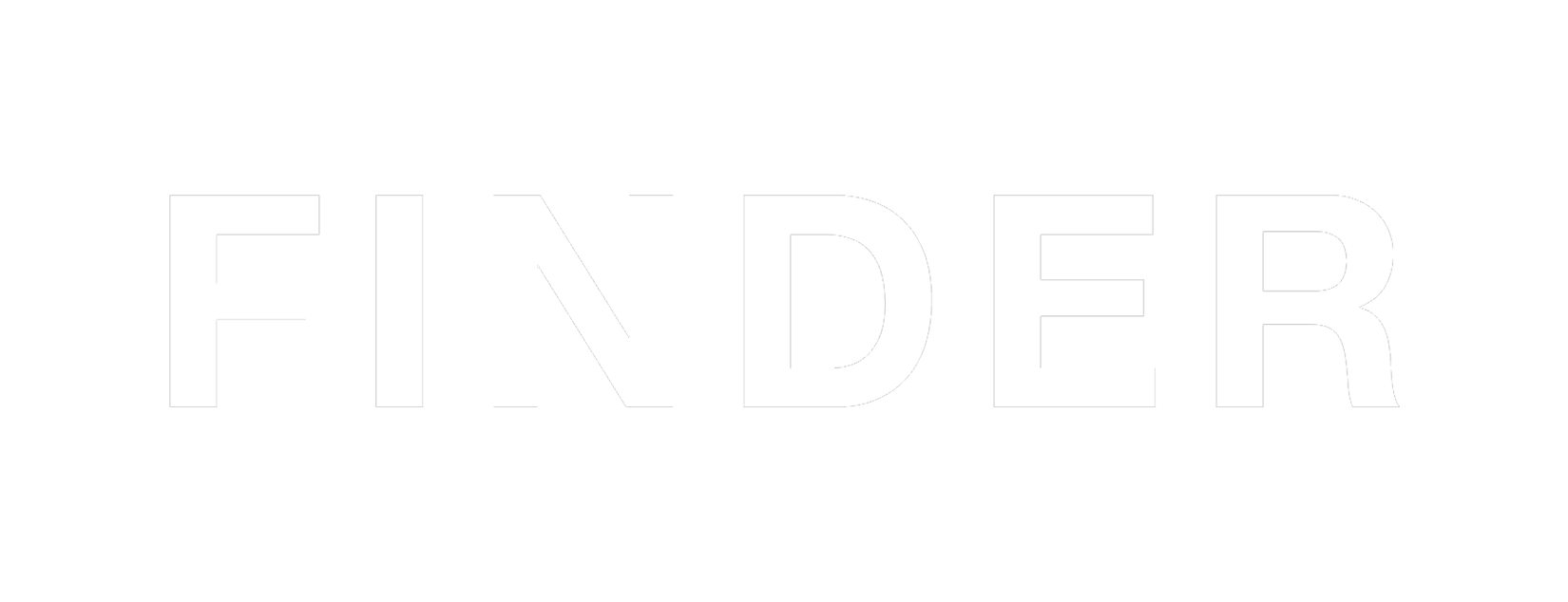 映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど
映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど





