最近の投稿
魔力の象徴としての「ヒョウ柄」:映画『媚薬』(1958年)の魔女ギルの衣装とインテリアから見る50年・・・映画『媚薬』(1958年)の中のビートニクな魔女とジャズが流れる占星術クラブ
「醜い老婆」から「若い女性」の姿へと変わっていく魔女(witch): 映画『オズの魔法使い』(193・・・
男性支配の物質主義的な世界の中で女性たちが求めること:映画『紳士は金髪がお好き』で「ヒョウ柄」の衣装・・・
記号としての「アニマル柄」:1934年の映画『特急20世紀』と1945年の『失われた週末』の中で「ヒ・・・
カテゴリ
フード&ドリンクビデオ・ゲーム
映画ポスター
ブック・カバー
ファッション
映画
インテリア
建築
音楽
ミュージック・ビデオ
コマーシャル映像
車・バイク
テレビ・シリーズ
アニメーション
アーカイブ
2024年1月2023年12月
2023年11月
2023年7月
2023年6月
2023年5月
2023年4月
2023年3月
2023年2月
2023年1月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
ブログについて
映画やTVドラマなどを観ていて、その中で流れてくる音楽、撮影に使われた建築やセットのデザイン、舞台の背景となるインテリア、登場人物が手にしているガジェットやプロダクトなどが気になったことはありませんか?
このブログでは、映画やTVドラマの中に登場するさまざまなものを調べて紹介していきます。そうしたものにも目を向けてみると、映画やTVドラマが今まで以上に楽しくなるはずです。映画、TVドラマ、音楽、建築、インテリアのどれかに興味がある方に、また自分と同じようにそのどれもが寝ても覚めても好きでたまらないという方に、面白いと思ってくれるような記事を発見してもらえたらという思いで書いています。
執筆者:伊泉龍一(いずみりゅういち)
ブログ以外には、以下のような書籍の翻訳をしたり、本を書いたりもしています。

ロバート・C・コトレル 著 伊泉 龍一 訳
『60sカウンターカルチャー ~セックス・ドラッグ・ロックンロール』

ドン・ラティン 著
『ハーバード・サイケデリック・クラブ ―ティモシー・リアリー、ラム・ダス、ヒューストン・スミス、アンドルー・ワイルは、いかにして50年代に終止符を打ち、新たな時代を先導したのか?』

デヴィッド・ヘップワース 著
『アンコモン・ピープル ―「ロック・スター」の誕生から終焉まで』

サラ・バートレット 著
『アイコニック・タロット イタリア・ルネサンスの寓意画から現代のタロット・アートの世界まで』
『ツイン・ピークス』の後のジュリー・クルーズ(5)――ロバート・アルトマン監督の映画『バレエ・カンパニー』とヘンリー・マンシーニの「ルージョン」
ここ数回、デヴィッド・リンチ監督のドラマ『ツイン・ピークス(Twin Peaks)』で「フォーリング(Falling)」などを歌い有名になったシンガー、ジュリー・クルーズ(Julee Cruise)のその後の音楽活動を少し追ってみました。特に前回は、90年代末から2000年代初頭にかけてのジュリー・クルーズが歌っている音楽は、さまざまなミュージシャンとのコラボレイションをしながら、当時最新のエレクトロニカに乗って歌っているのを見てきました。
今回は、まずアメリカの映画製作者ロバート・アルトマン(Robert Altman)が監督した2003年の映画『バレエ・カンパニー(The Company)』の中で非常に印象的に使われているジュリー・クルーズの歌う「ザ・ワールド・スピンズ(The World Spins)」を、美しいバレエとともにご覧ください。。
「ザ・ワールド・スピンズ」は、ジュリー・クルーズの1989年のファースト・アルバム『フローティング・イントゥ・ザ・ナイト(Floating into the Night)』の中の最後に収録されていますが、以前に述べたように『ツイン・ピークス』の中でも使われています。それにしても、『バレエ・カンパニー』のダンスの場面に合わせて聴くと改めて実感しますが、同じ曲でも映像との組み合わせによって、かなり違った印象になりますね。「Love/Don’t go away/Come back this way/Come back this way/Forever and ever(ラブ/行かないで/こちらの方へ戻ってきて/こちらの方へ戻ってきて/果てしなく永遠に)」という歌詞をまさに表現しているようなロープにつながったダンサーの見事な動きによって、この曲自体が『ツイン・ピークス』とはまるで別の世界を想像させる音楽へと変容させられているようにすら感じられます。
『バレエ・カンパニー』は、バレエのお好きな方ならお馴染みの映画かもしれませんが、シカゴのダンス・カンパニー、ジョフリー・バレエ(Joffrey Ballet)を題材にした映画です。本作の主演はネーヴ・キャンベル(Neve Campbell)です。キャンベルと言えば、ジューリー・クルーズの曲が使われているということで、このブログの少し前の記事で言及した1996年のウェス・クレイヴン(Wes Craven)監督の映画『スクリーム(Scream)』で、ヒロインのシドニー・プレスコット(Sidney Prescott)を演じていた女優です。
ちなみに、ホラー映画ファンの方には周知の通り、『スクリーム』はいわゆるスラッシャー映画として当時最後の興行収入(全世界で1億7300万ドル)を記録し、その後の同映画のシリーズ作品の始まりとなりました。そして、第2作(1997年)、第3作(2000年)、第4作(2011年)、第5作(2022年)と製作され、その間、ネーヴ・キャンベルは25年にわたり、主役のシドニー・プレスコット役を演じ続けています(5作目は日本では劇場未公開でしたが、DVD&ブルーレイも発売されていますし、これを書いている現時点(2022年12月14日)ではU-NEXTとNetflixでも見られます)。また、TVシットコム『フレンズ(Friends)』のファンには嬉しいことにも、コートニー・コックス(Courteney Cox)がゲイル・ウェザーズ(Gale Weathers)役として、1作目から5作目まで全てに出演しています。
この一連の『スクリーム』のシドニー・プレスコット役での印象的な姿から、ネーヴ・キャンベルと言えば、どうしてもスクリーム・クイーン的なイメージが強いのはやむを得ないでしょう。ですが、この『バレエ・カンパニー』でのまったく違う役柄と演技を観れば、彼女のイメージが完全に一変すること間違いありません。
そもそもネーヴ・キャンベルは映画出演以前の子供の頃から、カナダの国立バレエ学校で訓練を受け、プロのダンサーをしていました。CNN.COMでのネーヴ・キャンベルのインタヴュー記事によると、ケガのために9年間ダンスを休んでいたにもかかわらず、他の役柄を演じるジョフリー・カンパニーのダンサーたちに引けを取らないよう自分の体を鍛え直すべく、1日8時間半のトレーニングを6カ月間続け、その後、同カンパニーで1ヵ月半、バレエを学んだそうです。
同インタヴューの中でキャンベル自身、次のようにも述べています。「とりわけ私自身がプロのダンサーだったので、あのカンパニーに入って、その基準に達しないようなことは決してしたくありませんでした」。
『バレエ・カンパニー』をご覧になっていない方は、ひとまず以下のトレイラーをご覧になってみてください。ネーヴ・キャンベルの踊っている姿が少し観られますし、ジュリー・クルーズの「ザ・ワールド・スピンズ」も冒頭から流れてきます。
『スクリーム』でシドニー・プレスコット役を演じるネーヴ・キャンベルも魅力的であることは言うまでもありませが、彼女のダンサーとしての情熱を感じさせてくれるのは、やはりこの『バレエ・カンパニー』での本当に見事な踊りの場面ですよね。
実際に『バレエ・カンパニー』は、キャンベルが長年温めていたアイデアだったようです。キャンベルは自身の原案を脚本化するのに、アメリカの画家ジャクソン・ポロック(Jackson Pollock)の伝記を基にした2000年の映画『ポロック 二人だけのアトリエ(Pollock)』の脚本を書いたことでも知られる女優で脚本家のバーバラー・ターナ(Barbara Turner)に依頼し、さらにロバート・アルトマンを説得して監督を引き受けてもらったとのことです。当初のアルトマンは、脚本を受け取った読んだものの戸惑いがあったようで、それに対して次のように述べたそうです。「バーバラ、君の脚本を読んでも、納得できないよ。理解できないんだ。それが何なのか分からない。私はとてもじゃないがこのためにふさわしい人間じゃないよ」(引用はRogerEbert.comでの同映画に対するRoger Ebert氏のレヴューから)。
ちなみに、ご覧になっていない方に言うと、バレエを題材にしているということから想像されるような、主人公が失敗の涙を流しながらも根性で厳しいコーチの訓練に耐え抜き、恋愛や人間関係の悩みも乗り越えて成功する的な感動の物語ではまったくありません。ただひたすらダンス・カンパニーの様子を淡々と描いている映画です。なので、感動させて泣かせようとする意図が丸見えの山あり谷ありの鬱陶しいストーリーが苦手な人でも、心落ち着けてバレエの練習や舞台の場面を集中して観ることができる映画です(逆に劇的なドラマを期待して観てしまった場合、意味不明な映画と思われる可能性もあります)。キャンベルは前述のインタヴューの中で次のように述べています。
「バーバラと私は最初から、この映画はアルトマン的でなければならないと話していました。なぜなら、道を踏み外した少女がバレリーナになるとか、コーラス隊にいた少女が主任になりたいと願い、そうなるといった映画を作りたくなかったからです。私たちはそのようなストーリをこれまで見てきましたし、少々飽き飽きしていますよね?それに、それはダンスの世界について多くを語るものではありませんし」。
個人的な感想を加えて言えば、しょうもない映画の場合だったら、ハラハラさせて盛り上げようとするような終盤のある出来事のシーンも、きわめてあっさりと通過していき、結果、その終わりも観ていて素晴らしく清々しい気持ちにさせてくれます。そういう意味で考えると、ネーヴ・キャンベルの原案とバーバラ・ターナーによる脚本は本当によくできていると思います。その一方で、監督のロバート・アルトマンが最初に脚本を読んだときに、「理解できない」と言った気持ちも分からないでもありません。
ところで、『バレエ・カンパニー』のサウンドトラックについて言えば、ジャズの歴史に残る超スタンダードな曲「マイ・ファニー・ヴァレンタイン(My Funny Valentine)」が、何度もさりげなく流れてくるのが、ご覧になった多くの方の印象に残ったのではないでしょうか?
「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」は、アメリカの作曲家リチャード・ロジャース(Richard Rodgers)と作詞家ロレンツ・ハート(Lorenz Hart)によって作られ、ニューヨークのブロードウェイのシュバート劇場で1937年に上演されたミュージカル『ベイブス・イン・アームス(Babes in Arms)』の劇中で、10代のミッツィ・グリーン(Mitzi Green)演じるビリー・スミス(Billie Smith)が歌ったのが世に出た最初となったそうですが、その後、数多くのミュージシャンによってカヴァーされて、今や誰もがどこかで聴いたことがある程の超有名な曲になっていることと思います。
『バレエ・カンパニー』の中では、「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」の複数のヴァージョンが流れますが、その中には日本でも熱心なファンが非常に多いと思われるアメリカのジャズ・ミュージシャン、チェット・ベイカー(Chet Baker)によるヴァージョンも含まれています。
チェット・ベイカーの滑らかにゆったりと流れていくような歌い方と中性的にも聴こえる歌声のテクスチャーが、じんわりと心に染み入ってきますね。「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」の最高のカヴァーとして、チェット・ベイカーの歌うヴァージョンを選ぶ人たちの気持ちもよく分かります。
もう一つ『バレエ・カンパニー』で使われている別の「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」も、よろしければお聴きください。こちらはイギリスのシンガーソングライター、エルヴィス・コステロ(Elvis Costello)の歌う「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」です。
この「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」は、エルヴィス・コステロの1979年のアルバム『アームド・フォーシズ(Armed Forces) 』からのシングル「オリヴァーズ・アーミー(Oliver’s Army)」のB面として収録されています。ちょっと鼻にかかった独特の声で、抑揚をつけて力強く歌うコステロの「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」も、これまたぐっときます。『バレエ・カンパニー』の中ではビリヤードをしているネーヴ・キャンベル演じるロレッタ・「ライ」・ライアン(Loretta ‘Ry’ Ryan)を、相手役のジェームズ・フランコ(James Franco)演じるジョシュ・ウィリアムズ(Josh Williams)が見つめるシーンのバックで、さりげなく使われています。
ここでふと想像したくなるのが、もしジュリー・クルーズが「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」をカヴァーして歌っていたらどうだったのかということです。間違いなく、ナイト・クラブにぴったりのドリーミーな雰囲気に包まれた曲に仕上がっていたのではないでしょうか。それに近い雰囲気(ジュリー・クルーズがもし「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」を歌っていたらに近い雰囲気)を想像させてくれるのが、何と言っても彼女の2002年の3枚目のアルバム『ジ・アート・オブ・ビーイング・ア・ガール(The Art of Being a Girl)』なのではないかとも思います。このアルバムは、『ツイン・ピークス』の頃とはサウンド的にも大きく異なり、またそれに伴いジュリー・クルーズの歌い方もかなり変化しています。
今回このジェリー・クルーズの3枚目のアルバムについても、本当は書きたいと思っていたのですが、結局ロバート・アルトマン監督の映画『バレエ・カンパニー』主演のネーヴ・キャンベルと「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」の話につい流れてしまいましたので、続きはまた次回に。
この記事が気に入ったら下のボタンでシェア!
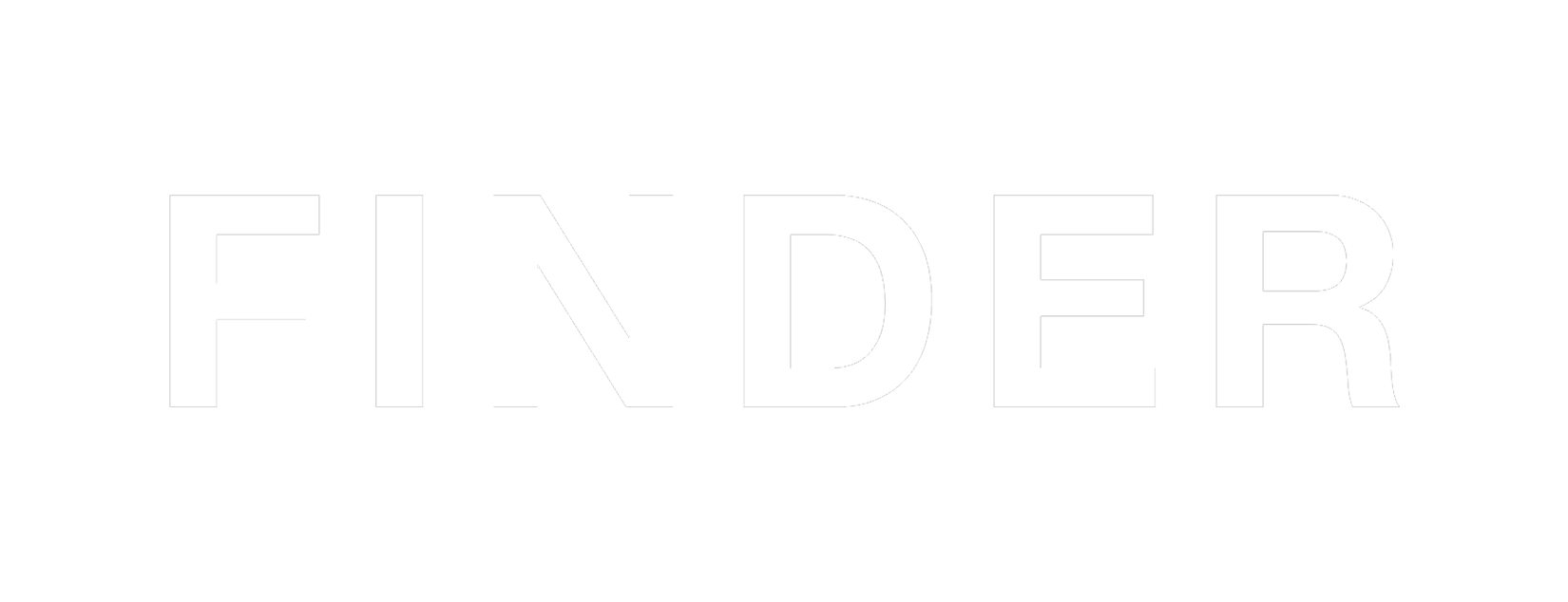 映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど
映画・TVドラマの中の音楽・インテリア・建築・デザインなど


